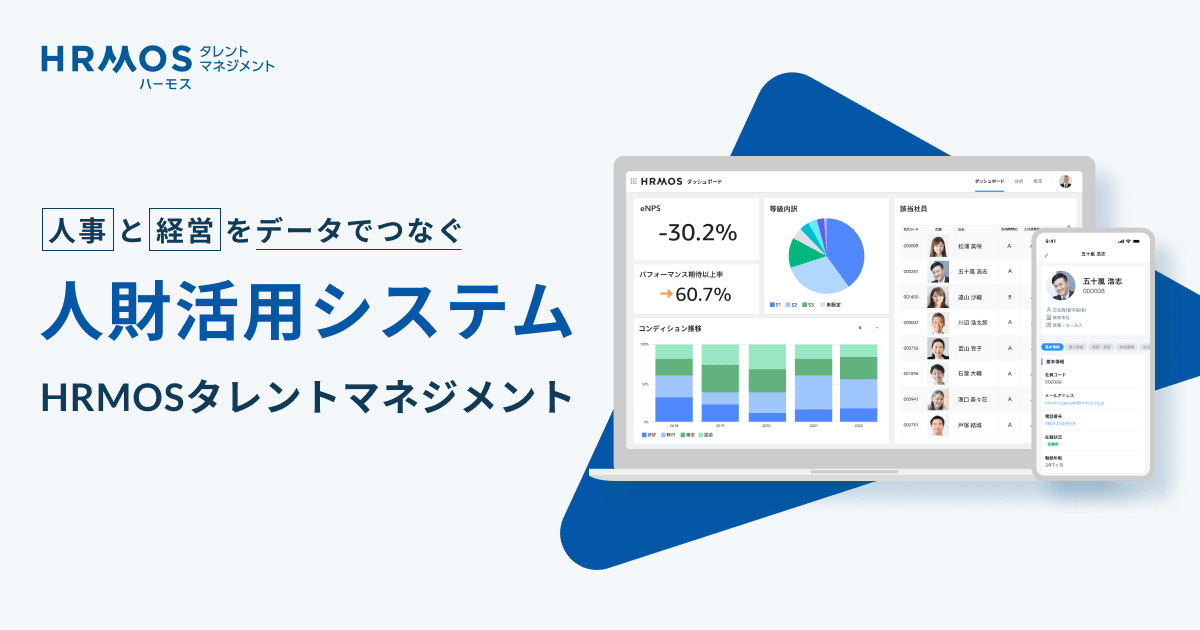目次
自然災害、サイバー攻撃、急激な市場変化など、企業を取り巻くリスクは年々多様化しています。
予測不可能なリスクに備え、企業経営を継続するには、リスクと適切に向き合って対策を講じることが求められています。
本記事では、企業が直面する代表的なリスクの種類、実務に役立つ管理手法、活用できる資格やフレームワークなどをわかりやすく解説します。
リスクマネジメントとは
はじめに、リスクマネジメントの意味や目的、企業がリスクマネジメントに取り組む必要性について説明します。
リスクマネジメントの定義
国際標準(ISO 31000)では、リスクは「目的に対する不確実性の影響」と定義されています。これは、予期せぬ出来事や不確実な要因により生じる損失や悪影響の可能性を意味します。
リスクマネジメントとは、こうしたリスクを特定・評価し、適切に対処することで、組織が目標を達成するためのプロセスを指します。
中小企業庁は、リスクマネジメントを「リスクを組織的に管理し、損失等の回避または低減を図るプロセス」と定義しています。
また、「企業経営におけるリスクを正確に把握し、事前に対策を講じて危機の発生を防ぐ。さらに、危機が発生した場合でも損失を極小化するための経営管理手法」とも説明されています。
リスクマネジメントの重要性
リスクマネジメントは、企業が不確実性に備え、安定した経営を維持するために欠かせない戦略的手段です。
予期せぬ事態に直面しても損失を最小限に抑え、事業継続を可能にするために、事前予測と予防措置の実施が求められます。
さらに、的確な対応力は競争優位性を高めるだけでなく、新たな成長機会の創出にもつながります。単なる危機回避策にとどまらず、企業価値を高める重要な経営基盤といえるでしょう。
企業が直面するリスク
企業活動には常に多様なリスクが伴います。
それらを正しく理解し、適切に備えることは、組織の持続的な成長と安定した経営に欠かせません。ここでは、企業が特に意識すべき代表的なリスクの種類を紹介します。
戦略的リスク
戦略的リスクとは、経営方針や市場戦略の判断ミス、または戦略の前提となる外部環境の急変によって生じるリスクです。
例えば、新規事業の投資判断が期待に反する結果となる、あるいは競合の台頭によってシェアを奪われるなど、企業の方向性そのものに影響を与える可能性があります。
財務リスク
財務リスクとは、為替の変動、金利の上昇など、財務に関わる外的要因によって損失が生じるリスクです。
海外取引の多い企業では為替リスクが特に大きく、財務体質の強化や多様な資金調達手段の確保が、リスク耐性の鍵となります。
人材流出リスク
人材流出リスクとは、優秀な人材の流出や従業員の定着率低下など、人的資源に起因するリスクです。
特に専門性の高い職種においては、一人の離職が事業継続に影響を与えるケースも少なくありません。人材流出リスクに耐えられるような人材マネジメントが求められます。
コンプライアンスリスク
コンプライアンスリスクは、法令違反や社内規定違反、不正行為の発生などにより、企業の信頼や社会的評価を損なうリスクです。
情報漏洩や賄賂、ハラスメントなどが挙げられ、一度の違反が企業の存続に関わる重大な影響を及ぼす可能性があり、予防的な取り組みが欠かせません。
サイバーセキュリティリスク
サイバーセキュリティリスクとは、不正アクセスやマルウェア、内部からの情報漏洩など、情報セキュリティに関するリスクです。
テレワークやクラウド活用の拡大により、対策を怠るとシステム停止や個人情報の流出といった重大な被害につながるため、継続的なセキュリティ対策が不可欠です。
社会情勢リスク
社会情勢リスクとは、感染症の拡大、政治の不安定さや政策変更、経済危機など、社会の大きな変化に伴うリスクです。
近年では新型コロナウイルスや国際紛争、資源価格の高騰といった影響が企業活動に大きく及び、柔軟な意思決定と状況に応じたサプライチェーン管理が重要な対応策となります。
自然災害リスク
自然災害リスク(ハザードリスク)とは、地震、台風、洪水など、自然災害による事業中断や設備被害のリスクです。
特に工場や物流拠点が被災した場合、生産・供給体制に大きな混乱が生じる可能性があり、事業継続計画(BCP)の策定が不可欠です。
他にも、上記に当てはまらない業界特有のリスクや個別事情も多数存在します。
例えば、飲食業では食中毒リスク、建設業では労働災害リスク、観光業では風評被害や外国人渡航制限などが挙げられます。自社特有の業態・立地・顧客層に応じたリスク分析が重要です。
<関連記事>
BCP(事業継続計画)とは? BCP対策の手順や訓練内容、企業事例を解説
リスクマネジメントの4原則
リスクマネジメントにおける対応策は、主に4つの基本原則に分類されます。それぞれの考え方と代表的な実例を踏まえて解説します。
回避
回避とは、リスクが発生する要因そのものを除去することで、損失の発生を未然に防ぐ手法です。
例えば、重要な機密情報を取り扱う場合は、アクセス権限を厳格に管理し、情報の保存先を暗号化するなどの措置が該当します。
また、教育やマニュアル整備により、人為的なミスを未然に防ぐことも回避策の一つです。
低減
低減とは、リスクの存在を前提としつつ、その発生確率や影響範囲を最小限にとどめる取り組みです。
完全にリスクをゼロに抑えることが難しい場合に、現実的な対応策として用いられます。
例えば、自動車事故に備えてシートベルトを着用する、災害時の被害を抑えるために耐震補強を行うなどが典型例です。
リスクの可能性を下げると同時に、損失の広がりを抑えることに重点を置きます。
移転
移転とは、リスクによって生じる損失や責任の一部または全部を、第三者に委ねる方法です。
代表的な手段としては保険への加入があり、事故や災害時に金銭的損失を補填してもらうことが可能です。
また、システム運用を専門会社に委託することで、障害発生時の対応責任を外部に分担することもリスク移転に含まれます。
ただし、移転できるのは主に金銭的なリスクに限られ、すべてのリスクが対象になるわけではありません。
受容
受容とは、リスクの存在を理解したうえで、あえて対策を講じず現状を容認する意思決定です。
たとえば、影響が小さく、対策にかかるコストが高すぎる場合などが該当します。
日常業務の中で起こりうる些細なトラブルに対して、都度対応を行い、保険加入などの対策を取らない選択が典型です。
重要なのは、「対策をしない」こともまた、明確な経営判断であるという点です。
システムを活用した企業の改善事例多数
株式会社サンリオ、トヨタカローラ山形株式会社、株式会社GA technologiesなど、どのような効果が得られたのか分かる事例を公開中
リスクマネジメントの基本プロセス
リスクへの対応は、単発の施策ではなく継続的な取り組みとして捉える必要があります。
企業の業種・規模・外部環境によってリスクの形は異なるため、状況に応じた柔軟な判断が求められます。ここでは、リスクマネジメントを進める上での標準的な4ステップを紹介します。
リスクの特定
はじめに、事業上で発生し得るリスクを洗い出し、特定を行います。経営層の視点だけでなく、現場の知見も取り入れ、あらゆる角度からリスクの可能性を洗い出します。
リスクの洗い出しを行ったら、それぞれの影響範囲や発生頻度などで分類し、事業継続への影響度が高いものを優先的に特定します。
リスクの分析・評価
続いて、特定したリスクごとに「どのくらい起こりやすいか」「どの程度の損害があるか」を数値化し、客観的な分析を行います。
点数による優先順位づけや、業界ベンチマークとの比較などを通じて、対応すべきリスクの重要度を明確にします。
例えば、頻度と損害額でリスクの重みをスコア化することで、どのリスクに先に対応すべきかが明確になります。
リスク対応戦略の選択
分析を経て優先度が明らかになったら、それぞれのリスクに対する具体的な対応方針を決定します。
回避・低減・移転・受容の4つの方法をベースに、自社にとって実行可能かつ効果的な手段を選びましょう。
損害保険の活用や外部委託といった手段も活用し、状況に応じた柔軟なリスク対策を講じることが重要です。
モニタリングとレビュー
リスクマネジメントは一度で終わる活動ではありません。実施した対策が適切に機能しているかを継続的に観察し、必要に応じて見直すことが求められます。
事業環境の変化や新たなリスクへの対応力を高めるには、PDCAサイクルを活用して定期的にチェック体制を整え、改善点を見直しながら、必要に応じて是正措置を講じることが求められます。
リスクマネジメントの国際標準とフレームワーク
企業がリスクマネジメントを組織的に導入するにあたり、指針となる国際規格やフレームワークの活用は不可欠です。
世界的に広く用いられている基準には、それぞれ異なる視点や強みがあります。ここでは代表的な3つの枠組みを紹介します。
ISO 31000
ISO 31000は、リスクマネジメントの国際的な原則を明確化した規格です。
あらゆる業種・組織に適用可能な枠組みとして、リスクの特定から評価、対応、見直しに至る一連のプロセスを体系化しています。
当規格は、経営層の関与とコミットメントの重要性が強調されており、ISO 31000の導入により、組織全体での方針共有が促進されます。
また、リスクマネジメントを単なる防御策ではなく、戦略実行の一部と位置づけています。
COSO ERM
COSO ERM(Enterprise Risk Management)は、アメリカのCOSO(米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会)が2004年に発行したフレームワークです。
ERMとは、全社的なリスクマネジメントのことで、経営や事業目標の達成のためにCOSO ERMを活用します。
当フレームワークでは、リスクを脅威だけでなく「機会」として捉える点にあります。
内部統制・財務報告といった枠を超えて、組織文化や意思決定にリスク視点を組み込むことを目的としています。
ガバナンスとの連動や、企業価値の最大化に向けたリスク感度の高い経営を支援する枠組みです。
NIST サイバーセキュリティフレームワーク
NIST CSF(Cybersecurity Framework)は、米国国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology)が2014年に策定したサイバーセキュリティ対策のガイドラインです。
特にITやインフラ領域の企業にとって実用性が高く、「識別・防御・検知・対応・復旧」の5つの機能に基づく構成が特徴です。
企業のセキュリティ成熟度に応じた柔軟な導入が可能で、近年では日本企業にも導入が進んでいます。
・「なんとなく」や特定の人の勘 に頼った配置 から脱却したい
↓
従業員のスキルを可視化し、組織の課題を可視化。評価・育成記録まで 一元管理 し、データに基づいた配置を実現
⇒デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
リスクマネジメントに役立つ専門資格
企業がリスクマネジメントに取り組む上で、専門知識を体系的に習得している人材の存在は大きな価値を持ちます。
企業のガバナンスや内部監査、サイバーリスク管理に関わる実務担当者にとって有益な国際資格を紹介します。
CRMA(R)
「CRMA®」(Certification in Risk Management Assurance)は、IIA(内部監査人協会)が提供する、リスクマネジメントと内部監査に関する国際資格です。
特に、内部監査の観点から経営のリスク管理体制を評価・助言する役割を担う人材に適しています。
内部統制やガバナンス強化を進める企業では、監査部門や経営企画に所属する担当者が取得を目指すことが想定される資格です。
CRISC
CRISC(Certified in Risk and Information Systems Control)とは、日本語で「公認情報システムリスク管理者」と呼ばれる資格です。
ITガバナンスの専門団体ISACA(情報システム監査・管理に関する国際団体)が認定する、ITリスクと情報システム統制に特化した資格です。
ITガバナンス、セキュリティ、事業継続など、デジタル化の進展に伴うリスクのマネジメントに強みを発揮します。情報システム部門やリスクマネジメント部門、内部統制の担当者などにとって信頼性の高いスキル証明となります。
CFE
CFE(Certified Fraud Examiner)は、公認不正検査士とも呼ばれる不正調査と防止の専門家として認定される資格です。
アメリカのACFE(公認不正検査士協会)が認定しています。
会計不正、汚職、横領などの企業内の不正を調査・防止するための資格で、再発防止策の立案までを担う専門職向けに設計されています。
監査部門、法務、内部統制の実務者にとって、コンプライアンス強化の柱となるスキルセットです。
自社にも応用できるリスクマネジメント事例
さまざまな業種・規模の企業が、それぞれの環境に応じたリスクマネジメントを実践しています。以下では、具体的な取り組みを行っている3社の事例を紹介します。
豊田通商株式会社
豊田通商のリスクマネジメントは、グローバル全体を対象とした統合的な体制を構築しています。
COSO-ERMの考え方を取り入れた「統合リスク管理委員会」が中心となり、重点リスクを毎年評価・可視化(Check10活動)し、全社的に対策を講じています。
また、財務健全性を保つため「リスクアセット(RA)」と「リスクバッファー(RB)」という想定される最大の損失と、それに耐えられる企業の財務力を指標化し、損失許容範囲内での経営を実践しています。
株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは、変化の速いネット業界に対応するため、柔軟な事業転換やAI活用など積極的なリスクマネジメントを展開しています。
社内では、経営陣と従業員が新規事業や経営課題を議論する「あした会議」、従業員が感じるリスクを全社から吸い上げる「リスクGEPPO」などを活用し、早期の課題発見と改善に取り組んでいます。
情報セキュリティやガバナンス体制も強化し、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。
株式会社カネキ吉田商店
株式会社カネキ吉田商店は、東日本大震災による全工場の被災という深刻な状況に対して、即座に原料を確保し、代替生産拠点を確保することで事業を再開しました。
同社では、2010年のチリ地震をきっかけに、年2回の避難訓練や研修の実施、従業員への継続的な情報共有を徹底。
その備えが、災害発生時の的確な初動対応につながりました。
被災後は保険の見直しや財務体制の強化を進め、将来の災害リスクに備える仕組みを整備しています。
これらの取り組みにより、同社は危機からの回復と事業継続の両立に成功し、自然災害に対するリスクマネジメントの好例となっています。
リスクマネジメントと類似する概念・手法との違い
リスクへの対応には多くの関連概念が存在しますが、それぞれの目的やアプローチには違いがあります。リスクマネジメントと混同されやすい代表的な用語との違いを整理して解説します。
リスクヘッジ
リスクヘッジとは、主に金融リスクに対して損失を回避・軽減するために取られる戦術的な対処法を指します。
例えば、株式を分散投資したり、為替変動リスクに対して先物取引を活用したりするなど、主に金銭的な損失回避が目的です。
一方、リスクマネジメントはそれより広義で、リスクの特定・分析・対応・見直しといった一連のプロセスを含むより包括的な経営手法です。
リスクヘッジは、このプロセスの中で活用される具体的な対処手段の一つと位置づけられます。
内部統制
内部統制は、企業が法令遵守や財務の信頼性、業務の有効性を確保するために整備する仕組みのことです。企業内部のリスクを対象とし、組織内の不正防止や業務の適正化に重点が置かれます。
一方、リスクマネジメントは内部・外部を問わず、あらゆるリスクに対処する包括的なプロセスであり、両者は相互に補完し合う関係にあります。
強固な内部統制は効果的なリスクマネジメントの土台となります。
危機管理
危機管理(クライシスマネジメント)とは、地震やシステム障害、不祥事など「発生してしまった重大なリスク」に対して、迅速かつ適切な対応を講じて早期復旧を図る取り組みです。
事後の対応が中心となるのが特徴で、初動の速さや対応体制の整備が鍵となります。
一方、リスクマネジメントは「起こる前の準備」に主眼を置き、未然防止と損害最小化に重きを置いて、計画的に動きます。両者を連携させることで、リスクの予防から発生時の対応までをカバーした、より堅牢な経営体制の構築が可能となります。
リスクマネジメントの未来
企業を取り巻く環境の変化とともに、リスクマネジメントも進化を続けています。
デジタル技術の発展や社会課題への対応を背景に、今後のリスクマネジメントは、より戦略的かつ即応性の高い体制へと移行しつつあります。
AIとデータアナリティクスの活用
近年では、AIによる予測技術の進歩や自然言語処理を活用した高度なレポート分析など、リスク可視化の手段が急速に進化しています。
大量のデータをもとにリスク傾向を予測・分析することで、判断の精度を高め、より迅速かつ的確な事前対応が可能となります。
AIを活用したリスクアナリティクスの反復により、データの精度向上も期待でき、データに基づくリスクマネジメントの意思決定が主流となり始めています。
<関連記事>
デジタルトランスフォーメーションとは?DX推進で企業・組織を改革する際の課題や企業事例などを解説
リアルタイムリスクモニタリングの高度化
従来は定期的なレビューを中心としていたリスクモニタリングも、今やリアルタイム化が進んでいます。
IoTセンサーやクラウド連携により、サプライチェーンやITインフラにおける異常を即時に検知できる体制が整いつつあります。その結果、被害の拡大前に迅速な意思決定と対策を講じることが可能になります。
持続可能性とリスクマネジメントの融合
近年、温暖化による豪雨や異常気象が多発しており、環境リスクに対する取り組みが、世界的に重要視されています。
自然災害、環境、社会リスクを最重要課題と捉え、サステナビリティーの取り組みとリスクマネジメントを統合する姿勢が企業に求められています。
<関連記事>
サステナビリティ経営とは? 意義や取り組み、SDGsとの違いを詳しく解説
まとめ
リスクマネジメントとは、企業や組織を取り巻く多様なリスクを体系的に管理し、損失の回避・軽減を図ることで、企業価値の向上を目指すプロセスです。
今後はAI活用やサステナビリティーといった新たな視点を取り入れながら、リスクマネジメントはより戦略的な経営ツールとして進化していくと考えられます。
HRMOSタレントマネジメントで実現する人材リスクマネジメント
従業員の情報をHRMOSタレントマネジメントで一元管理し、評価・配置・育成・エンゲージメントまでを可視化することで、離職やスキル不足、配置ミスといった人材リスクへの対応が可能になります。
感覚ではなくデータに基づく意思決定を支援し、組織の安定と持続的な成長を後押しするタレントマネジメントを活用してみませんか。