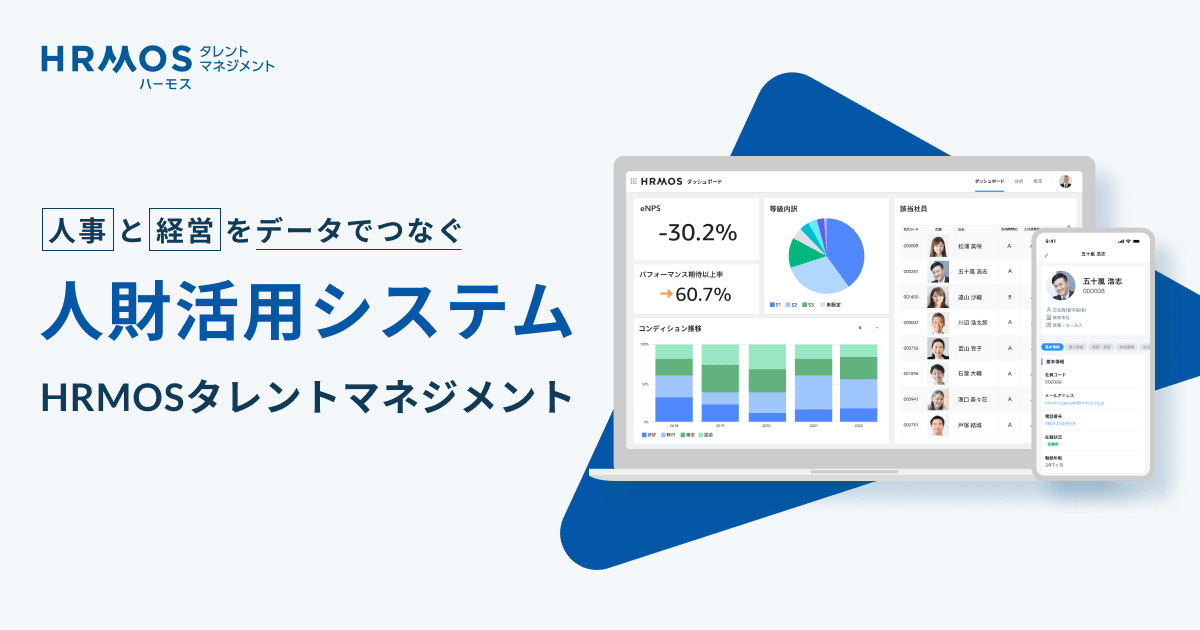目次
多様な人材の強みや個性を生かすためには、深い相互理解が重要です。
本記事では、自己理解、他者理解を促す心理学的ツール「ジョハリの窓」の概要や使い方、メリット、注意点について解説します。
ジョハリの窓とは
ジョハリの窓(Johari Window)とは、自己理解と対人コミュニケーションの円滑化に役立つ心理学的フレームワークです。
1955年に、アメリカの心理学者ジョセフ・ラフト(Joseph Luft)とハリー・インガム(Harry Ingham)が、グループ・ダイナミクス(集団力学)の研究過程で開発されました。両名の名前からそれぞれの頭文字を取って、「Johari(ジョハリ)」と名づけられました。
ジョハリの窓では、自分が自覚している自分(自己認識)と、他者が知っているが自分では気づいていない自分など、自己と他者の認識のズレや重なりを4つの領域に分類し、可視化します。
これにより、自己理解を深めるだけでなく、他者との関係性やフィードバックの受け止め方にも気づきが生まれます。
このフレームワークは、就職・転職活動における自己分析をはじめ、職場での人事評価、リーダーシップ開発、チームビルディングなど、幅広いシーンで活用されています。
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
ジョハリの窓の4つの領域を詳しく解説
ジョハリの窓は「自分が知っているかどうか」「他人が知っているかどうか」という2つの視点で、自己を4つの領域に分類して捉えるフレームワークです。以下では、4つの窓の意味を説明します。

開放の窓:自他ともに知っている領域
「開放の窓(Open Area)」は、自分も他人も知っている情報(性格、強み、言動の特徴など)を指します。
例えば、ある従業員が「リーダーシップがある」「几帳面である」といった特性を自他ともに認識している状態です。
この領域が広いほど、相互理解が深まり、チーム内のコミュニケーションや信頼関係も良好になりやすくなります。
人事としては、1on1のような定期的な対話や、社内SNSのようにオープンなコミュニケーションの場を設けることで、開放の窓を広げることが可能です。心理的安全性の高い環境作りとも深く関係します。
<関連>
1on1ミーティングで話すことは?話題とすべき7つのテーマと20の質問事例
盲点の窓:他者のみが知っている領域
「盲点の窓(Blind Spot)」は、自分では気づいていないが、他人は知っている情報の窓です。
例えば、自分自身のことを「控えめな性格」と考えていても、他人からは「興味があることには積極的」と評価されるような場合が該当します。
盲点の窓が広いと、本人の意図と周囲の受け取り方にギャップが生まれやすくなるため、誤解や関係性の摩擦を引き起こす可能性があります。反対に、盲点の窓を知ることで、客観的に自己分析ができるといえるでしょう。
人事施策としては、上司や同僚からのフィードバック、360度評価の導入などが有効です。丁寧なフィードバック文化を作ることで、盲点の窓を小さくし、開放の窓を広げていくことができます。
秘密の窓:自分のみが知っている領域
「秘密の窓(Hidden Area)」は、自分は知っているが、他人には明かしていない情報を指します。
例えば、職場で本音を言わなかったり、本当は得意なスキルや経験を隠していたりするようなケースが挙げられます。
秘密の窓が大きいと、周囲との関係性が浅くなったり、本人の強みや能力が生かされにくくなったりする可能性があります。
人事としては、キャリア面談や1on1での信頼構築を通じて、従業員が安心して自己開示できる環境作りを行うことが重要です。
<関連>
1on1と人事評価面談の違いを解説。1on1は評価に活用できるか?
未知の窓:誰も気づいていない領域
「未知の窓(Unknown Area)」は、自分自身も他者もまだ気づいていない領域を指します。
例えば、トラブル時など予測不可能な状態での反応や、新規事業にアサインされたときのパフォーマンスなど、本人が経験したことのない場面での行動などが含まれます。
未知の窓はコントロールが難しい反面、新たな成長や変化の可能性が眠っている部分といえるでしょう。
従業員の未知の窓を他の窓に移すためには、新しい挑戦の機会を与えることや、本人の潜在意識を引き出すような対話が有効です。
ジョハリの窓を活用するメリット
ジョハリの窓は、自己理解と他者理解のギャップを可視化することで、個人の成長や組織内の信頼構築を促す心理学的フレームワークです。
ここでは、ジョハリの窓を活用することで得られる主な3つの効果を紹介します。
自己認識の向上と他者との認識のズレの発見
ジョハリの窓は、自身の行動や特性を客観的に振り返る機会を提供し、他者との認識の違いに気づくきっかけとなります。
自分では気づきづらい日々の言動の特徴や強み・弱みを、他者からのフィードバックを通じて把握でき、自己認識の精度が高まります。
自己認識を深めることは、マズローの欲求段階説の「自己実現」と関連性が高く、内発的なモチベーションの向上にもつながります。
また、自己認識の向上は、リーダー層の育成やキャリア開発においても重要な要素です。
例えば、1on1ミーティングや人事評価面談の場面で、本人が抱える「盲点」や「秘められた強み」を明らかにしていくことで、意欲や成長意識を引き出すことができるためです。
<関連記事>
モチベーション理論とは?理論の代表マズローの欲求5段階説の意味と種類を解説
コミュニケーション能力の向上
ジョハリの窓の「開放の窓」を意識的に広げることで、自己開示や相互理解が進み、対人関係における信頼性が高まります。
このプロセスは、傾聴力や共感力、フィードバック力といったコミュニケーションスキルの土台を強化します。
また、開放の窓を広げることは、心理的安全性の確保にもつながります。
自分の考えや感じたことを安心して共有できる関係性が構築されることで、職場における誤解や対立の予防にも有効でしょう。
<関連>
職場の心理的安全性とは?作り方や4つの因子、高める方法を解説
チームダイナミクスの改善
ジョハリの窓は、個人の自己理解を深めるだけでなく、チーム内の関係性やチームダイナミクスにもよい影響を与えます。
ジョハリの窓のワークを通して、自己開示とフィードバックを行い、メンバー同士がお互いの特性や価値観を理解し合えるようになります。その結果、コミュニケーションの行き違いが減少し、自然と協力しやすい雰囲気が生まれるでしょう。
従業員同士の関係性向上は、情報共有の活性化や意思決定の迅速化だけでなく、人間関係に起因する不安やストレスの軽減など、メンタルヘルスの改善にも寄与します。
チームダイナミクスの改善を通じて心理的安全性を高め、エンゲージメント向上や離職防止を図る上でも、ジョハリの窓を研修や1on1に取り入れることが有効です。
<関連記事>
人気のある企業は実践している!グループの効果を最大化するチームダイナミクスとは?
従業員エンゲージメントとは? 高める方法や事例から学ぶ成功のポイントを解説
納得感のある評価を効率的に行うための仕組みを整備し、従業員の育成や定着率の向上に効果的な機能を多数搭載
・360°フィードバック
・1on1レポート/支援
・目標・評価管理
・従業員データベース など
ジョハリの窓の具体的な活用シーン
ジョハリの窓は、単なる心理学的フレームワークにとどまらず、組織における人材開発や関係性構築の実践ツールとしても活用されています。
ここでは、ビジネスシーンでの代表的な活用例を紹介します。
企業研修での活用
ジョハリの窓は、自己理解を深める手段として、多くの企業研修や人材育成プログラムで導入されています。
自分自身の強み・弱みに向き合い、他者からのフィードバックを受け入れることで、従業員一人一人の気づきが促進されます。
研修では、ジョハリの窓のグループワークに加えて、「強みが生かされたエピソードの共有」や、「自分らしさを活かせる業務領域の発見」など、業務と連携性を持たせたワークを取り入れるのも有効でしょう。
ただし、自己開示に対して抵抗を感じる従業員も一定数存在するため、導入にあたっては、ワークの目的や進め方に対する事前の丁寧な説明が欠かせません。
1on1など社内のキャリア面談での活用方法
上司と部下で定期的に行う1on1ミーティングや、キャリア面談などでジョハリの窓を取り入れることも有効です。
上司が部下に対して「他者からどう見られているか」「自分の強み・弱みをどう捉えているか」といったフィードバックを行うことで、部下自身が気づいていない「盲点の窓」を狭めることができるでしょう。
一方で、部下が自身の価値観や悩み、今後のキャリアに対する考えを言語化し「秘密の窓」を開いていくことも、信頼関係の構築や相互理解の深化につながります。
人事評価における活用事例
ジョハリの窓は、360度評価の運用と非常に相性のよいフレームワークです。
360度評価では、上司・同僚・部下など複数の立場から受けるフィードバックを通して、本人が気づけなかった行動傾向や強み・課題が明らかになります。
これはまさに、ジョハリの窓における「盲点の窓」を明らかにし、「開放の窓」を広げるプロセスと同じです。
人事評価の場面では、ジョハリの窓を「評価のためのツール」ではなく、「自己理解を促す支援ツール」として位置づけ、上司・部下間のフィードバック文化の醸成に生かすとよいでしょう。
<関連記事>
360度評価とは?導入のメリットや項目例、成功のポイントを解説
360度評価のコメント例文と書き方!部下から上司など立場や職種別に解説
ジョハリの窓の診断方法とやり方
ジョハリの窓は、自己認識と他者認識のギャップを可視化するシンプルかつ有効なフレームワークです。ここでは、実際にジョハリの窓を実践するためのステップと注意点を解説します。
ワークシートの準備
ジョハリの窓を実践するには、まず専用のワークシートを用意します。
ワークシートは縦横2軸に分かれた4象限のマトリクス形式で、「自分が知っている/知らない」と「他者が知っている/知らない」の2軸で構成されます。
ジョハリの窓をオンライン上で実施できる無料アプリや無料テンプレートも豊富に公開されており、リモートワーク環境下でも実施が可能です。
中には複数人で匿名入力できるグループワーク向けのツールもあるため、実施規模や運用目的に応じて、適切な形式を選ぶとよいでしょう。
自分の性格、特性を書き出す
ワークの第1ステップは、「自分自身が認識している自分」を書き出すことです。具体的には、自身の性格や行動傾向、強み・弱みなどをを列挙します。
書き出す形式には、あらかじめ用意された特性リストから選択する方法と、自由記述形式で自身の言葉で表現する方法があります。
選択式の場合、以下のような特性を表す言葉を複数用意してから臨みます。
- 責任感がある
- 努力家
- 前向き
- 好奇心旺盛
- チャレンジ精神が強い
- リーダーシップがある
- 空気が読める
- 傾聴力がある など
ポジティブな特性だけでなく、自己改善につながるような「心配性」「せっかち」「ストレスに弱い」といった項目を取り入れると、より多面的な自己理解が得られるようになります。
他者から認識を記入してもらう
次のステップでは、上司・同僚・部下など複数の立場の人に、自分に対する印象や評価を記入してもらいます。
異なる関係性の人からのフィードバックを集めることで、より立体的な視点が得られるようになります。
また、匿名で実施することで、率直かつ忖度のないフィードバックを得ることが可能です。
他者からの認識を収集する際は、オンラインフォームや無記名の記入シートなどを活用するとよいでしょう。形式にかかわらず、事前に目的や方法をしっかり説明し、安心して参加できる環境を整えることが重要です。
4つの窓に分類してフィードバックを行う
自己記入と他者からのフィードバックがそろったら、これらの情報を4つの領域に分類します。
- 開放の窓
- 盲点の窓
- 秘密の窓
- 未知の窓
分類が完了したら互いに結果を共有し、フィードバックの時間を設けましょう。
特に「盲点の窓」には、複数人からの共通意見を分析し、「なぜそのように評価されているのか」を掘り下げることで、自分では気づかなかった一面への理解が進みます。
また、「秘密の窓」は、自らの価値観や考えを適切に開示することで、「開放の窓」を広げることができ、他者との信頼関係構築にもつながります。
・「なんとなく」や特定の人の勘 に頼った配置 から脱却したい
↓
従業員のスキルを可視化し、組織の課題を可視化。評価・育成記録まで 一元管理 し、データに基づいた配置を実現
⇒デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
ジョハリの窓を実施する際の注意点・デメリット
ジョハリの窓は、自己理解や相互理解を深める有効なフレームワークである一方で、導入に際してはいくつかの注意点やリスクも存在します。
ここでは、実施にあたって事前に押さえておきたい代表的な課題とその対策について解説します。
認識が正しいのかという問題
ジョハリの窓は、「自分自身が認識している自分」と「他者から見た自分」を比較・照合する手法ですが、前提としてある程度の自己認識が本人に備わっていることが求められます。
また、他者からの評価も必ずしも正しいとは限らず、関係性や状況によっては、偏見や主観に基づいた評価が含まれる可能性もあります。
例えば、新人や異動直後の従業員など、他者との接点が少ない状態でジョハリの窓を行うと、「盲点の窓」が実質的に機能しない場合があります。また、フィードバックを行うメンバーが限定されている場合、特定の意見が過度に影響を及ぼすリスクもあるでしょう。
このような事態を避けるためには、事前に性格診断などで自己分析の土台を作り、プロジェクトの中盤など一定の関係性が作られたタイミングで実施するなどの工夫が重要でしょう。
心理的負担になる可能性
ジョハリの窓を行う際は、従業員の心理的な負担を排除するように注意が必要です。
組織や他者に対し、信頼関係が十分に築かれていない状態で自己開示を求めると、かえって警戒心や不信感を抱かせてしまうおそれがあります。
また、ジョハリの窓の評価を過度に気にしてしまい、ストレスを感じる方もいます。
特に、盲点の窓が大きい場合、他人からのコメントに不快感を覚える可能性もあるでしょう。対策としては、フィードバックには前向きな表現や伝え方の工夫が求められます。
他にも、人間性を否定しないことや、プライバシーの配慮、匿名性など、ワークを行う際のルール作りにも留意しましょう。
ジョハリの窓以外の自己理解を深める方法
ジョハリの窓は、自己と他者の認識ギャップを可視化する優れたフレームワークですが、その効果を高めるためには、まず「自分自身をどれだけ理解しているか」が重要な前提となります。
ここでは、ジョハリの窓とあわせて取り入れやすい、代表的な3つの手法を紹介します。
マインドマップの作成
マインドマップは、中心となるテーマ(キーワード/単語)から関連する言葉やアイデアを放射状に広げて書き出す思考整理の手法で、自己分析や内省にも効果的です。
ジョハリの窓が「自分の特徴を認識し、他者と共有するプロセス」であることに対し、マインドマップはその前段階として、「自分の価値観や強みを棚卸しする」役割を果たします。
例えば、「仕事における自分の価値観」をテーマに、関連する経験や感情を書き出していくことで、自分が大切にしている考えや行動パターンが見えてきます。
マインドマップは手書きでもデジタルでも実践でき、人材研修やキャリア面談の場でも取り入れやすいアプローチです。
ジョハリの窓の事前準備として活用することで、より深い内省を引き出すことができるでしょう。
マインドフルネスの実践
マインドフルネスとは、雑念を取り払い、「今この瞬間」に意識を向けて自己の内面を観察する心のトレーニングです。
ビジネスパーソンの間でも注目が高まっており、集中力の向上やストレス軽減、自己認識力の向上といった効果が報告されています。
特に現代の職場では、他人からの評価、仕事のストレスなど外的な刺激が多く、自分の本来の感情や思考を見失いがちです。
マインドフルネスの実践は、そうした雑念を一度手放し、心の状態を整えることで、自分自身の反応や傾向に気づける点がメリットです。
マインドフルネスを取り入れることで、自己認識の精度を高めることができ、ジョハリの窓もより有効になると考えられます。
<関連記事>
マインドフルネスとは? 企業に導入する方法や瞑想のやり方、効果を解説
自己分析ツールの活用
ジョハリの窓を行う前に、自己理解を支援する診断ツールやアセスメントを活用することも有用です。
性格傾向や価値観、強み、行動特性などをツールで可視化すれば、本人の思い込みや曖昧な認識を正しやすくなるでしょう。
代表的なツールには、性格診断、適性検査、強み診断などがあり、特に「どのような環境でパフォーマンスを発揮しやすいか」や「どんな働き方が向いているか」のヒントを得ることができます。
こうした客観データを踏まえてジョハリの窓に取り組むことで、自己理解の幅をより広げることができるでしょう。
まとめ
ジョハリの窓は、個人の自己理解を深めるだけでなく、他者との関係性を整理し、組織内の信頼関係やコミュニケーションの質を高めるための有効なフレームワークです。
ジョハリの窓を実施する際は、無理な自己開示を求めずにポジティブな側面のみフィードバックするなど、一定の配慮が求められます。また、従業員自身の自己理解や職場の心理的安全性が確保されていることも、前提条件となります。
単なるワークで終わらせず、継続的な仕組みとしてジョハリの窓を取り入れて、従業員一人一人の価値発揮につなげていきましょう。
HRMOSタレントマネジメントで自己理解を促進しよう
HRMOSタレントマネジメントは、従業員一人一人のパフォーマンスや成長を可視化し、客観的なデータで意思決定を行う人材マネジメントシステムです。
HRMOSタレントマネジメントの「360度評価機能」を活用することで、従業員に多角的な視点からフィードバックを行うことができ、ジョハリの窓の「盲点の窓」を発見できます。
360度評価で「開放の窓」を広げながら、継続的な成長支援のサイクルを構築していきましょう。
HRMOSタレントマネジメントの機能一覧を見る