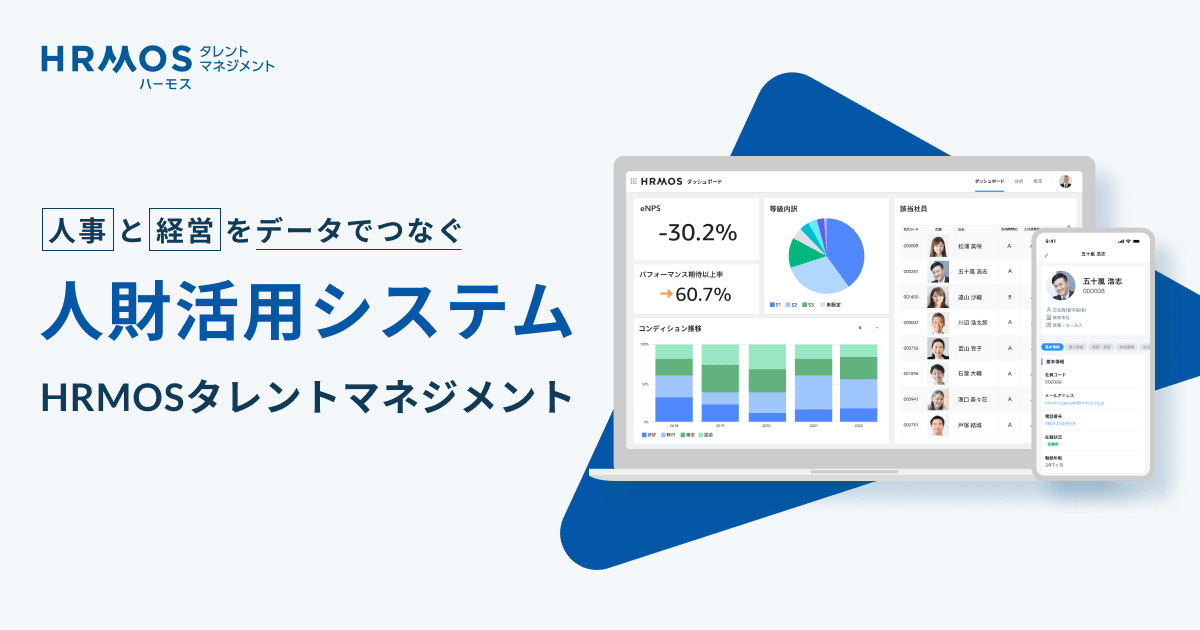目次
障がいがある人の就労を支援する制度にはさまざまなものがあり、国の「就労継続支援」もそのひとつです。障がいや難病があって一般企業での就労が難しい場合でも、就労継続支援を活用すればさまざまな業務に就くことができます。
働くうえで必要な知識や能力を向上でき、一般企業での就労に向けたステップアップとしても活用できます。
障がいのある方やそのご家族は、制度の内容を正しく理解し、適切に活用することが大切です。本記事では、就労継続支援の概要やA型とB型の違い、利用するメリットや利用時の手続きの流れを紹介します。
就労継続支援とは
就労継続支援とは、障がいがあり一般企業での就業が困難な人に雇用の機会を提供して、能力向上のための訓練を行う制度です。障がいや難病があるなど一定の要件に該当すると利用できます。
就労継続支援事業所で働きながら就業のための訓練を受けられる制度で、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。障害福祉サービスでは、利用者は原則として費用の1割を自己負担します。
ただし、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担なしで利用できます。
また、利用料には上限額があり、上限額(月額)は市町村民税課税世帯では9,300円、それ以外の世帯では37,200円です。障害福祉サービスを多く利用した月でも、自己負担額が上限額を超えることはありません。
就労継続支援事業所で実際に働く場合は、梱包やデータ入力、接客、清掃などの業務を担当し、給料や工賃が支払われます。企業は就労継続支援事業所に業務の依頼が可能です。
就労継続支援A型とB型の主な違い
就労継続支援にはA型とB型の2種類あり、利用できる人の要件や雇用契約の有無、支払われる報酬の種類が異なります。A型とB型は、いずれも「通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者」を対象としていますが、以下のような違いがあります。
| A型 | B型 | |
| 利用対象者 | 適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者 | 通常の事業所に雇用されていた障がい者であって年齢・心身の状態などにより引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者や、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者など |
| 年齢制限 | 原則として65歳未満(但し一定の要件を満たす場合は65歳以上でも利用可) | なし |
| 雇用契約の有無 | あり | なし |
| 報酬 | 給料 | 工賃 |
| 業務内容 | お菓子の製造レストランでの接客パソコンのデータ入力製品の部品組立清掃 など | 箱詰めシール貼り清掃 など(A型に比べて簡単な業務が多い傾向にある) |
B型はA型と異なり、雇用契約に基づく就労が難しい人が対象です。B型の事業所では、障がいの程度が比較的重度の人が働くケースなどが見られ、業務内容はA型の事業所よりも簡単な内容が多い傾向にあります。
A型では雇用契約を結ぶため、支払われる報酬は給料に該当し、最低賃金法の適用を受けます。一方でB型では雇用契約は結ばないため、支払われる報酬は給料ではなく工賃です。工賃は最低賃金法の適用対象外であり、A型に比べてB型は報酬額が低い傾向にあります。
厚生労働省が公表した2023年度のデータによれば、報酬の平均月額はA型事業所では86,752円、B型事業所では23,053円です。
<関連記事>
法定雇用率とは?計算方法や引き上げの背景、障害者雇用促進法との関係を解説
就労継続支援の利用方法と手続きの流れ
就労継続支援をはじめとした障害福祉サービスを利用するには、「障害福祉サービス受給者証」の発行が必要です。以下では、働く事業所を探す方法や受給者証の発行方法など、就労継続支援の利用方法を手続きの流れに沿って紹介します。
1.就労継続支援事業所の選定
就労継続支援事業所を探す主な方法は以下のとおりです。
- 自治体の窓口(障がい福祉課)や相談支援事業所で相談する
- ハローワークを利用する
- ネット検索で調べる
お住まいの自治体の市町村役場に行けば、就労継続支援に関する相談ができます。相談する窓口は一般的に障がい福祉関係を担当する部署です。ハローワークの窓口でも相談できます。
求人情報を検索できるサイト「ハローワークインターネットサービス」で障がい者向けの求人情報を検索することも可能です。検索条件の中の「求人区分」で「障害のある方のための求人」を選択して、「フリーワード」で「就労継続支援」と入力して検索すれば、就労継続支援事業所に該当する求人を見つけやすくなります。
「自治体名+就労継続支援事業所」でネット検索して民間の求人サイトを確認してもよいでしょう。また、自治体によっては、その自治体内にある就労継続支援事業所を一覧で自治体サイトで掲載しているケースもあります。
2.事業所の見学・体験利用
気になる就労継続支援事業所が見つかったら、事業所に電話などで問い合わせましょう。就労の枠に空きがあるかや見学・体験を受け付けているか確認してください。
就労継続支援事業所で働くにあたり、見学や体験利用は必須ではありません。
しかし、職場の雰囲気や仕事内容は事業所に行って直接確認するほうがよいでしょう。職員から説明を受ければ詳細な情報が手に入り、自分に合っているか判断する際の参考にできます。
働きたい事業所が決まって求人募集に申し込むと、A型事業所の場合は面接が行われます。B型とは違い、A型では雇用契約の締結が必要です。選考フローのひとつとして面接が行われるので、実際に働くためには面接に通る必要があります。
3.障害福祉サービス受給者証の申請
利用する事業所が決まったら、就労継続支援を利用するために必要な障害福祉サービス受給者証の発行を自治体の窓口で申請します。
A型事業所であれば採用決定後に発行申請を行い、B型事業所であれば利用の意思を事業所に伝えた後に発行申請を行いましょう。
自治体の窓口で申請する際には、申請書や障害者手帳を提出し、障害者手帳を持っていない方は一般的に医師の診断書や意見書などを提出します。提出書類はケースによって異なるので、自治体窓口で確認するようにしてください。
4.サービス等利用計画書の作成と支給決定
サービス等利用計画書とは、利用する障害福祉サービスの内容や障がいをお持ちの方の現在の状況、サービス利用に関する意向などを記載する計画書です。
市町村は、提出されたサービス等利用計画書の内容を踏まえて障害福祉サービスの支給決定を行います。
一般的にサービス等利用計画書は、自治体の指定を受けた相談支援事業者が作成します。ただし、相談支援事業者ではなく本人や家族などが計画を作成することも可能です。
自治体が障害福祉サービスの支給決定をすると障害福祉サービス受給者証が交付されます。
申請してから発行までにかかる期間は自治体によって異なり、数週間で発行されることもあれば1ヶ月以上かかることもあります。発行に時間がかかることもあるので早めに申請しましょう。
納得感のある評価を効率的に行うための仕組みを整備し、従業員の育成や定着率の向上に効果的な機能を多数搭載
・360°フィードバック
・1on1レポート/支援
・目標・評価管理
・従業員データベース など
就労継続支援を利用するメリット
就労継続支援にはさまざまなメリットがあります。以下では、障がいや難病がある人が就労継続支援を利用する主なメリットを紹介します。
就労スキルの向上と社会参加の促進
就労継続支援事業所では、お菓子の製造やカフェでの接客、農作業、梱包、データ入力など、さまざまな業務に従事できます。就労継続支援事業所で働けば、就労スキルを習得・向上できる点がメリットです。
障がいがある人の中には、働きたいと思っていても一般企業での就労を諦めるケースも少なくありません。
しかし、就労継続支援事業所であれば、障がいがある人へのサポート体制が整っています。体調や障がいの特性に合わせて自分のペースで働けるので、障がいがある人でも仕事に就くことを諦めずに済み、就労を通じて社会に関わることができます。
収入の確保と経済的自立への支援
就労継続支援事業所で働けば、A型では給料が、B型では工賃が、労働の対価としてそれぞれ支払われます。
障がいがある人が収入を確保できれば、経済的に自立できる可能性が上がる点は就労継続支援のメリットのひとつです。
障がいや難病がある人の中には、一般企業での就労が難しくて働けないと、収入を得られず生活に余裕がない場合や困る場合があります。しかし、就労継続支援を活用して給料や工賃を得れば、生活費などに充てることができます。
報酬の平均月額(2023年度)はA型事業所で86,752円、B型事業所で23,053円です。
B型は収入が低い点が課題ですが、A型より簡単な作業内容が多く、自分のペースで働きやすいというメリットもあります。
一般就労への移行に向けたステップアップ
就労継続支援事業所で働いてスキルが身に付けば、一般企業で就労できる可能性が高まります。一般就労を目指すためのステップアップとして活用できる点も、就労継続支援のメリットのひとつです。
障がいがある人の場合、働く中でどのような問題や困りごとが起きるのかは、実際に働いて初めて気づくケースも多くあります。
障がいの特性や体調などによって、どれくらい働けるかや、周囲からどのようなサポートが必要になるのかは人によってさまざまです。
就労継続支援での経験から、自分に合った働き方が見つかれば、一般企業への就労を検討する際に役立ちます。
就労移行支援・就労定着支援・就労選択支援との違いと連携
就労継続支援と似た言葉に就労移行支援・就労定着支援・就労選択支援があります。
障害福祉サービスを利用する際は、これらの用語や制度を混同しないように違いを理解しておく必要があります。以下では各制度の概要や違いを解説します。
就労移行支援から一般就労へのキャリアパス
就労移行支援は、就労継続支援と同じく、障がいがある人が働きたい場合に利用できる障害福祉サービスのひとつです。
一般企業等への就労を希望する人を対象として、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援では一般企業等での就労が困難な人が対象ですが、就労移行支援では、一般企業等に雇用されることが可能と見込まれる人が対象です。
また、就労継続支援ではA型・B型いずれも利用期間の制限はありませんが、就労移行支援では利用期間は原則2年です。ただし、市町村審査会の個別審査を経て必要性が認められれば、最大1年間延長できます。
就労定着支援によるサポート
就労定着支援とは、就労移行支援や就労継続支援などを利用した後、一般企業等で働くことになった人をサポートする制度です。雇用に伴い生じる日常生活・社会生活を営むうえでの各般の問題に関する相談、指導、助言等の必要な支援が行われます。
就労定着支援を利用できるのは、就労移行支援などの利用後に通常の事業所に雇用された障がい者で、就労の継続期間が6月を経過した人です。最長で3年間サポートを受けられます。
障がい者が一般企業に就職できても、悩みやトラブルを抱えて離職するケースも少なくありません。障がいのある人の就労では、実際に働き始めてからのサポートも重要になるので、就労定着支援によって企業・障害福祉サービス事業者・医療機関での連絡・調整が行われます。
就労選択支援の創設によるサポート体制の充実
就労選択支援とは、障がい者本人が希望や能力、適性に合った就労先・働き方を選べるよう支援するサービスです。
従来の障害福祉サービスでは、障がい者の就労能力や一般就労の可能性について、障がい者本人や支援者が十分に把握できておらず、適切なサービスにつなげられていない可能性が指摘されていました。
そこで、障害者総合支援法が改正され、2025年10月から就労選択支援という新たな制度がスタートします。
出典:厚生労働省「就労選択支援について」
2025年10月以降は、就労継続支援B型の利用申請前に原則として就労選択支援を利用することになります。
また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者と、就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、2027年4月以降、原則として就労選択支援を利用することになる予定です。
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
就労継続支援の課題と今後の展望
就労継続支援にはメリットがある一方で、課題や改善すべき点も指摘されています。以下では、就労継続支援の制度の現状と今後の展望を紹介します。
賃金・工賃の向上に向けた取り組み
就労継続支援事業所から支払われる賃金・工賃の額は近年上昇傾向にあります。A型・B型の平均賃金・平均工賃(月額)は、2023年度でそれぞれ86,752円と23,053円です。
しかし、障がいや難病がある人が生活するうえで十分な金額とはいえません。就労継続支援の役割は「働く機会を提供し、収入を得られるように支援すること」であり、賃金・工賃のさらなる向上が必要です。
就労継続支援事業所の中には、作業工程や販売価格を見直したり、障がい者がより働きやすい職場環境を整えて生産効率を上げたりして、賃金・工賃を向上させた事例があります。
今後も経営改善などを通じて賃金・工賃が上がり、就労継続支援事業所で働く人の収入向上につながることが求められます。
一般就労への移行率の改善
障がい者がより安定した収入を確保して経済的自立・社会参加を実現するうえでは、就労系障害福祉サービス利用後に一般就労へ移行できるかがポイントのひとつです。
就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は近年増加傾向にあり、2022年は約2.4万でした。就労移行支援を利用した後に一般就労へ移行した人の割合は57.2%で、半数以上が一般就労に移行しています。
しかし、就労継続支援A型・B型では一般就労への移行率が低い状態が続き、2022年の割合はそれぞれ26.2%と10.7%でした。一般就労への移行率向上のために取り組めることはまだ多くあり、さらなる改善が求められます。
地域社会との連携
障がいや難病がある人が就労継続支援事業所で働くことで、地域産業の担い手として活躍でき、人手不足解消や地域活性化につながります。
就労継続支援は事業所で働く人の生活支援という観点に留まらず、地域社会の活性化の観点からも重要な制度です。就労継続支援事業所の数が今後増えて、障がいのある人と地域社会の連携が一層促進されることが求められます。
しかし、A型・B型いずれの事務所数も近年増加傾向にあったものの、A型の事務所数は、2024年3月時点の4,634事業所から同年12月の4,384事業所に減少しました。
背景には、A型事業所の大量閉鎖があります。国が2024年4月に収支の悪い事業所の報酬を引き下げたことが、主な要因です。
今後は、事業所の経営改善、報酬額向上に向けた取り組みを国が継続して、障がい者の生活支援・地域社会への貢献を果たせる、経営状態のよい事業所の数を増やせるかが課題です。
まとめ
就労継続支援を活用すれば障がいや難病がある人でも働くことができ、就労に必要な知識や能力を身に付けることができます。
障がいの特性や体調などご自身の状況に合わせて働くことができ、収入を確保できて一般就労へのステップアップとして活用できる点がメリットです。
就労継続支援を利用する際は、障害福祉サービス受給者証の発行を申請して、サービス等利用計画書を作成する必要があります。
就労継続支援以外にも、障害福祉サービスには就労移行支援などのサービスがあるので、ご自身の状況に応じて利用する制度を検討しましょう。
A型とB型のどちらにすべきか、就労継続支援事業所はどのように探すのか、分からず悩んだ場合は一人で抱え込まず、自治体の障がい福祉課などで相談するようにしてください。
HRMOSタレントマネジメントで適切な人材管理を推進
企業が事業活動を行うには、社員の能力や成果を正しく把握・評価することが重要です。スキルに応じて適切な部署に配置し、人材配置を最適化することで、働く意欲の向上や生産性アップにつながります。
障がいがある人や持病がある人など、多様な人材の現状を把握し、個々の目標設定による動機づけ、人材育成を行うのであれば、タレントマネジメントシステムの活用が効果的です。
HRMOSタレントマネジメントでは社員のスキルを可視化し、客観的に正しく数値化することができます。それにより、適切な人材配置や社員の現状に合わせた人材育成が可能です。
従業員のモチベーションが高い状態を維持するためにも、従業員一人一人に適した業務や部署に配置することが重要となります。
HRMOSのスキル管理機能について、詳しくはこちらをご覧ください。