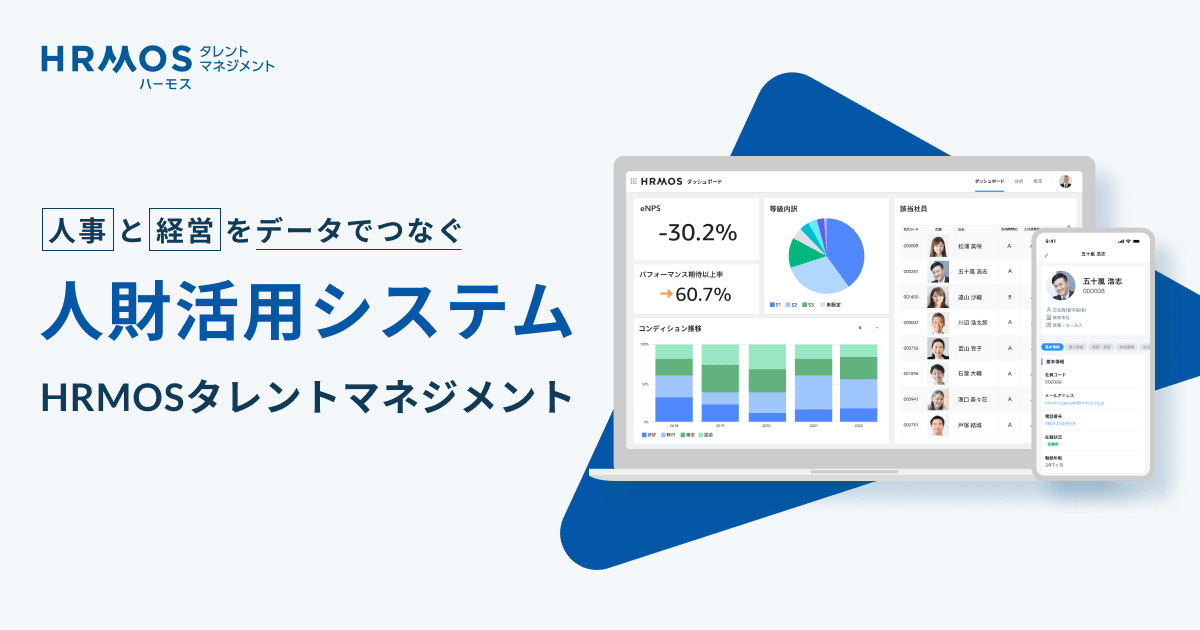目次
ビジネスで顧客や取引先と交渉する際や日常生活で家族や知人と話す際、話を有利に進めるためには交渉術が欠かせません。
その中でも、相手に要求を承諾させる際に役立つテクニックの一つが「フット・イン・ザ・
ドア」です。
本記事では、フット・イン・ザ・ドアの意味や具体例、ドア・イン・ザ・フェイスとの違いを解説します。
フット・イン・ザ・ドアを成功させるためのポイントやフット・イン・ザ・ドア以外の交渉術も紹介するので、顧客対応や売上向上について考える際の参考にしてください。
フット・イン・ザ・ドアとは
フット・イン・ザ・ドアとは、相手にまず小さな要求を承諾させて、その後に段階的に要求を大きくして本命の依頼を通す心理的なテクニックです。
交渉や依頼をするときに活用でき、営業などビジネスの場面でも使用されています。
フット・イン・ザ・ドアは、訪問販売の際、営業担当者がドアの内側に足を入れる動作「put foot in the door」に由来します。要求を徐々に大きくしていくため、日本語では「段階的要請法」とも呼ばれます。
フット・イン・ザ・ドアの有効性は論文でも発表されています。
1966年にスタンフォード大学のJonathan Freedman(ジョナサン・フリードマン)とScott Fraser(スコット・フレイザー)が発表した論文では、初めから本命の大きな要求をするよりも、最初は小さな要求から始めてその後に本命の要求につなげるほうが承諾率が高いことが証明されました。
フット・イン・ザ・ドアはなぜ効果があるのか
フット・イン・ザ・ドアはなぜ効果があるのか、その理由は心理学の理論で説明できます。以下では、フット・イン・ザ・ドアに関係する2つの心理学の理論を紹介します。
自己知覚理論
自己知覚理論とは、アメリカの心理学者ダリル・ベムが1967年に提唱した理論で、人は自身の行動を観察して、自分の態度や感情を行動から推測するという考え方です。
最初に提示された小さな要求に同意した場合、その人は「自分は相手に協力的で、相手からの依頼に応じる人間である」と自身の中でそうした人物像を認識するようになります。
その結果、協力的な自分という認識に基づき、より大きな要求に応えやすくなるのです。
従来の考え方では、態度や感情が行動を決めると考えられていましたが、自己知覚理論ではその逆で、行動によって態度や感情が形成される、という考え方です。
コミットメントと一貫性の原理
コミットメントと一貫性の原理とは、一度コミット(約束)した立場やスタンスを守ろうとし、無意識のうちに態度や行動に一貫性を持たせようとする人間の心理的傾向を指します。
フット・イン・ザ・ドアも、このコミットメントと一貫性の原理を利用したテクニックです。
人間は相手からの要求を一度受け入れてしまうと、自身の行動に一貫性を持たせるため、その後に提示された要求も同様に承諾すべきだと感じやすくなる傾向があります。
そのため、最初に小さな要求を提示して承諾させることで、その後により大きな要求を提示しても相手から承諾を得やすくなります。
フット・イン・ザ・ドアとドア・イン・ザ・フェイスの違い
ドア・イン・ザ・フェイスとは、最初に大きな要求をして、相手に断らせた上で本命の小さな要求を出すことで、相手の承諾を得やすくするテクニックです。
慣用句の「shut the door in the face(門前払い)」に由来し、日本語では「譲歩的依頼法」と呼ばれます。
フット・イン・ザ・ドアとドア・イン・ザ・フェイスはいずれも、相手から承諾を得るための心理的テクニックですが、アプローチの順序に違いがあります。
フット・イン・ザ・ドアは、小さな要求から始めて段階的に大きくしていく手法であるのに対し、ドア・イン・ザ・フェイスは最初に大きな要求を提示し、その後小さな要求へと切り替える点が特徴です。
【関連記事】
ドア・イン・ザ・フェイスとは?由来や例、効果的な使い方を解説
納得感のある評価を効率的に行うための仕組みを整備し、従業員の育成や定着率の向上に効果的な機能を多数搭載
・360°フィードバック
・1on1レポート/支援
・目標・評価管理
・従業員データベース など
フット・イン・ザ・ドアの具体的な活用例
フット・イン・ザ・ドアは、ビジネスや恋愛などさまざまな場面で活用できます。以下では具体的な活用例を紹介します。
無料トライアルから有料契約へ導く戦略
無料トライアルや試用期間を設けて、商品を試しに使ってもらってから有料契約につなげる方法は営業販売でよく見られる手法です。これはフット・イン・ザ・ドアを活用した手法の一つです。
無料トライアルや無料サンプルであれば料金がかからないため、顧客にとって試しやすい手段です。そして、商品を使うことに対して一度同意を与えているため、その後の有料契約も受け入れられやすくなります。
また、顧客の立場から見ると、商品を一度使ってみてから本契約を結ぶか決められるので、安心して契約を結ぶことができて本契約を結ぶ際の心理的なハードルが下がり、契約締結に同意を与えやすくなります。
資料請求からの段階的アプローチ
無料の資料請求やメールマガジン(メルマガ)登録などで自社と顧客との関係の入口を築き、最終的に商品販売につなげる方法もフット・イン・ザ・ドアを活用した手法です。
資料請求やメルマガ登録などを行う顧客は、その企業とつながることに一度承諾を与えているので、その後に段階的に要求を大きくしても承諾を得やすくなります。資料請求後にいきなり商品購入の話を持ちかけると相手が拒否感を抱くようであれば、セミナーや体験会への参加などを間に挟み、段階を踏んで商品購入につなげるとよいでしょう。
資料請求からの段階的アプローチでは、まずは顧客に資料請求を促す必要があります。フット・イン・ザ・ドアの考え方によれば請求フォームの項目は、少ないほうが理想です。
しかし、項目数が多い場合でも、見込み客の質が高まることで成約率が向上する可能性もあるため、バランスの取れた設計が重要となります。
テレマーケティングの交渉促進
テレフォンアポイントメント(テレアポ)で顧客にコンタクトを取って商品販売につなげる際、最初は小さな要求から始めて「2〜3分だけお時間をいただけませんか」「資料をお送りしてもよろしいでしょうか」などの負担の少ない提案を行い、段階的に要求を大きくしていく手法もフット・イン・ザ・ドアを活用した手法です。
初めて電話がかかってきた顧客からすれば、いきなり「商品を買ってほしい」と言われても拒絶しがちですが、数分だけの話や資料を送ってもらうだけであればハードルが低くなり承諾を得やすくなります。
そして、一度その企業からの要求に承諾を与えたことで、その後の大きな要求にも応えやすくなります。
もちろん、このような商品販売における交渉術・顧客への提案テクニックは、アウトバウンド(テレアポ)時だけでなくインバウンド(お問い合わせ)時にも活用でき、お問い合わせの回答から無料の試供へと段階を踏んで販売するなどの形で応用できます。
恋愛の駆け引き
いきなり「2人で今度の週末に出かけよう」とデートに誘うと断られる可能性が高い場合でも、最初は小さな提案から始めて段階を踏んでデートに誘うことで、受け入れてもらえる確率が高まります。
フット・イン・ザ・ドアは、恋愛などの日常生活にも応用できる心理的アプローチです。
たとえば、2人で話す機会を作りたい場合に「カフェでお茶しよう」と提案すれば、週末出かけることよりも、相手が受け入れやすくなります。カフェで話す中で共通の話題が見つかり、その話題についてさらに話すために週末に会いたいなどと誘えば、より自然な流れでデートに誘うことができて相手は拒否感を抱きにくくなるでしょう。
フット・イン・ザ・ドアを成功させるためのポイント
ビジネスなどでフット・イン・ザ・ドアを効果的に活用する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。以下では、フット・イン・ザ・ドアを成功させるための4つのポイントを紹介します。
要求の差に注意する
最初の要求の内容と次の要求の内容の差が大きいと、相手は拒否感を抱きやすくなって断られる可能性が高くなります。
要求の差が大きすぎると、相手は別の依頼と捉えてしまい、「一貫性の原理」が働きにくくなります。
フット・イン・ザ・ドアでは、要求の差に注意して、要求の内容を段階的に大きくしていくことが重要です。最初の要求を小さくしすぎないことや、次の過度な要求を避けること、相手に無理なく受け入れてもらえる提案を心がけましょう。
たとえば、営業訪問で「5分だけでよいから話を聞いてほしい」と相手に承諾させた後、「商品を詳しく紹介したいからさらに1時間だけ時間をほしい」と要求した場合、時間の差が大きすぎて相手に断られやすくなります。
要求の一貫性を保つ
フット・イン・ザ・ドアは、同じような要求をされたときに、要求された側が自身の行動に一貫性を保ちたいと考える「一貫性の原理」に基づくテクニックです。
最初の要求と次の要求の内容に関連性がなければ、一貫性の原理は働きにくくなり、最初の要求で承諾を得られても次の要求では断られる可能性が出てきます。
そのため、ビジネスの場面などでフット・イン・ザ・ドアを生かす際は、無関係な要求は避けて要求の一貫性を保つことがポイントです。関連性を持たせれば効果を得やすくなります。
たとえば、「商品の無料サンプルを持ってきたので使ってほしい」と相手に提案した後、全く関係のない別の商品の提案をしても、相手は違和感を覚えてしまいます。そのため、次の要求をする場合は最初の要求と関係した内容にしましょう。
タイミングと頻度
フット・イン・ザ・ドアを活用した交渉では、相手の反応や興味、意欲に合わせながら段階的に要求を大きくすることがポイントです。
相手の態度に合わせて適切な段階を踏むことで承諾を得やすくなる一方で、相手の関心がまだ薄い段階で次の大きな要求をすると、断られるリスクが高くなります。
また、要求の頻度が高すぎたり、間隔が短すぎたりすると、「しつこい」と受け取られてしまい、逆効果になることもあります。フット・イン・ザ・ドアでは、相手に要求するタイミングと頻度が重要です。
信頼関係を築く
要求の差が大きくなったり一貫性がなかったりすると、相手から信頼してもらえず拒絶される可能性が高くなります。
フット・イン・ザ・ドアを活用した交渉では、相手から信頼してもらえるかどうかがポイントの一つです。
たとえば、フット・イン・ザ・ドアを使った交渉術を同じ相手に何度も使うと、特定のテクニックを使って交渉を優位に進め、契約を取ろうとしている意図が相手に伝わってしまい、信用されなくなる可能性があります。
フット・イン・ザ・ドアは、初対面の相手や関係構築の初期段階で活用するのが効果的です。
また、相手の反応や態度を見ながら相手にあわせて交渉や提案を行うことで、無理なく信頼関係を深めることができ、承諾を得やすくなります。
・履歴書やExcel管理で情報がバラバラ(人事情報が属人化)
↓
人事情報・スキル・経歴を 自動更新・一元管理ができて、必要な人材に 数秒で辿り着ける 検索・抽出機能
⇒【人材DB機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
その他の交渉術
ビジネスなど交渉が必要な場面で役立つテクニックには、フット・イン・ザ・ドアとドア・イン・ザ・フェイス以外にもさまざまな手法があります。以下では主な交渉術を紹介します。
ローボールテクニック
ローボールテクニックとは、最初に好条件を提示して、相手から承諾を得た後に、後から不利な条件を追加することで、相手が断りづらくなるよう仕向ける交渉術です。
これは、すでに承諾した事実が一貫性の原理を働かせるため、相手が拒否しにくくなる心理を利用しています。
たとえば、商品のメリットだけを説明して購入させた後、「実はこの商品を使うためには附属品の購入も必要でその費用もかかります」と説明するようなケースがローボールテクニックに該当します。
ローボールテクニックとフット・イン・ザ・ドアは、一度相手に承諾させ、一貫性の原理によって断りにくくする点は同じです。
しかし、フット・イン・ザ・ドアでは要求を段階的に大きくして要求内容を追加するのに対して、ローボールテクニックでは最初に要求する時点で要求の内容の一部を隠している点が異なります。
ザッツ・ノット・オール・テクニック
ザッツ・ノット・オール・テクニックとは、交渉時に提示した条件に加えて、さらに有利な特典を後から提示することで、相手にお得感を与えて承諾を得やすくする手法です。
「それだけではない」を意味する「that’s-not-all」に由来します。
たとえば、ネットショッピングで「価格は○○円です。さらに今ならなんと△△もお付けします」と商品紹介を行い、後から追加情報を紹介するケースが該当します。
最初に提示された条件が基準となるため、それに上乗せされた内容がより魅力的に感じられ、購入の後押しにつながります。
ザッツ・ノット・オール・テクニックはフット・イン・ザ・ドアと同じく心理学に基づく交渉術ですが、フット・イン・ザ・ドアは段階的に要求を大きくするのに対して、ザッツ・ノット・オール・テクニックでは最初に提示した条件に特典やおまけを付けてお得感を感じさせる点が異なります。
イエスセット
イエスセットとは、いくつかの質問をされて「イエス」と答え続けていると、その次の質問にも同じく「イエス」と答えやすくなる人間の心理を使った交渉術です。
ビジネスの場面では、簡単に同意を得られる質問をいくつか行い、最終的に本命の提案へつなげるという形で使われます。
イエスセットもフット・イン・ザ・ドアも、心理学の一貫性の原理を利用した交渉術である点は同じです。
ただし、イエスセットでは「同意を積み重ねる」のに対し、フット・イン・ザ・ドアでは「行動を積み重ねる」点に違いがあります。
まとめ
フット・イン・ザ・ドアは、ビジネスの顧客対応から恋愛や人間関係まで、幅広い場面で活用できる交渉テクニックです。
フット・イン・ザ・ドアは心理学の「自己知覚理論」や「コミットメントと一貫性の原理」に基づいており、小さな要求から始めて徐々に大きな要求へと導くアプローチが特徴です。最初に大きな要求を提示する「ドア・イン・ザ・フェイス」とは対照的な方法と言えるでしょう。
活用にあたっては、要求と要求の間に過度な差が生じないように注意し、内容に一貫性を持たせることがポイントです。
加えて、提案のタイミングや頻度、相手との信頼関係の構築も重要です。これらの点を押さえれば、相手の承諾を得やすくなります。
HRMOSタレントマネジメントの活用で従業員のスキル管理・向上を
企業が労働生産性を高めて売上を向上させるには、従業員一人一人のスキルやノウハウ、実績を把握し、個々の状況に応じて必要な研修を実施するなど、従業員へのきめ細やかな対応を行うことが重要です。たとえば、営業実績が芳しくない従業員がいる場合、フット・イン・ザ・ドアやドア・イン・ザ・フェイスをはじめとした交渉術に関する研修を行うことで、営業実績を改善できる場合があります。
こうしたスキル管理には、タレントマネジメントシステムの活用がおすすめです。
「HRMOSタレントマネジメント」では、社員のスキルを可視化し、数値で客観的に把握できます。これにより、適切な人材配置や育成計画を立てやすくなり、社員の状態をリアルタイムで確認しながら迅速なフォローも可能です。
タレントマネジメントシステムを選ぶ際は、搭載されている機能の豊富さだけでなく、カスタマイズの柔軟性や操作性にも注目すべきです。HRMOSでは、2週間の無料トライアルを実施しており、実際の操作感を確認できます。
HRMOSのタレントマネジメントシステムについて、詳しくはこちらをご覧ください。