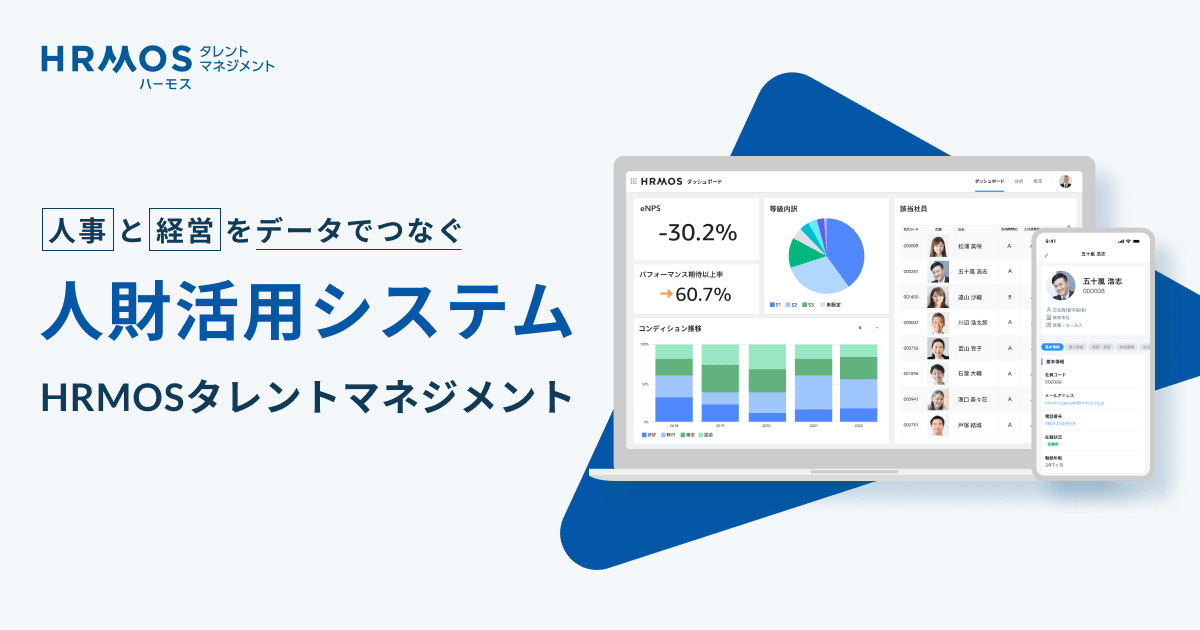近年、多くの企業が1on1ミーティング(以下1on1)を導入している一方で、目的が共有されないまま形式的に行われ、「話しただけ」で終わってしまうケースが課題となっています。
今回は、和光大学の坂井敬子先生のキャリア発達論など産業・組織心理学の知見を生かし、1on1を若手の離職防止・キャリア支援の場とするためのコツを解説します。現場でありがちな悩みにも触れながら、より効果的な運用方法を紹介します。

プロフィール
坂井 敬子
和光大学准教授 博士(心理学)
辞めたくなる前に気づく。若手の心理とサイン
── 若手社員が早期に辞めてしまう背景には、どのような心理的要因があると考えられますか?
若手が就職後すぐに離職してしまう背景には、入社前の吟味不足や、リアリティショックによる心理的負担が大きく関係しています。
入社前の吟味が不足すると「早く内定がほしい」と焦るなかで企業を選び、入社後に「こんなはずじゃなかった」とギャップに直面してしまいます。また、業務量や人間関係、将来への不安が重なると「続ける自信が持てない」と感じてしまうのです。
── 若手社員が早期に辞めないためには?
離職を防ぐには、入社前の情報提供だけでなく、入社後の継続的なケアが欠かせません。
入社前には仕事内容の魅力ややりがいだけでなく、実際の働き方や大変な点、人間関係なども含めたリアルな情報をバランスよく伝えることが大切です。
ポジティブな面だけでなく、適度にネガティブな側面も伝えることで、入社後のギャップやリアリティショックを和らげ、ミスマッチによる早期離職を防ぐことにつながります。
一方、入社後のフォローとして特に求められるのが、若手社員の孤立を防ぐための丁寧なコミュニケーションです。リモート勤務が浸透した今、「上司が忙しそうで話しかけにくい」といった声も多く聞かれます。若手社員の孤立を防ぐためには、日々の小さな変化への気づきが大切です。
表情や話し方、テンションなどのサインを察知し、「最近どう?」とさりげなく声をかけるだけでも、不安を早めにキャッチできることがあります。観察と対話の積み重ねが、若手の安心感を生み、定着につながるでしょう。
納得感のある評価を効率的に行うための仕組みを整備し、従業員の育成や定着率の向上に効果的な機能を多数搭載
・360°フィードバック
・1on1レポート/支援
・目標・評価管理
・従業員データベース など
「ただの雑談」で終わらせない1on1の設計とは?
── 多くの職場で1on1が実施されていますが、「ただの雑談」に終わるケースもあります。その背景は何でしょうか?
最大の要因は、上司・部下ともに1on1の目的を理解・共有できていないまま形式的に実施していることです。「とりあえずやればいい」という認識では、有意義な対話にはつながりません。
また、1on1を「業務報告の時間」と捉えてしまう上司もいますが、それでは通常の面談と変わりません。本来の目的は、部下の成長支援と心理的ケアにあります。上司は聞き役に徹し、部下が自由に話せるようにファシリテートする姿勢が求められます。
── 若手との1on1を行う際、特に重視すべきポイントは何でしょうか?
若手に対する1on1では、育成や教育よりもまず話しかけやすい関係性をつくることが重要です。ケアとは相手の現状に寄り添い、「何に困っているのか」に気づく関わり方を指します。
特に就職直後の若手は、入社後のギャップや孤立感から不安を抱えがちです。こうした不安は、本人の努力だけでは乗り越えるのが難しいでしょう。だからこそ、「安心して話せる場」を1on1で提供することが、離職防止の第一歩となります。
<関連>
1on1ミーティングで話すことは?話題とすべき7つのテーマと20の質問事例
── 若手支援のために、1on1はどれくらいの頻度で実施するのが適切でしょうか?
1on1の頻度には正解はなく、目的と現場の状況に応じて柔軟に設計することが大切です。
普段から密にコミュニケーションが取れている職場であれば、1on1の頻度は低くても問題ありません。
一方、接点が少ない職場では、1on1が孤立を防ぐ役割を果たします。最初は短時間でも構いません。実施しながら最適な頻度と時間を見極めていく姿勢が必要です。
制度との連携で支援を仕組み化する
── 1on1をOJTやメンター制度と連携させて機能させるためには、どのような工夫が必要ですか?
1on1は誰と実施するかが重要です。
直属の上司との実施が基本ですが、別部署の先輩など「斜めの関係」を活用する場合もあります。また、1on1を繰り返すことで信頼関係は深まりますが、過度な依存状態にならないよう配慮する姿勢も必要です。
クローズドな場になりやすい1on1では、「どんな目的でどんなテーマを話すか」をチーム内で共有しましょう。
情報をまったく共有しないと、OJT担当やメンターとの連携が取りづらくなり、本人が混乱するリスクがあります。
一方で、1on1ではプライバシーに関わる話題も扱うため、開示と守秘の線引きを明確にすることも欠かせません。目的や方向性のみを共有するなど、開示の粒度を工夫することで、風通しと信頼を両立できます。
<関連>
OJTとOFF-JTとは?違いやメリット・デメリットを人材育成の観点で解説
メンタリングプログラムとは?メンタリングの意味やメリット、プログラムの導入方法について詳しく解説!
職場の心理的安全性とは?作り方や4つの因子、高める方法を解説
── メンターやOJT担当に求められるスタンスとは?
支援者が持つべき視点は、「ケアは双方向の関係」であるという理解です。
関わるなかで自分自身も気づきを得て成長する、双方向の関係性こそが、健全な支援体制につながります。
「やってあげているのに伝わらない」と感じる場合は、支援が一方的になっているかもしれません。支える側も何かを得ているという実感があることで、関係性は持続可能なものに変わります。
たとえば、「部下の話を聞いて自分も刺激をもらった」といった声は、現場でもよく耳にします。メンターやOJT担当は、教える人ではなく「ともに育つ人」と捉えることで、信頼に満ちた双方向の関係性が築かれていきます。
── 入社初期の支援で人事が意識すべきことはありますか?
業務支援だけでなく、「この会社で成長できそう」と思える未来の見通しを提示することです。将来が見えない不安は、離職の引き金になりやすい傾向です。
また、若手は「監視されている」と感じやすく、過度なマネジメントは逆効果です。自由度のある関係性のなかで信頼が育つことで、安心して働き続けられる土壌が生まれます。
たとえば、先輩社員との座談会や、ロールモデル紹介の機会を日常的に組み込むことで、将来への前向きな想像がしやすくなるでしょう。
ポイントは、一方的に教える場ではなく、気軽に話せる接点を設計することです。日常的な関わりが、若手にとっての「ケア」となり、心理的安全性や内発的動機づけを高めます。
オンボーディング期の支援は、「見守る・つなげる・寄り添う」を軸に、信頼を基盤とした環境設計として捉えることが必要です。
・「なんとなく」や特定の人の勘 に頼った配置 から脱却したい
↓
従業員のスキルを可視化し、組織の課題を可視化。評価・育成記録まで 一元管理 し、データに基づいた配置を実現
⇒デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
若手が「辞めない組織」を育む1on1の生かし方
── 人材配置の最適化に1on1をどう生かすべきでしょうか?
若手が自らの興味や強みを言語化できるよう、上司が対話のコントローラー(主導権を握る立場)にならず、ファシリテーターに徹することが大切です。
他部署への興味が出たときに肯定的に受け止めることで、本人の本音やキャリア志向が引き出され、結果として、配置最適化や成長支援につながります。
また、話題を部下に委ねることで、業務外の悩みや将来の目標など、配置を考えるうえで貴重なヒントが自然と浮かび上がってきます。
若手の1on1を「配置を見極める情報収集の場」として機能させるには、キャリアの話題も歓迎する姿勢を明確に示すこと。信頼を前提とした対話こそが、本人の意欲や適性を見極める最良の手がかりになります。
<関連>
── 1on1を通じて若手が辞めない組織をつくるために、組織文化として必要なことは?
信頼を土台とした心理的安全性のある文化を組織全体で育むことが必要です。若手社員が安心感を得られることで、困難にも前向きに立ち向かえます。一方で、過干渉や成果至上主義は逆効果です。
「失敗しても大丈夫」「今は学びの時期」と若手社員に伝えるだけで、挑戦への安心感が生まれます。
「辞めない組織」を支えるのは、安心して話せる関係性や、失敗を許容する風土、支え合いの文化です。これらを、1on1やOJT、オンボーディングを通じて根づかせていくことが、長期的な定着と活躍につながります。