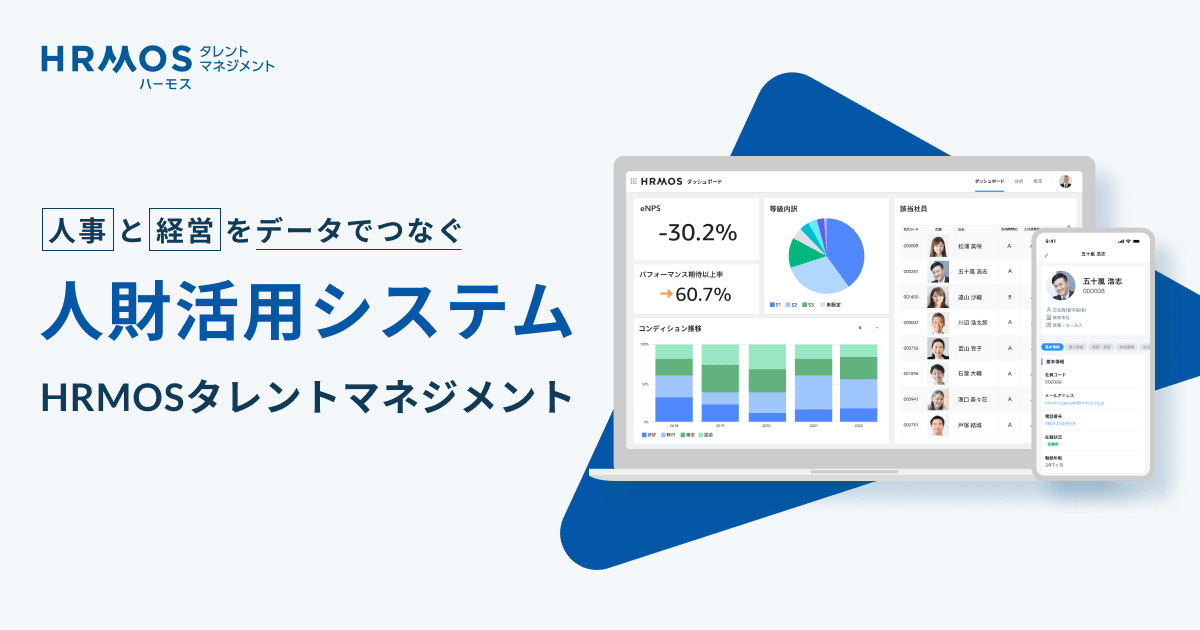目次
エンハンシング効果を活用すると、モチベーションが高まり、積極性や主体性が生まれ、意欲的に物事へ取り組めるようになります。
この効果は具体的に、企業が従業員の就労意欲を高める場合や、親が子どもを教育するときに勉強への意欲を高めたい場合などに活用されています。
本記事では、エンハンシング効果とは何か、意味や具体例、ビジネスでの活用メリットやアンダーマイニング効果との違いを解説します。
エンハンシング効果とは?
エンハンシング効果とは、報酬など外的な動機づけで行動しているうちに、魅力ややりがいに気付いて自ら積極的に取り組むようになり、内的な欲求・意欲が高まる効果のことです。
たとえば、昇給・昇格などの外的な動機づけで仕事をしていたものの、仕事自体に楽しさを感じ始め、意欲的に仕事に取り組むケースです。
「成長したい」「達成感を得たい」といった、自分の関心に基づく内的な動機に基づく行動は、外的な動機づけより効果が長続きする傾向にあります。
部下や従業員の労働意欲を高める場合には、いかにして内的な動機づけをするかが重要です。報酬など外的な要因で動機づけをしつつ、エンハンシング効果によって内的な動機づけをできれば、従業員は自ら意欲的に仕事に取り組むようになります。
内発的動機づけと外発的動機づけ
心理学の世界では、内的な動機づけと外的な動機づけをそれぞれ「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」と呼びます。
「内発的動機づけ」とは、個人の内面に湧き起こった心理的欲求を要因としてある行動の意欲が高まることです。
一方、「外発的動機づけ」とは、報酬や賞賛、罰則など、外部からの要因によって、行動の意欲を高めることを指します。
外発的動機づけは、報酬や罰則など提示しやすいものが動機になるので、比較的すぐに動機づけをできる点が特徴です。ただし、自ら望んだものではなく外部から与えられた動機にすぎず、効果が短い傾向にあります。
一方で内発的動機づけは、効果が表れるまで時間がかかるものの、自らの内なる欲求に基づく行動であるため、効果が長続きする傾向にあります。
関連記事
内発的動機づけとは?具体例や心理学的背景、高める方法をわかりやすく解説
外発的動機づけとは?活用方法や具体例、メリット・デメリットを解説
・「なんとなく」や特定の人の勘 に頼った配置 から脱却したい
↓
従業員のスキルを可視化し、組織の課題を可視化。評価・育成記録まで 一元管理 し、データに基づいた配置を実現
⇒デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
エンハンシング効果に関する心理学的実験
エンハンシング効果は、心理学の実験によって実証されています。
エンハンシング効果を意識した場合としない場合でどのような違いが生じるのか。有名な2つの実験をご紹介します。
エリザベス・B・ハーロックの賞罰実験
1925年、アメリカの発達心理学者エリザベス・B・ハーロックは、子どもたちを3つのグループに分けて対応を変えながら算数の試験を実施しました。
- 試験のたびに褒められるグループ
- 試験のたびに叱られるグループ
- 何も言われないグループ
褒められるグループの子どもは、やる気が向上して71%の生徒の成績が上がりました。
一方で叱られるグループの子どもは、2日目に20%の生徒の成績が上がり、叱られないように最初は頑張るものの、徐々にやる気が低下しました。
何も言われないグループの子どもは、2日目は5%の生徒の成績が上がりましたが、その後は変化がありませんでした。
「褒められるために」「叱られないために」といった理由で頑張ることは、どちらも外発的動機づけによる行動です。
しかし、この賞罰実験の結果からは、叱ったり罰則を与えたりするよりも、褒めたり報酬を与えたりするほうがやる気が上がり、エンハンシング効果が生まれることがわかります。
コロンビア大学の知能テスト実験
褒めることでエンハンシング効果が期待できますが、その効果は「褒め方」によって大きく異なることが、実験によって示されています。
1990年代、コロンビア大学は約400人の子どもを対象に知能テストを行いました。
テスト終了後、実際の点数は言わず、すべての子どもに個別に「100点満点中80点だった」と告げるようにし、以下の3つのグループに分けて伝え方を変えました。
- 本当に頭がいいんだね
- 努力の甲斐があったね
- 何もコメントしない
そして、コメントを伝えた後、以下の2つの課題のうちいずれか1つを選んでもらいました。
課題1:難度が高いが、やりがいのある課題
課題2:簡単に解け、学びの少ない課題
難しい課題1を選んだ割合は、努力を褒められたグループでは約90%で、非常に高い割合でした。一方で、能力を褒められたグループでは約45%、何もコメントされなかったグループでは約55%でした。
この実験結果からは、努力や過程を褒めると、さらに努力して頑張ろうという気持ちになり、エンハンシング効果によってやる気が上がることがわかります。
一方で、「頭がいい」というように結果や知能を褒めると、より難しい課題にチャレンジしようというやる気は生まれにくいことがわかります。
これは、「賢く見られたい」という気持ちから失敗を恐れるようになったり、「自分は能力があるから努力しなくても良い」と思い込んでしまうことが原因と考えられます。
エンハンシング効果をビジネスに生かすメリット
外発的動機づけから内発的動機づけにつなげるエンハンシング効果は、ビジネスにも応用可能です。
以下では、従業員や部下のモチベーション向上など、エンハンシング効果をビジネスでどのように生かせるのか、紹介します。
個人・組織の成長促進
エンハンシング効果によって内発的動機が強まれば、従業員や部下は仕事に積極的に取り組むようになります。
「成長したい」という思いからスキルの習得に励み、「達成感を得たい」という思いから難易度の高い業務に積極的に挑戦するようになります。
内発的動機づけは、自ら意欲的に取り組む姿勢を生み出し、自主性や積極性につながる点がメリットです。
自ら考えて行動して仕事に取り組むなかで、新たな気付きやより多くの知識・経験を得ることができ、個人の成長が組織の成長につながります。
従業員が仕事に前向きに取り組み、「自分ならできるはずだ」と考えるようになれば、自己効力感が向上して自信を持って業務に臨めるでしょう。
関連記事:自己効力感とは?意味や高める方法、自己肯定感との違いを簡単に解説
従業員エンゲージメントの向上
従業員エンゲージメントとは、従業員が会社に対して抱く愛着心や帰属意識、貢献意欲のことです。
従業員エンゲージメントが高いと、労働生産性向上や離職率低下などの効果を期待できます。従業員エンゲージメントを向上させることが企業にとって重要です。
エンハンシング効果によって内発的動機が強まれば、従業員は仕事にやりがいを感じ、従業員エンゲージメントの向上につながります。
従業員が「この会社で働きたい」「この仕事が面白い」と感じれば、モチベーションが高まり、企業への貢献意欲も向上します。
従業員のモチベーションが高い状態になれば、職場の活性化や雰囲気の改善につながり、働きやすい職場環境を構築できるでしょう。
関連記事:従業員エンゲージメントとは? 高める方法や事例から学ぶ成功のポイントを解説
ビジネス成果の改善
エンハンシング効果によって内発的動機を強め、従業員のモチベーションや従業員エンゲージメントが向上すれば、ビジネス成果の改善を期待できます。
たとえば、従業員が意欲的・自主的に仕事に取り組み、自ら考えて行動するようになると、業務効率の改善や労働生産性の向上を期待できるでしょう。
よく考えずに単に仕事をこなすだけの場合とは違い、主体的に考えて工夫しながら業務に取り組むため、業務の効率や質の向上を期待できます。
職場におけるエンハンシング効果の活用事例
エンハンシング効果は、企業が人材育成をする際や上司が部下の育成をする際に活用できます。職場でエンハンシング効果をどのように活用できるのか、以下で具体的な事例を見てみましょう。
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で行うミーティングです。
人材育成や部下のモチベーション向上を目的として、週1回や月1回など定期的に行います。
1on1ミーティングでは、日頃の業務状況の確認だけでなく、部下が悩んでいる場合には相談に乗ってアドバイスを行います。部下に成長を促す機会であり、上司と部下の信頼関係構築に役立ちます。
1on1ミーティングを行う際、部下の強みや努力を認めて評価することで、仕事への意欲を高める効果が期待できます。
コロンビア大学の知能テスト実験で示されたように、エンハンシング効果を高めるには、結果よりも努力の過程を褒めることが効果的です。
これまでの部下の取り組みを振り返り、よい点を評価して継続を促すとよいでしょう。
関連記事:1on1とは?実施の目的や効果、トーク例などを解説
メンタリングプログラム
メンタリングプログラムとは、豊富な知識や経験を持つ先輩社員(メンター)が、後輩社員(メンティ)に対して個別にサポートを行う制度です。メンター制度とも呼ばれ、後輩社員(メンティ)のキャリア形成上の課題解決や悩みの解消をサポートします。
先輩社員がメンターとして後輩の話を聞く際、エンハンシング効果をうまく使えると、部下のモチベーションアップや成長につながります。部下のよい点を見つけて褒めれば、仕事を通じて「さらに成長したい」「達成感を得たい」と思えるようになり、前向きに業務に取り組めるようになるでしょう。
部下へアドバイスを行うなかで自ら意欲的に取り組む姿勢を引き出せれば、自主性や積極性を生み出すことにつながります。
関連記事:メンタリングプログラムとは?メンタリングの意味やメリット、プログラムの導入方法について詳しく解説!
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックとは、業務中の行動などに対して、よい点を見つけてポジティブな内容で評価することです。
ポジティブな評価を受けることで、部下のやる気が高まり、より積極的に業務へ取り組むようになります。
「君が細かい点まで事前に確認してくれたおかげで、必要な対応を漏れなく行うことができて助かったよ」など、部下が前向きな気持ちになれるように伝えることがポイントです。
賞賛・評価という外発的動機を与え、エンハンシング効果で内発的動機づけにつなげられれば、部下は意欲的・主体的に業務に取り組むようになるでしょう。
関連記事:フィードバックとは? 意味や言い換え、仕事における使い方をわかりやすく解説
エンハンシング効果を引き出すポイント
エンハンシング効果を生かす際には、効果を引き出すためのポイントを理解しておくことが重要です。以下では、エンハンシング効果を引き出すためのポイントを4つ紹介します。
努力や過程を褒める
コロンビア大学の知能テスト実験で示されたように、結果や能力を褒めると消極的になり、モチベーションが下がる場合があります。
そのため、外発的動機づけのために賞賛を与える場合は、結果や能力を褒めるよりも、努力や過程を褒めるようにしましょう。
結果や能力を褒めると、褒められた側はその結果に満足して、「自分には能力があり、これ以上努力しなくてもよい」と考える可能性があります。
一方で、努力していることを評価されて褒められれば、今後も努力しようという意欲が高まり、さらなる成長に期待できます。
他人の前で褒める
他人の前で褒められると自尊心が満たされる結果、他に誰もいない状況で褒められるより、モチベーションがアップする可能性があります。
表彰式を行ったり、社内会議で優秀な社員の実績を紹介して褒めたりすれば、エンハンシング効果を引き出すうえで効果的です。
他人の前で褒められ、自分の努力や成果が多くの人に認められたと感じると、さらに頑張る気力が湧いてきます。
たとえば、社内で表彰基準を作って定期的に表彰式を行えば、エンハンシング効果によって従業員の内発的動機を高められるでしょう。
信頼関係を築く
相手を褒めたとき、エンハンシング効果によって必ずモチベーションが上がるかといえば、そうとは限りません。
エンハンシング効果を生み出すうえで重要なことの1つが、褒める側と褒められる側の間に信頼関係があるかどうかです。
たとえば、信頼していない人から褒められても、「どうせ適当なことを言っているのだろう」と真意が伝わらず、かえって逆効果になる場合もあります。
一方で、信頼している人からの賞賛であれば心に響き、「もっと成長したい」「さらに頑張りたい」という気持ちになるでしょう。
相手を褒めてエンハンシング効果によって内発的動機づけにつなげるためには、日頃から信頼関係を築いておくことが重要です。
言葉だけになっていないか注意する
実際には相手のことをよく考えておらず、とりあえず賞賛の言葉を贈ったとしても、相手の心に響かずエンハンシング効果が生まれない可能性が高いでしょう。
本当に相手のことを考えて褒めている場合とそうではない場合では、表情や態度などに違いが表れやすいものです。本心から褒めているのか、相手にも伝わってしまいます。
また、仮に相手のことを高く評価していても、伝え方を間違えれば、賞賛の気持ちが伝わらずエンハンシング効果が起きないこともあります。
相手を褒める際は伝え方に気を配り、言葉だけになっていないか注意しましょう。
・履歴書やExcel管理で情報がバラバラ(人事情報が属人化)
↓
人事情報・スキル・経歴を 自動更新・一元管理ができて、必要な人材に 数秒で辿り着ける 検索・抽出機能
⇒【人材DB機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
エンハンシング効果に関連する心理効果
エンハンシング効果を活用する際には、関連する心理効果についても理解しておくと有効です。以下では、エンハンシング効果に関連する3つの心理効果を紹介します。
アンダーマイニング効果との違い
アンダーマイニング効果とは、報酬や罰則などの外発的動機を与えたときに、興味や関心、達成感などの内発的動機が弱まる効果のことです。
内発的動機づけを弱める点で、外発的動機づけから内発的動機づけを促すエンハンシング効果とは対照的です。
報酬や賞賛などの外発的動機を与えた場合、エンハンシング効果によって内発的動機づけが強まるとは限りません。
逆に、アンダーマイニング効果によって内発的動機づけが弱まる場合があるので注意が必要です。
すでに成長や達成感といった内発的動機で行動している従業員に対して、報酬を与えると報酬をもらうことが目的化して、内的な動機づけが弱まることがあります。
関連記事:アンダーマイニング効果とは?意味や事例、対策を解説
機能的自律との違い
機能的自律とは、当初は手段だった行動が、やがて目的へと変わり、自律性を持つようになることです。
たとえば、生活していくうえで稼ぐ必要があるため仕事をしていたものの、仕事にやりがいを感じ始め、仕事自体が好きになるケースが該当します。
エンハンシング効果も機能的自律も、外的な要因で動機づけされていた状態から内的な動機づけに変化していく点は同じです。
ある行動を取るうちに興味や関心が湧き、成長や達成感を得るためにその行動をすること自体が目的化し、動機が内的なものに変わります。
ピグマリオン効果との違い
ピグマリオン効果とは、周囲から高い期待をかけられると、期待に応えようとして頑張る結果、成果が上がる効果のことです。
他者からの期待や応援により、モチベーションが高まり、成果にも良い影響を及ぼすとされる理論です。
ピグマリオン効果は「教育期待効果」とも呼ばれます。
エンハンシング効果もピグマリオン効果も、外的な要因によって動機づけがされる点は同じです。いずれも他者から評価されたり褒められたりすると生じる効果であり、企業内での人材育成や子どもへの教育の際に活用できます。
関連記事:ピグマリオン効果とは?ゴーレム効果との違いや事例、活用方法を解説
まとめ
エンハンシング効果を活用すれば、報酬や賞賛などの外発的動機づけをもとにして内発的動機づけを行うことができます。企業内で人材育成をする際に活用が可能です。
従業員が仕事を通じて「成長したい」「達成感を得たい」と思うようになると、就労意欲が高まり、積極的・主体的に業務に取り組むようになるでしょう。個人の成長が組織の成長につながり、従業員エンゲージメントの向上などの効果も期待できます。
エンハンシング効果を引き出すには、結果や能力よりも努力や過程を褒めること、普段から信頼関係を築いておくことがポイントです。他人の前で褒めることもエンハンシング効果を高めるうえで効果的です。
1on1ミーティングやメンタリングプログラムなど、エンハンシング効果はビジネスのさまざまな場面で活用できます。うまく活用して業務改善や成果創出につなげましょう。
HRMOSタレントマネジメントで適切な人材管理を推進
従業員や部下のサポートを行い、エンハンシング効果でモチベーションを高めるには、従業員や部下の能力や業務の状況などを把握しておく必要があります。
従業員のキャリアビジョンに関する相談に乗り、悩み・課題の解決のためにアドバイスをするためには、一人一人の現状を正確に把握・理解しておく必要があります。
社員の状況を的確に把握し、人材管理・人材育成を行うのであれば、タレントマネジメントシステムの活用が効果的です。
HRMOSタレントマネジメントでは、サーベイを通じて社員一人一人のモチベーションの変化をグラフと数値で可視化し、適切なフォローやサポートを提供することが可能になります。
HRMOSのスキル管理機能について、詳しくはこちらをご覧ください。