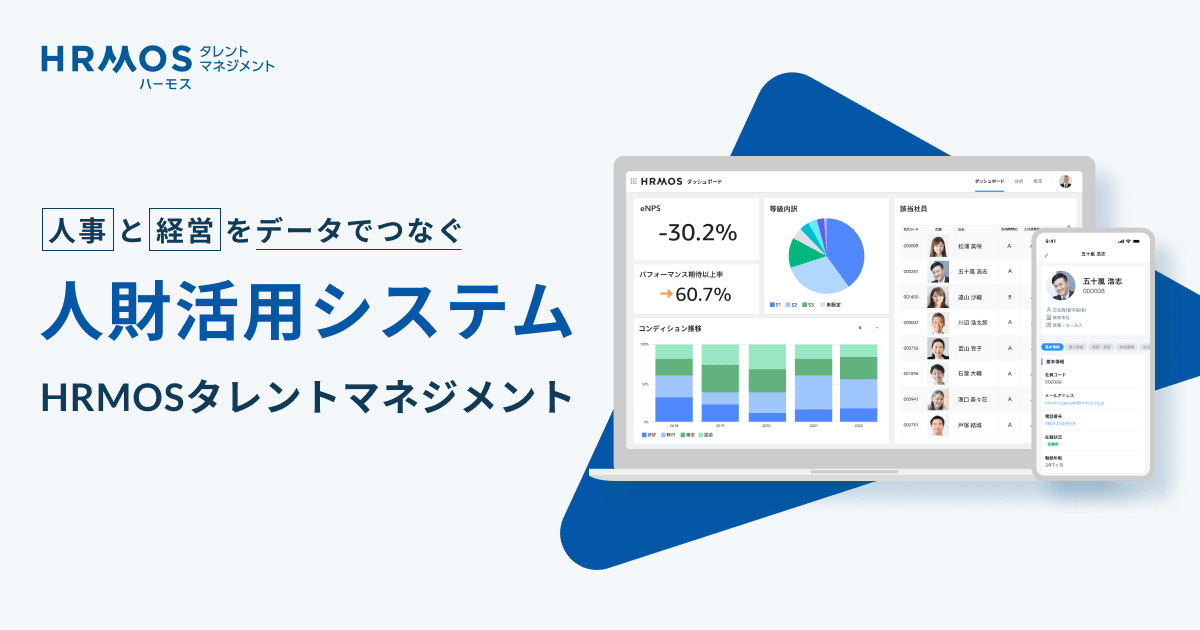目次
こんにちは。「HRMOS(ハーモス)タレントマネジメント」のHRMOS TREND編集部です。
こちらからお役立ち資料「タレントマネジメント成功への条件」を無料でダウンロードできます!
組織の生産性を上げ、人手不足の問題を緩和する策として、「ワークエンゲージメント」の向上に注目が集まっています。言葉を耳にしたことがあるものの、具体的な概念や必要な取り組みについてはよくわかっていない人も多いのではないでしょうか。本記事では、企業の人事・労務・採用担当者などに向けて、ワークエンゲージメントの意味、高めるための方法、具体的な事例について解説します。
ワークエンゲージメントとは?
ワークエンゲージメントの定義
ワークエンゲージメントとは、2002年にオランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによって確立された概念です。厚生労働省では、「働きがい」という呼び方もしています。具体的には、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」を指すもので、個人の労働生産性や健康にも影響する要因として注目されています。国内では、厚生労働省による「令和元年版労働経済の分析」においてその重要性が指摘されたことから、広く認知されるようになりました。ワークエンゲージメントには、次の2つの特徴があるとされています。
ワークエンゲージメントを形成する3つの要素
ワークエンゲージメントは、仕事に対する「活力」、「熱意」、「没頭」の3つの要素がそろった状態として定義されます。仕事に対する活力とは「仕事から活力を得て生き生きとしていること」で、仕事に対する熱意とは「仕事に誇りとやりがいを感じていること」です。そして、仕事への没頭とは「仕事に熱心に取り組んでいること」を指します。つまり、ワークエンゲージメントが高い人は、自らの仕事に誇りを持って夢中になって取り組み、仕事をしていると活力がみなぎるように感じる状態にあるといえるでしょう。
ワークエンゲージメントが高いとは?
ワークエンゲージメントの高さは、「特定の仕事などに向けられた一時的な状態」を指すものではありません。例えば、管理職に昇進した直後には喜びもあいまって一時的にやる気が高まることがあるでしょうが、これだけではワークエンゲージメントが高いとはいえません。ワークエンゲージメントが高いとは、個人の一時的な経験として変動していく面もあるものの、基本的には仕事全般に対して熱意を持ち、持続的かつ安定的に生き生きとした状態にあることを指します。
ワークエンゲージメントに関連する3つの概念
ワークエンゲージメントを正しく理解するうえでは、類似する3つの概念との違いや関係性を整理しておくことが大事です。「仕事への態度・認知」に対する概念は、「ワークエンゲージメント」のほか、「ワーカホリスムズ」「職務満足感」「バーンアウト」に分類されます。これらの概念は、「仕事への態度・認知が否定的・肯定的か」「活動水準が高い・低いか」という2つの軸によって区別できます。それぞれの特徴について順番に見ていきましょう。
1.ワーカホリズム
ワーカホリズムは、仕事への活動水準が高いものの、仕事への態度・認知は否定的な状態にあることを指します。仕事に熱心に取り組んでいる点ではワークエンゲージメントと共通しています。しかし、仕事から離れることへの不安が強く、「仕事をしていないと落ち着かない」「仕事をしないといけない」といった強迫観念がベースになっているのが特徴です。仕事以外に興味がないといったタイプの人も含まれます。過度に働きすぎる傾向があるため、放っておくと健康を損ねるリスクがあります。
ワーカホリズムはワークエンゲージメントと重複する部分も多く関連性が高いため、ワークエンゲージメントが高くても、職場環境次第ではワーカホリズムに移行する恐れがある点に注意が必要です。例えば、「毎日残業している社員が褒められる・評価される」といった職場では、ワークエンゲージメントが高い人がワーカホリズムに傾いてしまいかねません。
2.職務満足感
職務満足感とは、組織や職場環境、仕事における自分の役割についての満足度を示すものです。仕事への態度・認知は肯定的であるときに高くなる点ではワークエンゲージメントと共通していますが、活動水準は低いのが違いです。
3.バーンアウト
「燃え尽き症候群」とも呼ばれるものです。仕事に熱心かつ献身的に貢献した結果、精神的・身体的に大きな負担がかかり、仕事への情熱や意欲、自信をなくした状態を指します。2軸で整理したときには、仕事への態度・認知が否定的であり、かつ活動水準も低い状態にあります。つまり、ワークエンゲージメントは、バーンアウトの対極の概念といえます。バーンアウを防ぐためには、個人としての対策だけでなく、組織や職場全体での協力が不可欠です。
従業員エンゲージメントや顧客満足度との違い
混同されることが多い、従業員エンゲージメントと顧客満足度との違いも整理しておきましょう。
従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い
ワークエンゲージメントとよく似た言葉に、従業員エンゲージメントがあります。職場の実務分野でエンゲージメントという言葉を用いたときには、従業員エンゲージメントを指すことが多いでしょう。ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントは、概念の対象範囲が異なります。従業員エンゲージメントとは、「社員の組織に対する共感や信頼」のことです。従業員エンゲージメントが高い社員は、所属する組織の企業理念に共感し、自発的な貢献意欲と強い愛着を持って働いている状態にあります。つまり、従業員エンゲージメントとは仕事に限ったものではありませんが、ワークエンゲージメントは、あくまでも「個人の仕事内容」についての関わりについての概念です。
従業員満足度とワークエンゲージメントの違い
ワークエンゲージメントは従業員満足度とも異なります。従業員満足度とは、仕事内容や待遇、職場環境、人間関係、福利厚生といった、社員の仕事や職場に対する満足度で、社員からの企業評価によってスコア化されます。従業員満足度が高まれば、従業員エンゲージメントが高まることも多く、またワークエンゲージメントが向上するというように、相乗効果も期待できます。ただし、必ずしも従業員満足度が高い社員が、活動水準も高いとは限りません。単に待遇や福利厚生に満足しているだけで、組織への自発的な貢献意欲は低い場合もあります。
ワークエンゲージメントを高めるメリット
社員のワークエンゲージメントを高めることで企業が得られるメリットも知っておきましょう。ワークエンゲージメントの向上が企業にもたらすメリットは主に次の5つです。
メリット1:組織の生産性が向上する
ワークエンゲージメントが高い社員は、熱意を持って仕事に取り組み、生き生きとした状態にあります。自分の能力やスキルを最大限に発揮できるよう、創意工夫したり、積極的に自己啓発に取り組んだりするため、アウトプットの質が高まっていきます。難度の高いタスクにも果敢に立ち向かっていくでしょう。個人の自発性が高まれば、管理職の負担も軽減されるはずです。個人の生産性が上がればチーム全体、部署全体のパフォーマンスも上がっていき、結果的に組織の生産性も向上していきます。
メリット2:社内の人間関係が良好になる
ワークエンゲージメントが高く、自発性の高い社員は、指示や命令がなくても、担当業務や役割以外の行動も積極的に行う傾向が見られます。例えば、自分の仕事が終わった後で、多忙な同僚を手伝う、チームリーダーに何かできることはないか申し出る、といった行動が増えていきます。つまり、ワークエンゲージメントが高い社員は、自分の仕事だけでなく、周囲に対してもプラスの効果をもたらします。結果的にチームや部署内の人間関係が良好になり、チームワークもより強固なものになっていくでしょう。
メリット3:離職率の低下につながる
ワークエンゲージメントを高めることは、社員の離職率の低下にもつながります。厚生労働省の分析によると、ワークエンゲージメントと新入社員の入社3年後の定着率や社員の離職率には、相関関係があることが分かっています。ワークエンゲージメントが向上すれば、新入社員の入社3年後の定着率も高まり、社員の離職率は低下しています。つまり、ワークエンゲージメントを高める取り組みを推進していくことで、社員が定着しやすい組織にできるのです。採用コストを抑えることができ、中長期的な視点での人材育成も行えるため、結果的に組織目標も達成しやすくなるでしょう。
メリット4:メンタルヘルスの改善に寄与する
厚生労働省の分析では、ワークエンゲージメントを高めることで、仕事の中で過度なストレスや疲労を感じる度合いを低下させる可能性があることも確認されています。忙しい環境でも精神的なストレスを感じにくく、仕事に対してやる気や前向きな姿勢を保ちやすくなれば、心身の健康も保たれやすくなるでしょう。一方、前述のワーカホリズムの指標となるワーカホリックスコアについては、高まるほどに仕事の中で過度なストレスや疲労を感じる傾向にあります。つまり、社員のメンタルヘルスを改善し、健康に保つうえでは、ワークエンゲージメントを高める観点が重要です。
メリット6:顧客満足度の向上
ワークエンゲージメントを向上させる取り組みを推進することで、顧客満足度も向上していきます。社員それぞれが付加価値の高い仕事を行い、自社の商品やサービスの魅力もアップし、購入・利用後の満足度を押し上げます。社員が生き生きと働く姿勢や定着率の高さも顧客からの信頼度を向上させるでしょう。顧客満足度がアップすれば、従業員エンゲージメントやワークエンゲージメントもアップするというように、組織内に好循環が生まれていくはずです。
ワークエンゲージメントの向上に有効な雇用管理
ワークエンゲージメントの考えでは、良好な仕事環境を含む「仕事の資源」と自己効力感や楽観性などを指す「個人の資源」を豊富にすることで、ワークエンゲージメントを高められると考えられています。つまり、社員のワークエンゲージメントを向上させるには、個人の考え方だけなく、組織全体でそれを高めていく取り組みが必要です。厚生労働省による「令和元年版労働経済の分析」では、ワークエンゲージメント(働きがい)の高い企業で実施されている雇用管理の取り組み内容を公開しています。ここでは、主な内容を5つの分野に分けて紹介します。
1.社内コミュニケーション
- 職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化
2.人事評価
- 能力・成果等に見合った昇進や賃金アップ
- 人事評価に関する公正性・納得性の向上
- 優秀な人材の抜擢・登用
3.ワークライフバランス
- 労働時間の短縮や働き方の柔軟化
- 仕事と育児との両立支援
- 有給休暇の取得推進
4.人材育成・能力開発
- 能力開発機会の充実や従業員の自己啓発への支援
- 業務遂行に伴う裁量権の拡大
5.健康管理
- 仕事と病気治療との両立支援
このように働きがいの高い企業では、ワークエンゲージメントの向上につながる雇用管理を多方面から実施しています。また、働きがいが高い企業と低い企業とのギャップ差については、1位が「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」、2位が「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」、3位が「業務遂行に伴う裁量権の拡大」でした。特に、1位と2位でのギャップが大きく、職場の人間関係や労働時間の長さ、望む働き方が実現できているかが、働きがいに強く影響する要因だといえます。
ワークエンゲージメントを高めるための人材育成
続いて、こちらも厚生労働省による「令和元年版労働経済の分析」を参考に、ワークエンゲージメントを高めるための具体的な人材育成の例を見ていきましょう。厚生労働省の分析によると、ワークエンゲージメント(働きがい)が高い企業では、以下のような人材育成を実施しています。
- 定期的な面談(個別評価・考課)
- 目標管理制度による動機づけ
- フィードバックの実施による動機づけ
- 企業としての人材育成方針・計画の策定
- 指導役や教育係の配置
- 本人負担の社外教育に対する支援・配慮
- キャリアコンサルティングなどによる将来展望の明確化
人材育成についての働きがいが高い企業と低い企業のギャップ差では、1位が「指導役や教育係の配置」、2位が「キャリアコンサルティングなどによる将来展望の明確化」3位が「企業としての人材育成方針・計画の策定」という結果でした。つまり、人材育成については、まずは企業としての人材方針を明確に打ち出したうえで、若手のうちから社員の教育をしっかりと行うことが大事です。そのうえで、キャリアコンサルティングなどで将来展望を明確化することが、ワークエンゲージメントの向上に効果的と考えられます。
ワークエンゲージメントを高める取り組み事例10選
ワークエンゲージメントの向上に有効な雇用管理や人材育成の考え方を踏まえて、社内で行うべき具体的な取り組み事例を10パターン紹介します。人事部としては、以下のような取り組みが実現できるような働きかけを社内の各部門に対して行いましょう。
1.上司からの挨拶を習慣化
職場でのコミュニケーションを活性化するうえで、ベースになるのが日々の挨拶です。挨拶は、相手に対する好意や興味、敬意を示す有効な表現方法です。ポイントは、上司から部下に毎朝挨拶を行うようにすることです。できるだけ相手の目を見て、笑顔で挨拶する組織風土にしていきましょう。1日のスタートを明るい雰囲気で始められれば、チームの雰囲気が良くなり、働きがいも向上するでしょう。挨拶をきっかけに、業務の相談や雑談が始まるなど、コミュニケーションが活性化することも少なくありません。
2.1on1ミーティングを定期的に実施
上司と部下との1on1ミーティングを定期的に行うことも有効です。ほかのメンバーもいるチームミーティングでは、業務の報告以外の話はしづらいものです。例えば、月に1回の頻度で1on1を行い、部下が困っていることはないかなどを確認してみるとよいでしょう。部下の現状を把握でき、必要な支援やアドバイスを行えます。直近の貢献に対するフィードバックも行えるでしょう。仕事の話だけではなく、近況を尋ねるなど、ざっくばらんな話も行うのがポイントです。上司に気にかけてもらうことで、部下の働きがいが向上し、信頼関係も生まれやすくなります。
3.目標管理ミーティングの実施
ワークエンゲージメントを高めるうえでは、仕事に達成感を持たせることも大事です。達成感は仕事へのやりがいを与えてくれ、自信にもつながります。1on1とは別に、半期ごとなどに上司と部下との間で目標管理ミーティングを行うとよいでしょう。最初に目標を設定し、達成度を上司と部下で確認することで、自分の成長を確かめられ、次のステップに進むための課題も把握できます。達成度を人事評価と連動させることで、人事評価に対する公平感や納得感も高まり、ワークエンゲージメントを維持できます。
4.メンター制度の導入
先輩社員が後輩社員の仕事面に加え、キャリ形成などをも含めた幅広いサポートを行うメンター制度を導入することも有効です。OJTのように同じ職場の先輩・後輩がペアになるのではなく、基本的に業務上の利害関係がない別部門の先輩とペアになるのがメンター制度の特徴です。優秀な先輩社員のスキルを伝承でき、社内に信頼できる人間関係も構築できます。同性の場合は、メンター役が将来のロールモデルにもなり得るでしょう。メンター制度の導入によって、若手社員が社内に安心できる居場所を確保でき、仕事や将来への不安も軽減されることから、ワークエンゲージメントが高まります。
5.業務の効率化
仕事量を適切に保ち、労働時間を短縮することもワークエンゲージメントの向上には必要です。そのためには、仕事への「ムリ・ムダ・ムラ」がないかを洗い出し、優先度の低い業務を削除・効率化する取り組みを社内で推進していきましょう。特定の社員への業務の偏りを解消する、情報の共有化を図ることも大事です。RPAやITツールを導入して、業務を抜本的に改革することも必要でしょう。部署の人数が少ない場合には、業務のアウトソースも効率化のための有効な手段です。
6.有給休暇の取得を推進する独自の取り組み
有給休暇を積極的に取得させることもワークエンゲージメントの向上につながります。また、ワーカホリズムの解消にもなるでしょう。ただし、社員個人の判断にゆだねていると、なかなか取得は進まないものです。上司が積極に取得するほか、閑散期の連続取得を推奨する制度などを導入して、全員が同じように休みやすい仕組みづくりを整えましょう。有休を取ってしっかりと心身を休めることで、リフレッシュ効果やチーム内での協力体制の構築が促進され、社員のワークエンゲージメントが向上します。
7.社内公募制度の導入
人事異動の場合、本人の希望や意思に沿わなかったり、強みを生かせないポストにアサインされてしまったりする場合もあるでしょう。社内公募制度を導入し、社員が自らの意思で自発的にやりたい仕事に応募できる仕組みを取り入れておくこともワークエンゲージメントの向上に効果的です。現状の仕事内容に不満がある社員の離職の防止にもつながるでしょう。ただし、かえってモチベーションが下がらないよう、選外となってしまった社員へのケアは別途考えておく必要があります。
8.テレワークをはじめとする柔軟な働き方の推進
柔軟な働き方ができる制度の導入は、ワークエンゲージメントの向上につながります。育児や介護などのライフイベントと仕事を両立させやすくなり、キャリアも継続しやすくなるためです。例えば、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、テレワークを導入した企業も多いことでしょう。在宅勤務では通勤時間が不要となり、社員の身体的負担が軽減されます。また、人によっては一人のほうが業務に集中できる場合もあります。テレワークの推進によって、家族と過ごす時間が増えた、自己啓発に取り組む余裕ができたと感じている人も多いようです。
テレワークを行う社員の業務管理や人事評価といった課題への対応は必要でしょう。しかし、テレワークを導入して社員のワークライフバランスの改善を図ることはワークエンゲージメントの向上につながるため、それを上回るメリットが期待できます。このほか、フレックス勤務や時短勤務なども併せて導入を検討しましょう。
9.管理職への権限の委譲
ワークエンゲージメントの向上につながる雇用管理では、「業務遂行に伴う裁量権の拡大」も大事なポイントでした。トップダウン型の組織の在り方を見直し、現場の管理職などに必要な権限を委譲していくこともワークエンゲージメントを高める方法の一つといえます。例えば、仕事のやり方や部下の配置、新人の採用などについて現場の管理職に権限を与えることで、現場に最も必要な判断ができ、適した人材配置が叶うでしょう。
目標達成に必要な権限を洗い出し、その権限を与えることで、現場の管理職はやりがいを感じられ、成果も上がってくるはずです。おのずとワークエンゲージメントも向上するでしょう。このほか、全社員が参加可能なワークショップを実施し、最優秀に選ばれたプロジェクトを新規事業として採用するといった形で現場社員に裁量性を持たせる方法もあります。
10.オフィス環境の改善・整備
いくら前向きな気持ちで出社しても、「汚い」「暗い」といった不健康なオフィス環境では心身の健康を保てません。ワークエンゲージメントを高く保つうえでは、オフィス環境も重要です。オフィス内を毎日掃除する、日当たりを良くする、空調を整備するなどして、社員が健康的な体を維持できるような環境づくりが必要です。必要に応じてレイアウトを見直す、大掃除をして不要な書類やキャビネットを減らして執務スペースを広げるなどの作業も行い、社員が快適に仕事のできる環境を整えましょう。定期的に、社員に対してオフィス環境についてのアンケート調査を行うことも有効です。
ワークエンゲージメントの向上は人手不足緩和策になる
社員のワークエンゲージメントが高まれば、一人ひとりの労働生産性が上がり、社内の風通しも良くなります。結果的に、離職率の低下にもつながります。人手不足が叫ばれる時代においては、優秀な人材の流出を防ぐことが肝心です。働く環境を整えて社員のワークエンゲージメントを高め、人手不足下でも安定的に成長できる組織を目指しましょう。