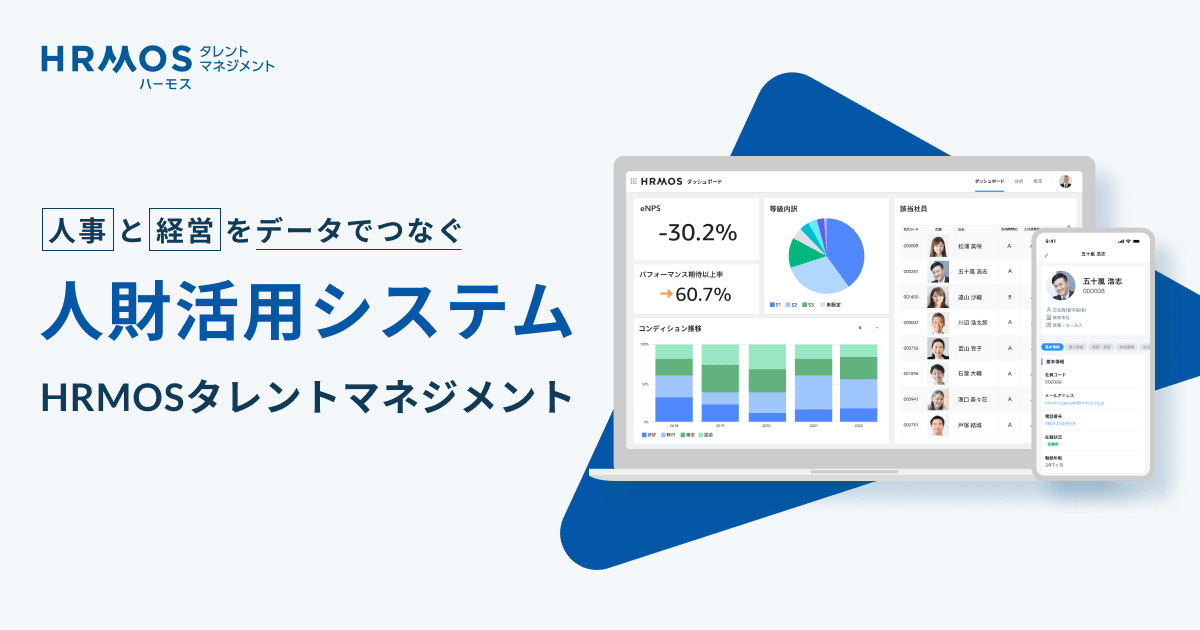目次
近年、チームビルディングにおいて「心理的安全性」の重要性が大きな注目を集めています。
心理的安全性を高めることは、個々のパフォーマンス向上や組織全体の生産性向上など、多くのメリットをもたらすとされています。
では、職場で心理的安全性を高めるには、どうすればよいのでしょうか。
本記事では、職場の心理的安全性の作り方や高める方法などについて解説します。
企業が抱えていた課題の解決事例を公開
- 入社手続きの効率化
- 1on1 の質の向上
- 1on1の進め方
- 従業員情報の一元管理
- 組織課題の可視化
株式会社サンリオ、トヨタカローラ山形株式会社、株式会社GA technologies社など、タレントマネジメントシステム活用によりどのような効果が得られたのか分かる資料を公開中
⇒実際の事例・機能を見てみる心理的安全性の定義と重要性
心理的安全性の定義や注目を集める背景、重要性についてご説明します。
心理的安全性とは何か
心理的安全性とは、何らかのリスクが伴う言動をとった場合でも、組織はその状況を受け入れてくれるだろうと考えられる心理状態のことです。
例えば、多数が賛成している状況下でも反対意見を述べられたり、分からないことを素直に質問できる環境は、心理的安全性が高い状態にあると言えます。
つまり、心理的安全性が高い場合、人は周囲の反応を恐れることなく、率直な意見を伝えられるようになります。
「心理的安全性」(psychological safety)は、マサチューセッツ工科大学の教授であるエドガーH.シャインとウォーレン・ベニスによって1965年に提唱された概念です。
さらに、ハーバード・ビジネススクール教授であるエイミー・C・エドモンドソンは1999年、チームの成果と心理的安全性の関係について発表した論文「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」の中で、心理的安全性を「a shared belief that the team is safe for interpersonal risk taking」と定義し、組織における心理的安全性の重要性を広めました。
エドモンドソンは、心理的安全性は「率直であることが許されるという感覚」であると示しています。
なぜ今、心理的安全性が注目されているのか
心理的安全性が注目を集める背景には、Googleの「プロジェクト・アリストテレス」と呼ばれる研究が関係しています。
このプロジェクトは、効果的なチームをつくり上げる条件は何であるかを探る目的で実施されたものです。
同社では2012年から4年間にわたり、180のチームを対象とした調査を開始しました。
その結果、効果的なチームづくりにおいては、「誰がチームのメンバーであるか」よりも「チームがどのように協力しているか」が重要であると結論づけました。
また、チームの効果に最も影響する因子は「心理的安全性」であると公表しました。
このGoogleの研究成果は、多くの企業の注目を集めました。その結果、現在、多くの企業が心理的安全性の向上に取り組んでいます。
<関連記事>
職場の問題行動はなぜ起きる? 沈黙、偏見、不公正の構造を解く<日本大学大学院 田中 堅一郎教授>
心理的安全性を高める4つの因子
後述する「心理的安全性のつくりかた」の著者である石井遼介らは、10,000人、800チームの調査を行い、心理的安全性を高める4つの因子を導き出しています。
1.話しやすさ
自分の考えを伝えやすい、話しやすい環境であることは心理的安全性を高めるうえで重要な因子です。
周囲とは異なる意見でも率直に発言できる環境は、コミュニケーションを活発にし、メンバーの相互理解を深めます。
また、話しやすい環境では、能力や知識がないことを非難される不安がないため、分からないことを躊躇せずに質問でき、悩みも気軽に相談できる風通しのよい組織をつくります。
さらに、多様な視点から交わされる活発な意見は、イノベーションの創出につながる土壌が生まれるとも考えられます。
2.助け合い
チーム内で誰かが困っているとき、問題が発生したときに、互いが助け合える環境であることも、心理的安全性の向上に必要な因子です。
チームの中に助け合いの精神が浸透すると困ったときに相談をしやすくなるため、トラブルを最小限に抑えられます。また、解決策についての話し合いが実施されるため、課題解決能力も高まるでしょう。
メンバーが互いの強みを生かし、弱点を補い合える環境になると、困難な課題も解決しやすくなり、組織の目標を達成できる強いチームとなります。
3.挑戦
心理的安全性が高い職場では、結果よりも“挑戦する姿勢”そのものが重視されます。
たとえ、結果が失敗に終わった場合でも、心理的安全性の高い環境では挑戦を非難される不安がないため、メンバーは失敗を恐れずに積極的に挑戦ができるようになります。
さらに、挑戦の結果を踏まえ、改善すべき点について率直な意見交換を行えるため、次回の挑戦の成功率を高められるでしょう。
4.新奇歓迎
“新奇歓迎”とは、既存の枠にとらわれず、目新しいアイデアや発想を前向きに受け入れる姿勢を指します。
多様な意見を尊重し、新しいアイディアやこれまでにはない価値観を受け入れる環境では、メンバーはより積極的に自分の考えを伝えやすくなります。
また、自由な発言がしやすくなるため、建設的な話し合いが行われ、新たなビジネスチャンスにつながる独創的な発想が生まれる可能性も高めます。
したがって、新奇歓迎の姿勢も心理的安全性を高めるためには必要不可欠な因子だといえます。
心理的安全性を妨げる4つの不安
チームの成果と心理的安全性の関係性を論じたエドモンドソン教授は、次の4つの不安因子によって心理的安全性を妨げられるとしています。
1.無知と思われる不安
上司やメンバーに「こんなことさえ知らないのかと思われるのではないか」「無知であることが知られるとバカにされるのではないか」という不安は、質問をためらう要因となります。
無知と思われる不安によって分からないことを理解しないまま業務を進めると、結果としてミスの発生確率が高まります。
また、質問しにくい雰囲気では、チームの共通理解も低下するため、認識にずれが生じ、組織全体のパフォーマンスも低下する恐れがあります。
2.無能と思われる不安
仕事でミスをしたときには「こんなこともできないのかと思われないか」「なんて能力が低いのだろうと思われないか」という不安が生じます。
無能と思われるのではないかという不安は、ミスの報告を遅らせ、さらに自分ではない他の要因に責任を転嫁するような行為を招く可能性があります。
ミスを隠蔽すると、失敗から学ぶ機会を失い、同様のミスやより深刻なトラブルにつながる可能性があります。
また、ミスを過度に恐れると新しいことへの挑戦意欲も低下するため、イノベーションの創出も難しくなります。
3.邪魔と思われる不安
ミーティングの際に、周囲とは異なる考えがあっても「こんな発言をしたら他のメンバーから疎ましがられないか」と考えると、意見を自由に言いにくくなります。
また、「自分の発言はミーティングの進行を邪魔してしまうのではないか」という不安も積極的な発言を妨げます。
チームから疎外されるのではという不安があると、提案された意見に同調する人ばかりとなり、活発な意見交換はなされません。
そのため、新たなアイディアが生まれにくくなります。また、互いの考えを理解しにくくなるため、チームワークも低下するでしょう。
4.ネガティブと思われる不安
メンバーの発言や提案に対し、よりよいアイディアを思いついた場合でも「人の意見をよく否定する人だと思われないか」「よく反対をする否定的な人だと思われるのではないか」という不安があると発言がしにくくなります。
ネガティブだと思われることへの不安は、反対の意見やよりよいアイディアの提案を妨げます。
多様な意見や考えを尊重する環境が整っていない場合、課題を改善しにくくなり、組織の成長を停滞させる要因にもなり得ます。
システムを活用した企業の改善事例多数
株式会社サンリオ、トヨタカローラ山形株式会社、株式会社GA technologiesなど、どのような効果が得られたのか分かる事例を公開中
心理的安全性を測定する方法
心理的安全性の測定にあたっては、前述のエドモンドソン教授が論文で示した7つの質問による簡単なアンケートが広く活用されています。以下にその質問をご紹介します。
- チームでミスをしたら非難されることが多い
- チームのメンバーは問題や困難な課題を提起することができる
- このチームでは、自分とは異なるものを排除することがある
- このチームならリスクを冒しても安全だと感じられる
- このチームのメンバーには助けを求めにくい
- このチームには自分の努力を故意に踏みにじるような人はいない
- このチームのメンバーと仕事すると自分のスキルと才能が尊重され、役立っていると感じられる
上記の質問について、1〜7までの段階で評価してもらい、ポジティブな質問(2、4、6、7)では点数をそのまま、ネガティブな質問(1、3、5)では点数を反転させます。
合計した点数の高さによって、心理的安全性の高さを評価することが可能です。
心理的安全性を高めるメリット
職場の心理的安全性を高めることで得られる主なメリットを3つご紹介します。
コミュニケーションの活性化
心理的安全性が高まると、発言することに対する不安が解消されるため、コミュニケーションが活性化します。コミュニケーションが活発になると互いの理解が深まるため、チームワークも強化されます。
さらに、それぞれの強みや弱点も把握しやすくなるため、互いが協力し合い、業務効率が向上することでチームの目標も達成しやすくなるでしょう。
また、上司やメンバーに遠慮することなく率直な意見を伝えられるため、さまざまな視点からの意見が集まります。
どんな発言でも受け入れられるようになると、物事を意欲的に考えるようになるため、チーム全体の問題解決能力も高まります。
イノベーションの促進
心理的安全性の向上は、イノベーションの創出も促進します。
周囲とは異なる意見であっても気兼ねなく提案しやすい組織文化においては、多様な考えが尊重されるため、斬新なアイディアが生まれる可能性が高まります。
加えて、心理的安全性の高い環境では、ミスや失敗を恐れずに、新たなことに挑戦しやすくなる点も、イノベーションの創出を促進させます。
そのうえ、ミスや失敗の原因を共有し、意見を交換することもできるため、失敗からの学びを次の挑戦に生かすことも可能です。
したがって、心理的安全性が高い組織では独創的なアイディアが生まれやすく、ブラッシュアップもしやすいため、イノベーション創出を後押しする要因となります。
離職率の低下
心理的安全性が担保されると、新たなことへの挑戦意欲やチームの目標を達成したいという意欲が高まり、従業員エンゲージメントが高まります。
何より、自分のアイディアを積極的に提案でき、失敗を恐れずに挑戦できる環境では、仕事のやりがいも大きくなるでしょう。
従業員エンゲージメントが高まると、会社に対する愛着心も高まるため離職率が低下し、優秀な人材の定着にもつながります。
さらに、上司やメンバーに遠慮せずに自分の意見を伝えられ、自分らしさを発揮できる環境では精神的なストレスも軽減します。この点も離職率の低下につながると考えられます。
<関連記事>
従業員エンゲージメントとは? 高める方法や事例から学ぶ成功のポイントを解説
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
心理的安全性を高める方法
心理的安全性を高めると、さまざまなメリットを得られます。
では、心理的安全性はどのようにすると高めることができるのでしょうか。
リーダーシップの発揮
職場環境には、現場をまとめるリーダーがつくり出す雰囲気が大きく影響します。
メンバー同士が自由に意見を言い合える雰囲気であっても、リーダーには率直に意見がしづらい状況であれば、心理的安全性を高めることはできません。
リーダーは、自分がチームの心理的安全性を高める意識を持ち、メンバーが気軽に話しかけやすいよう、親しみやすい雰囲気をつくることが重要です。
また、失敗を恐れず、新たな挑戦をしやすい環境を整えるためには、ミスや失敗を叱責するのではなく、原因を振り返り、解決策につながるようなアドバイスを行う姿勢も必要になるでしょう。
オープンな対話の場づくり
エドモンドソンはメンバー自身が心理的安全性を高めるためには、「好奇心を形にし、積極的に質問する」ことが重要だと指摘しています。
メンバーが困ったときや悩んだときに気軽に相談できる環境をつくることも重要です。リーダーには、日ごろからメンバーに積極的に話しかけ、密にコミュニケーションを図る姿勢が求められます。
また、さまざまな年齢やポジションの従業員がミーティングに参加する場合には、特定のメンバーに発言が偏り、他の従業員が意見を言い出しにくいケースもあります。
平等に意見を出せる環境をつくり出すためには、全員に発言の機会が与えられるラウンドロビン方式を採用したり、ファシリテーターが発言機会を均等にするような配慮を行ったりする必要があるでしょう。
失敗を学びに変える文化の醸成
エドモンドソンは「仕事を実行の機会ではなく学習の機会と捉える」「人は間違うということを認める」ことも、メンバー自身が心理的安全性を高めるうえで重要な取り組みだと指摘しています。
仕事はスキルを発揮する場ではなく、学びの場と捉える意識が、メンバーの成長を促します。
また、失敗やミスを過剰に恐れる場合、新たなことにチャレンジできないだけでなく、心理的安全性も高めることができません。
そのため、人間は誰でも間違えるものであるという認識のもと、失敗やミスを学びに変える文化を醸成していくことも必要になります。
多様性の尊重と包摂
心理的安全性の高い環境をつくるためには、まず、多様性を尊重し、自分とは異なるものも包摂する姿勢が求められます。
大多数の意見が正しいとは限りません。他にはない個性的な意見が新たなアイディアにつながるケースや組織の課題を解決に導くケースもあります。
多様性が尊重され、包摂が実践されている職場環境であると実感できれば、メンバーの心理的安全性を向上させます。
また、心理的安全性の向上により、多様な意見が提案されるようになると、イノベーションの創出も促進されるでしょう。
<関連記事>
心理的安全性を高める具体的な取り組み事例
心理的安全性を高める具体的な取り組みの例を3つご紹介します。
1on1ミーティングの活用
1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で向き合い、気軽な雰囲気でコミュニケーションを取れる絶好の機会です。
1on1ミーティングは、上司が部下の話に耳を傾け、部下のモチベーションアップを図ったり、部下の自発的な成長を促したりする目的で実施されます。
業務上の話だけでなく、プライベートな相談を受けても問題はありません。
定期的に1on1ミーティングを実施すると、普段から気軽にコミュニケーションが取りやすくなります。
さらに、部下との信頼関係を構築しやすくなるため、悩みも早期にキャッチしやすくなるといった効果も期待できます。
<関連記事>
ピアボーナスの導入
ピアボーナスとは、仲間を意味する「peer」と報酬を意味する「bonus」を組み合わせた言葉で、メンバー同士が頑張っている人や感謝したい人などに対し、ポイントをプレゼントできる制度です。
たまったポイントは、金銭や商品に交換できる仕組みです。
ピアボーナスでは、メンバーからの信頼や感謝を報酬や贈りものという形で受け取れるため、チームから認められているという実感を抱きやすくなります。
また、ポイントを送る側も自分の気持ちを伝えることができるため、双方の心理的安全性を高める効果があります。
メンター制度の運用
メンター制度も心理的安全性を高める有効な取り組みです。メンターは、仕事に対する不安や悩みなど、メンティーとなるメンバーの話に耳を傾け、メンティーの成長をサポートします。
メンターは、否定せず耳を傾け、時にはアドバイスや励ましを送ることで、メンティーの不安をやわらげます。
定期的にコミュニケーションを重ねることでメンターとメンティーの間には信頼関係が築かれるため、悩みや不安も気軽に相談できるようになります。
自分の考えを率直に伝えることができる相手がいる環境は、メンバーの心理的安全性の向上につながります。
<関連記事>
メンタリングプログラムとは?メンタリングの意味やメリット、プログラムの導入方法について詳しく解説!
心理的安全性を高めるうえでの注意点
心理的安全性の高い職場は、メンバーや組織にさまざまなメリットをもたらしますが、注意しなければならない点もあります。
過度な心地よさを求めすぎない(ぬるま湯組織)
心理的安全性とは、自身の意見を率直に述べることができる状態のことです。
ありのままの自分を受け入れられる環境であるため、働きやすい環境である一方で、単なる「ぬるま湯組織」になっては本末転倒です。
ぬるま湯組織の場合、居心地を優先するために意見の対立を避けるケースや、相手の間違いも受け流すケースがあります。
しかし、心理的安全性の高い環境は、多様な意見の交換を歓迎する、活発なコミュニケーションを目指す組織です。
心理的安全性が高い環境とぬるま湯組織には、明確な違いがあります。
心地よく働ける環境の構築は目指すものの、メンバーには責任を持たせることで、組織がぬるま湯化しないよう、メリハリのあるマネジメントが求められます。
一晩で構築できるものではない
たとえ、1on1ミーティングやメンター制度、ピアボーナスなどの制度を導入しても、心理的安全性は短期間で高められるものではありません。
どんな発言も受け入れられる、挑戦して失敗をした場合でも叱責されることがない、自分が組織に必要とされていると実感できる環境を整えるまでには時間がかかるものです。
そのため、心理的安全性を高める文化が組織に浸透するまでには時間がかかることを理解しておかなければなりません。
したがって、一過性の取り組みで終わらせず、粘り強く継続する姿勢が求められます。
人事評価制度との関連性
不公平さを感じる評価制度ではチーム内に嫉妬や羨望の感情が生まれ、協力体制を構築しにくくなる可能性があります。
また、成果を重視する評価制度では、上司からの評価が低くなることを防ぎたいという心理が現れ、挑戦への意欲を阻害する恐れもあるでしょう。
さらに、評価に関するフィードバックが不足した場合、評価に対する納得感が得られず、従業員エンゲージメントが低下する可能性もあります。
タレントマネジメントを活用すると、メンバーのスキルや成果、行動などを踏まえた総合的かつ公正な評価が可能です。
1on1ミーティングで話した内容も記録できるため、的確なフィードバックがしやすく、継続的な取り組みの効果を計測することもできます。組織内の心理的安全性を高めるうえでは、人事評価制度の見直しの検討も必要です。
<関連記事>
【事例付き】タレントマネジメントとは?目的、システム導入や比較・活用方法
心理的安全性を高めるための企業事例
成功事例を知ると、自社の取り組みを推進する際の参考になるでしょう。心理的安全性を高めることに成功した3社の事例をご紹介します。
Google LLC
前述のように、Googleはアリストテレスプロジェクトを実施し、チームの効果を高めるには心理的安全性の向上が重要であることを突き止めました。
同社では研究結果の社内浸透を目的に、各チームでワークショップを実施しました。そこでは、心理的安全性に良い・悪い影響を与える行動を紹介し、重要性や自身のチーム状況について考える機会を提供しています。
さらに、チームにおいて心理的安全性の有無がどのような違いをもたらすか、自身のチームの心理的安全性の状況を問い、メンバーの当事者意識を喚起することによって、心理的安全性の向上につなげています。
日野自動車株式会社
日野自動車株式会社では、社会的責任を果たす企業への生まれ変わりを目指し、3つの改革を推進しています。その一つが「人材尊重」を中心に捉えた組織風土改革です。
同社では、パワハラゼロ活動によって互いが協力し合う文化を醸成し、心理的安全性を高める職場づくりに取り組んでいます。
2022年には風土改革チームを立ち上げ、組織横断での対話会や各部署での対話会を実施し、本音の対話ができる環境整備を進めてきました。
これにより、経営層へ意見する従業員の増加や自発的な改革の取り組みの開始などの効果を得ています。
また、同社では、PR誌においても「組織力アップのカギ 心理的安全性のつくりかた」と題した特集を組み、シリーズで職場における心理的安全性の重要性や具体的な取り組みを伝える啓発活動を実施しています。
静岡鉄道株式会社
静岡鉄道株式会社も心理的安全性を高める職場づくりに注力している企業です。
同社では「自分たちの会社は自分たちでよくするんだ」という思いのもと、人事部と労働組合が協働し「みんなの100日プロジェクト」を立ち上げました。
その中の一つとして「心理的安全性のプロジェクト」が進められています。
プロジェクトでは、はじめに従業員の経歴や趣味などを含めたプロフィールを紹介する「しずてつ仲間図鑑」を社内イントラに公開し、コミュニケーション機会の増加を図りました。
各部の部長がランチタイムにスピーカーを務める交流イベントや、新入社員へのWeb寄せ書きなども行われました。
同社では、取り組みによって部署を超えた交流が生まれ、社内の一体感が高まったとともに、社内に心理的安全性の認知が広がったとしています。
これらの取り組みは高く評価され、心理的安全性アワード2022においてシルバーリング、2023では最高位のプラチナリングの受賞に至っています。
心理的安全性と類似する概念
心理的安全性にはいくつかの類似した概念があります。類似した概念との違いや関係性についてご説明します。
心理的資本との違い
心理的資本とは、働く人が自律的に困難を乗り越えようとする心の力のことです。
心理的資本は「Hope(希望)」「Efficacy(自己効力感)」「Resilience(回復力)」「Optimism(楽観性)」の4つの要素で構成されています。
一方で心理的安全性は、誰もが率直に意見を伝えられる環境そのものを意味します。
いずれもチームの効果を高めるためには必要なものですが、心理的資本はメンバーの心の力であるのに対し、心理的安全性は成果を上げやすい組織の環境である点に違いがあります。
<関連記事>
自己効力感とは?意味や高める方法、自己肯定感との違いを簡単に解説
帰属意識との関係性
帰属意識とは、特定の組織や集団に属している意識のことで、企業における帰属意識とは、自分が会社を構成している一人だという自覚を指します。
帰属意識が高くなるとモチベーションとパフォーマンスが向上するとともに、会社への愛着心が高まるために離職率も低下します。
心理的安全性が高まるとコミュニケーションが高まり、帰属意識の向上につながります。
また、帰属意識が高まること自体がメンバー間の交流を促進し、結果として心理的安全性の向上にも寄与します。そのため、両者は相互に作用し合う関係にあるといえるでしょう。
<関連記事>
メンタルヘルスとの関係性
メンタルヘルスとは、心の健康状態を意味する言葉です。
心理的安全性とメンタルヘルスは、帰属意識同様、相互に作用し合う関係にあります。
心理的安全性が高い職場では、率直な意見が言いやすく、失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気があります。加えて、上司や同僚に気軽に相談できる関係が築かれることで、ストレスの蓄積も抑えられます。
そのため、心理的安全性が高い環境では、不安や抑うつなどを軽減でき、メンタルヘルスを向上させることができます。
反対に心理的安全性が低い職場では、自由な発言が抑制され、悩みを一人で抱え込むケースが増えるため、メンタルヘルスが悪化する可能性があります。
<関連記事>
EAP(従業員支援プログラム)とは?従業員のメンタルヘルス対策とその効果
心理的安全性を学ぶためにおすすめな本
心理的安全性について学習できるおすすめの本を3冊ご紹介します。
「心理的安全性のつくりかた」著:石井遼介
「科学的視点」と「現場目線」の双方から心理的安全な職場づくりを目指す組織開発のプロフェッショナルである株式会社ZenTech代表の石井遼介の著作です。
日本の組織・チームの心理的安全性構築についての研究を進める著者は、心理的安全性の高い職場の実現に必要な心理的安全性の4つの因子「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」を特定しました。
また、本書では、心理的安全性の高いチームをつくるリーダーに求められる「心理的柔軟性」や、心理的安全性を高める4つの因子を活性化させるためのフレームワークについて解説しています。
個性を生かし、チーム全体が学び、成長するチームビルディングの実践に役立つ1冊です。
「恐れのない組織」著:エイミー・C・エドモンドソン
組織における心理的安全性の重要性を説いたエドモンドソンの著作です。
著者は、心理的安全性は万能ではなく、それ自体が組織を動かす原動力ではないとしつつも、重要な土台であると位置づけています。
しかし、心理的安全性を高めると、回避できる失敗を防ぐことができ、困難な目標の達成も叶えられると主張します。
本書の中では、心理的安全性の研究結果を実践に生かす方法、フィアレスな職場を実現するために必要なポイントなどが具体的に示されており、組織の成功につながるさまざまなヒントを得ることができます。
「心理的安全性 最強の教科書」著:ピョートル・フェリクス・グジバチ
起業家教育事業会社の代表である、ピョートル・フェリクス・グジバチの著作です。同氏は、Googleのアジア・パシフィック人材・組織開発責任者として人材開発や組織改革、リーダーシップマネジメントに従事した経験を持ちます。
本書の中で著者は、心理的安全性は、良好そうな人間関係を取り繕い、意見の対立を回避するものではなく、職場においては、健全な対立がある環境が心理的安全性が高い状態だと主張します。
そのうえで、心理的安全性を高め、ビジネスの成果を出す手法を「理解編」「マインドセット編」「実践編」の3つのパートから解説しています。
20年間、日本で働いた経験を持つ著者が、日本のビジネスパーソンに向けて書き下ろされた、日本企業における心理的安全性の教科書であるともいえる一冊です。
まとめ
心理的安全性が高い職場では、メンバーは上司や同僚に臆することなく、自由に意見を述べることができ、コミュニケーションが活性化します。
その結果、ミスや失敗も速やかに共有され、課題解決のための意見交換も行われるため、チームの成果を高めやすくなります。また、多様な視点からの意見が出されるため、イノベーションも創出しやすくなるでしょう。
さらに、率直に意見ができる職場環境はストレスを低減させるため、従業員エンゲージメントを高め、離職率を低下させます。
心理的安全性の構築には時間がかかりますが、地道な取り組みが組織全体の成長を促します。
まずは、1on1ミーティングのような取り組みやすい施策から始めてみるのも良いでしょう。
心理的安全性向上の継続的な取り組みを支援するHRMOSタレントマネジメント
従業員の情報を一元管理できるHRMOSタレントマネジメントには、個人コンディションサーベイ機能が付加されています。
個人コンディションサーベイを活用すれば、従業員のモチベーション低下をリアルタイムで把握でき、最適なタイミングで1on1ミーティングを実施できます。
適切なタイミングで悩みや不安をヒアリングし、意見を否定せずに受け入れることで、従業員の心理的安全性は高まります。
加えて、1on1の実施記録や運用実態を可視化する機能も搭載されており、面談の形骸化を防ぎながら継続的な改善を支援します。
職場の心理的安全性を高める取り組みは、一朝一夕で実現するものではなく、継続が重要な意味を持ちます。ぜひ、心理的安全性向上の継続的な取り組みを支援するHRMOSタレントマネジメントの活用をご検討ください。