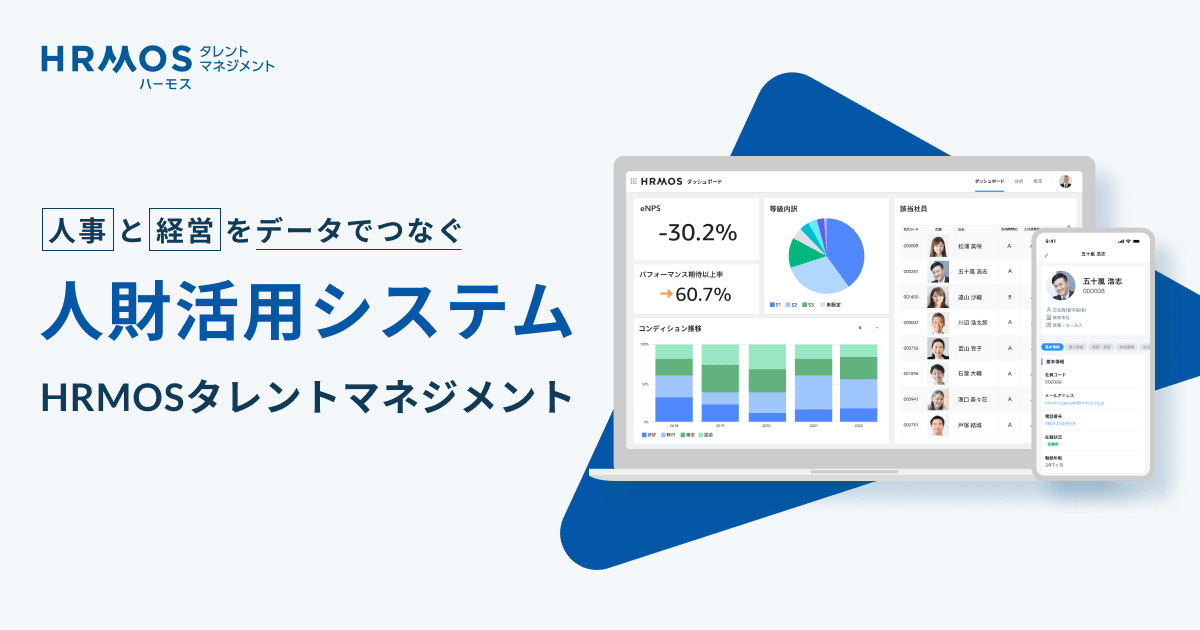目次
GDP(国内総生産)のような統計上の豊かさとは違い、一人一人が実感として幸せを感じているかを表すウェルビーイングは、日本を含む世界各国で注目されている指標です。
国や地域の幸福度を測定する場合だけでなく企業経営においても活用できます。
本記事では、ウェルビーイングとは何か、定義や測定・評価方法、企業がウェルビーイング経営に取り組むメリットなどを解説します。
企業経営においてウェルビーイングをどのように活用できるか、その具体例も紹介しますので、自社に導入できる方法がないか確認してみましょう。
ウェルビーイングとは
ウェルビーイング(Well-being)とは、身体的・精神的・社会的に良好な状態であることを指します。
well(よい)とbeing(状態)からなる言葉です。世界保健機関の憲章(WHO憲章)では、以下のように定められています。
| Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病または病弱が存在しないことではない。 |
つまり、WHO憲章が定める健康とは、単に病気をしていない状態を指すのではなく、多様な個人が、それぞれに幸せや生きがいを実感できる状態のことです。
GDPに代表される経済的な豊かさにとどまらず、精神的な充足や健康も含めて幸福や生きがいを捉える考え方が、国際的に重視されています。2015年の国連総会で採択されたSDGsの宣言文でも、ウェルビーイングに関する記述が盛り込まれました。
そのような中で、幸福や生きがいを測る指標のひとつとして、日本でもウェルビーイングが注目されるようになっています。
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
ウェルビーイングと類似する概念の違い
健康や幸福に関連する概念には、ウェルビーイング以外にもさまざまな用語が存在します。以下では、ウェルビーイングとよく混同されがちな「ウェルネス」「ウェルフェア」との違いについて解説します。
ウェルネスとの違い
ウェルネスとは「よりよく生きようとする生活態度」のことで、1961年にアメリカのハルバート・L・ダン博士が提唱した概念です。
世界ウェルネス機構は、ウェルネスを「全体的な健康状態につながる活動、選択、ライフスタイルの積極的な追求」と定義しています。日本においても2010年代後半から働き方改革が進む中で、「ウェルネス経営」という言葉が広まりました。
ウェルビーイングとウェルネスは、健康に関する概念である点は同じです。
ただし、ウェルネスは幸福を追い求める態度や姿勢を指すのに対して、ウェルビーイングは身体的・精神的・社会的に良好な状態そのものを指す点が異なります。ウェルネスを意識して健康を追求することで、その先にウェルビーイングという理想的な状態があるとされています。
ウェルフェアとの違い
ウェルフェア(welfare)は英語で福祉や幸福を意味する言葉です。生活困窮者をはじめとした社会的弱者に対する救済や保護など、社会福祉制度に関する言葉として使われます。
ウェルビーイングとウェルフェアは、幸福に関する概念である点は同じです。ただし、ウェルフェアは社会福祉の意味合いが強い点が異なります。
ウェルビーイングは、幸福や生きがいを個人が実感することに主眼を置いているため、個人に焦点を当てた概念といえます。一方で、ウェルフェアは社会福祉に関する概念であり、社会全体に焦点を当てている点がウェルビーイングとは異なります。
ウェルビーイングの測定と評価方法
ウェルビーイングには主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイングの2種類があります。以下では、それぞれのウェルビーイングの測定方法を紹介します。
主観的ウェルビーイングの測定
主観的ウェルビーイングとは、個人が自らの幸福をどのように認識しているかという主観的視点で捉えたウェルビーイングを指します。
主観的ウェルビーイングはその人の感じ方に基づくものなので、アンケートやインタビューなどをもとに測定・評価します。
主な測定方法として、「キャントリルの梯子法」や「人生満足度尺度」を用いる方法が挙げられます。
キャントリルの梯子法とは、0から10まで番号が振られた梯子をイメージし、一番上を「最高の人生」、一番下を「最悪の人生」として、自分が現在どの段に立っていると感じるかを尋ねることで、人の幸せを測る方法です。国連の調査でも使われています。
人生満足度尺度とは、5つの質問に答えて、「1点:まったく当てはまらない」から「7点:非常によく当てはまる」までの7段階で得点を付ける測定方法です。その人が主観的に感じている幸福度を測ることができ、合計点が高いほど幸福度が高いことを表します。
客観的ウェルビーイングの指標
客観的ウェルビーイングとは、客観的な指標に基づいて算出したウェルビーイングです。
経済状況や教育水準などに関する指標を使って測定します。測定に用いる指標には、GDPや平均寿命、失業率や平均賃金、教育費などの指標が挙げられます。
客観的ウェルビーイングでは客観的な統計指標を使って数値化するため、国別や地域別にウェルビーイングの充実度の比較が可能です。
個人の主観が入り込んだり、一人一人の感じ方の違いによって結果が変わったりせず、客観的に評価可能である点が特長です。
ただし、近年は客観的ウェルビーイングよりも主観的ウェルビーイングが重視される傾向にあります。
理由は、統計指標が仮に優れた値を示していても、実際にはその国の人が幸福感を得られていないケースもあるからです。
実際に豊かさを実感できるかどうかが重要視されるようになり、それに伴い主観的ウェルビーイングへの注目が高まっています。
システムを活用した企業の改善事例多数
株式会社サンリオ、トヨタカローラ山形株式会社、株式会社GA technologiesなど、どのような効果が得られたのか分かる事例を公開中
ウェルビーイングを構成する要素
ウェルビーイングな状態を保つには、具体的にどのような要素を満たせばよいのでしょうか。
以下では、ウェルビーイングの構成要素を考えるうえで参考になる概念として、PERMAモデルとギャラップ社が提唱した概念を紹介します。
PERMAモデルによる5つの要素
PERMA(パーマ)モデルとは、以下の5つの要素を満たす人を幸せな人とするモデルです。アメリカの心理学者マーティン・セリグマン博士が提唱しました。
- Positive Emotion(ポジティブな感情)
- Engagement(何かへの没頭)
- Relationships(他者との関係性)
- Meaning(生きる意味)
- Accomplishment(達成)
嬉しい・楽しいなどポジティブで前向きになれる場合や、何かに没頭して夢中になれる場合、人は幸せを感じやすくなります。豊かな人間関係を築き、人との付き合いを楽しんでいるときも幸せな状態といえるでしょう。
また、生きる意味や目的を明確にして自覚しながら過ごすほうが幸福度が高まり、何かを成し遂げて達成感や充実感を得ることでも幸福度は高まります。
ギャラップの考える5つの要素
ギャラップ社の調査によれば、以下の5つの要素が満たされると、幸福感や充実感が得られるとされています。
- Career Wellbeing(キャリア)
- Social Wellbeing(社会)
- Financial Wellbeing(経済)
- Physical Wellbeing(身体)
- Community Wellbeing(地域)
幸福感や充実感を高めるには、自分の仕事にやりがいや目的意識を持つことができるか、社会の中で良好な人間関係を築けるかどうかが重要です。収入を確保して経済的な安定感・安心感を得られるかや、食事や運動、睡眠など健康面の要素も重要といえるでしょう。
また、地域のコミュニティとのつながりを感じ、自身が地域社会に貢献していると実感できることも、幸福感や充実感を高めるうえで重要です。
ウェルビーイングが注目される背景
ウェルビーイングは現在、日本でも世界でも注目されている概念です。以下では、ウェルビーイングが注目される背景を紹介します。
GDPのみでは測れない幸福度
かつては、国民の生活の豊かさを測る指標として、国に関する経済的な指標を用いる傾向にありました。
GNP(Gross National Product:国民総生産)やGDP(Gross Domestic Product:国内総生産)などの指標が代表的な指標です。
しかし、実際には、国全体として経済的に豊かだったとしても、国民一人一人が幸せを感じているとは限りません。
ものやサービスが多く生産されて国全体ではGDPが高い場合でも、国民の主観的な幸福感とは必ずしも一致しないからです。
そこで、物質的な豊かさではなく、実感として個々人が感じられる幸福度が注目されるようになりました。GDPなどでは測れない幸福度を測る方法として、主観的ウェルビーイングが注目されるようになりました。
SDGsへの意識の高まり
SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年に国連で採択されたもので、2030年までに達成すべき17の目標を定めた開発目標です。貧困や飢餓、環境などの問題を解決して、人類が安定して暮らし続けられるように定められました。
17の目標のうち、3番目の目標として掲げられているのが「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」です。
世界には、医療体制が不十分で、健康的な生活が困難な国や地域も多いため、すべての人の健康を保障することが重要視されています。
この目標の中でウェルビーイング(Well-Being)が使われており、SDGsへの意識が高まる中で、ウェルビーイング(Well-Being)の注目度も高まっています。
納得感のある評価を効率的に行うための仕組みを整備し、従業員の育成や定着率の向上に効果的な機能を多数搭載
・360°フィードバック
・1on1レポート/支援
・目標・評価管理
・従業員データベース など
企業がウェルビーイング経営に取り組むメリット
ウェルビーイングの概念を経営に取り入れる「ウェルビーイング経営」には、組織と従業員双方にとって多くのメリットがあります。
以下では、従業員が身体的・精神的・社会的に良好な状態になるように企業が取り組むメリットを紹介します。
生産性と業績への影響
従業員が身体的・精神的・社会的に良好な状態で働くことができれば、仕事をする際に能力を十分に発揮しやすくなります。
体調不良によってパフォーマンスが低下したり休んだりする従業員が減れば、企業の生産性や業績が安定・向上する点がメリットです。
イリノイ大学のエド・ディーナー博士の研究によれば、主観的ウェルビーイングが高い人は低い人よりもパフォーマンスがよいことが示されています。
売上は37%、生産性は31%、創造性は3倍に高まるという調査結果も報告されています。ウェルビーイングを高めることが企業業績に影響することがわかります。
企業のブランディング
ウェルビーイング経営によって従業員のウェルビーイングを重視すれば、企業として従業員の健康に配慮している姿勢を示すことができます。
働きやすい職場環境づくりを重視することで企業イメージがよくなる点も、ウェルビーイング経営のメリットのひとつです。
ブランディングによって企業イメージが向上すれば、自社の商品やサービスに対するイメージが向上して売上アップを期待できます。
企業がウェルビーイング経営を実践し、従業員が働きやすさや働きがいを感じられれば、口コミなどで伝わって企業イメージの向上につながるでしょう。
関連記事:企業の魅力を高めるエンプロイヤーブランディングとは?採用にもたらす効果やステップを解説
離職率の低下と採用率の改善
従業員のウェルビーイングを重視し、職場におけるストレスを減らして働きやすい職場環境を整えれば、従業員の満足度が向上します。
従業員が働きやすいと感じれば離職率の低下につながりし、優秀な人材の流出を防ぐことができます。
離職率が高い場合は、その都度の採用活動や育成に時間とコストがかかります。一方、離職率が低下すれば、それらの負担を抑えられます。
また、働きやすい職場環境づくりや従業員のワークライフバランスを重視すれば、企業イメージが向上して採用率アップも期待できます。採用の募集を行ったときに優秀な人材が応募してくれる可能性も高まり、生産性向上も期待できるでしょう。
関連:
ワーク・ライフ・バランスとは? 使い方や例文、企業の取り組み事例を簡単に解説
従業員のモチベーション向上
従業員が職場で良好な人間関係を築き、働きやすさや働きがいを感じられれば、仕事をする際のモチベーションアップにつながります。
従業員のモチベーションは労働生産性に影響する点で、企業の事業経営において重要な事項のひとつです。従業員のモチベーションを向上させる方法のひとつとして、従業員のウェルビーイングを重視した経営手法が役立ちます。
従業員が日頃から高いモチベーションで業務に臨める雰囲気が社内で醸成されれば、意識の高さが従業員間で互いによい影響を与え合い、モチベーションや生産性がさらに向上する好循環を生み出せるでしょう。
ウェルビーイング経営の具体例
企業が実際にウェルビーイング経営を実践する場合、さまざまな手法があります。以下では、ウェルビーイング経営を実践するための代表的な5つの手法を紹介します。
労働環境の改善
残業時間を減らすなど、労働環境が改善されれば従業員のストレスが軽減されます。
長時間労働が常態化している場合や有給の取得率が低い場合は、業務を見直して課題を特定し、労働環境の改善につなげましょう。
深夜残業や休日出勤を減らすことは、従業員の疲労やストレスの軽減につながり、健康的に働ける環境が整えば、従業員は能力を十分に発揮しやすくなります。
また、労働災害の発生件数が多い場合は、労働災害防止のための取り組みを強化することが重要です。労働災害が起きず安心して働ける職場であれば、従業員は不安やストレスを感じずに働くことができます。
健康支援
従業員が健康的で心身ともに健やかな状態で働けるようにするうえで、健康面で企業が支援を行うこともウェルビーイング経営では重要です。
例えば、健康診断の費用だけでなく、予防接種やがん検診の費用を会社で負担する方法が挙げられます。
また、悩みを抱えている従業員がいた場合にすぐに把握して必要なサポートを行えるように、ストレスチェックを実施してもよいでしょう。
個別面談の実施や産業医との面談の設定を早期に行えば、従業員がストレスが蓄積し体調を崩す事態を回避できます。
関連記事:健康経営とは?企業の取り組み事例、効果的な施策、メリットを解説
福利厚生の充実
福利厚生を充実させることも、従業員の満足度向上やウェルビーイング達成を実現するうえで有効な方法のひとつです。
例えば、住宅手当や通勤手当、家族手当など各種手当を充実させれば、従業員満足度の向上を通じて、ウェルビーイングの実現にもつながります。
また、アニバーサリー休暇やボランティア休暇などの特別休暇制度を設ける方法も、従業員のワークライフバランスを充実させることにつながります。
福利厚生の一環として新たな制度を導入する場合は、まずは自社で導入できる制度にどのようなものがあるか確認してみましょう。
従業員にアンケートを通じて従業員のニーズを把握し、それに基づいた制度設計を行うことで、より納得感のある施策につなげられます。
関連:従業員満足度調査(ES)とは? アンケート項目や具体的な向上施策をわかりやすく解説
心理的安全性の確保
職場の人間関係や雰囲気が悪い場合、従業員はストレスを感じたり働く意欲が低下したりして、労働生産性が低下する可能性があります。
これは従業員のウェルビーイングとはほど遠い状態です。
職場環境に問題があって従業員に心理的負担がかかっているケースでは、心理的安全性を確保するための取り組みを行いましょう。
職場の雰囲気を改善して風通しをよくし、社内のコミュニケーションを活性化して楽しい職場環境を整えれば、従業員はストレスを感じずに働くことができます。コミュニケーション促進策としては、休憩・談笑用のスペースの設置や懇親会費用の補助などが挙げられます。
関連:職場の心理的安全性とは?作り方や4つの因子、高める方法を解説
従業員サーベイの実施
従業員にサーベイを実施すれば、従業員の状況や不満を把握できます。
自社はどのような問題を抱えているのか、問題点を洗い出して改善策の考案をする場合には従業員サーベイが役立ちます。
従業員がウェルビーイングな状態を保てるようにするためには、従業員の意見に直接耳を傾けて意見を取り入れることが重要です。従業員に対するヒアリングを実施せず経営層だけで決めてしまうと、従業員の希望に応えられず適切な解決策を講じられない場合があります。
従業員サーベイに基づいて適切な解決策を実行し、従業員の不満や不安を解消することが、労働生産性の向上や会社全体での質の高い経営につながります。
関連:従業員サーベイとは?意味や目的からメリットや実施時の注意点まで徹底解説
ウェルビーイング経営の企業事例
ウェルビーイング経営はさまざまな企業で実践されています。ここでは、ウェルビーイング経営を先進的に実践している3社の取り組み事例を紹介します。
パナソニックグループ
パナソニックグループでは人事戦略のひとつとして、社員のウェルビーイング実現へ向けた取り組みを実践しています。
パナソニックグループのウェルビーイング経営は、「安全・安心・健康な職場づくり」「Diversity, Equity & Inclusionの推進」「自発的な挑戦意欲と自立したキャリア形成の支援」の3つを柱としています。
エクササイズの促進などによって健康リスクの低減を図り、社員の自発的なコミュニティ活動の活性化などの取り組みを行っています。
リモートワークや社外副業など働く時間・場所の選択肢を拡大することで、従業員一人一人が自分らしい働き方を選択できるようになっています。
楽天グループ株式会社
楽天グループ株式会社では、楽天健康宣言「Well-being First 」のもと、さまざまな取り組みを行っています。
Body(健康的な体)・Mind(健康的な心)・Social(健康的な社会とのつながり)を促進するための取り組みを行い、健康的に働き続けられる従業員・組織風土づくりの実現を目指している点が特徴です。
毎年ストレスチェックを実施するほか、「ウェルビーイングサーベイ(調査)」を定期的に行い、従業員の心身の状態を可視化しています。
長時間労働者や管理職への注意喚起、年次有給休暇の計画的な取得促進なども行っています。定例ワークショップや社内研修、ゲスト講演などを通じて、マインドフルネスに対する従業員の知識や理解を深め、実践できる環境を提供しています。
P&Gジャパン合同会社
P&Gジャパン合同会社では、社員が最大限の能力を発揮できるように社員のウェルビーイングを重視しています。ウェルビーイング経営宣言のもと、社員一人一人の自律した健康管理を積極的に支援している会社です。
社員とその家族の健康の保持・増進、ワーク・ライフ・バランスの実現、生産性の向上、多様な社員が活躍できる職場づくりを総合的に推進しています。
経営層や人事統括部門、健康管理部門が中心となって、健康保健組合や各職場と協力しながら社員やその家族の健康増進やメンタルヘルスケアなどに取り組んでいます。
これからのウェルビーイング経営の展望
ウェルビーイング経営は今後、新たな形で発展していく可能性があります。以下では、これからのウェルビーイング経営の展望について紹介します。
デジタルウェルビーイングの進化
デジタル技術の進展によって生活は大きく便利になった一方で、長時間のスマートフォン使用による眼精疲労や、夜間の使用による睡眠の質の低下など、新たな健康リスクも生じています。
デジタル技術が普及した現代社会において、ウェルビーイング実現のためにはデジタル技術との向き合い方も重要になるポイントのひとつです。ゲームやインターネットに過度に依存すると、依存症になって心身の不調につながる場合や、社会的なつながりが希薄になる場合があります。
身体的・精神的・社会的に良好な状態を保つためには、スマホやパソコン、ゲームなどに過度に依存しすぎず、デジタル技術とうまく付き合うことが求められます。ブルーライト対策やデジタルデトックスなど、適切な対策を講じることが重要です。
また、デジタル技術は、うまく活用すればウェルビーイングを実現するうえで役立ちます。
一方で、AIやビッグデータは、企業が従業員の状態を可視化・分析するうえで有効です。個人レベルでも、ウェアラブルデバイスやヘルスケアアプリを通じて、健康の維持・増進が可能になります。
ポストSDGsとしてのウェルビーイング
SDGs(持続可能な開発目標)は2030年の達成を目指して設定された国際目標ですが、その期限が近づく中、次なる枠組みとして「ポストSDGs」が議論され始めています。
その中で注目されているのが、「SWGs(Sustainable Well-being Goals)」と呼ばれる新たな概念です。これは、経済成長や開発だけでなく、人々の幸福や心身の健康、社会的つながりといった側面に焦点を当て、持続可能な形でのウェルビーイング実現を目指すものです。
今後は、物質的な豊かさだけでなく、精神的・社会的な幸福を含めた「総合的な豊かさ」をどう実現するかが、企業・国家・個人すべてにおいて問われることになるでしょう。
まとめ
SDGsへの意識の高まりを背景に、「身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること」であるウェルビーイングは、今後ますます重要な概念として注目されるでしょう。
ウェルビーイングには主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイングの2種類あり、GDPのみでは測れない幸福度を測定できます。
ウェルビーイングの考え方は企業経営においても活用が可能です。企業がウェルビーイング経営を実践すれば、従業員のモチベーション向上や労働生産性アップ、離職率低下などの効果を期待できます。
実際にウェルビーイング経営を推進する際の方法は、従業員サーベイの実施や労働環境の改善、福利厚生の充実など、企業ごとにさまざまです。
ウェルビーイング経営を行っている他社の事例を参考にしつつ、自社の状況に即した施策を選び、段階的に実行していくことが大切です。
HRMOSタレントマネジメントで適切な人材管理を推進
企業が事業活動を行ううえでは、社員のモチベーションや能力、成果を正しく把握することが重要です。社員のウェルビーイング実現やモチベーションアップのためには、人材管理を適切に行う必要があります。
個々の社員の状況を的確に把握し、人材管理・人材育成を行うのであれば、タレントマネジメントシステムの活用が効果的です。
HRMOSタレントマネジメントでは、サーベイを通じて社員一人一人のモチベーションの変化を可視化できます。これにより、現状に即した的確なサポートを提供することが可能になります。
HRMOSのスキル管理機能について、詳しくはこちらをご覧ください。