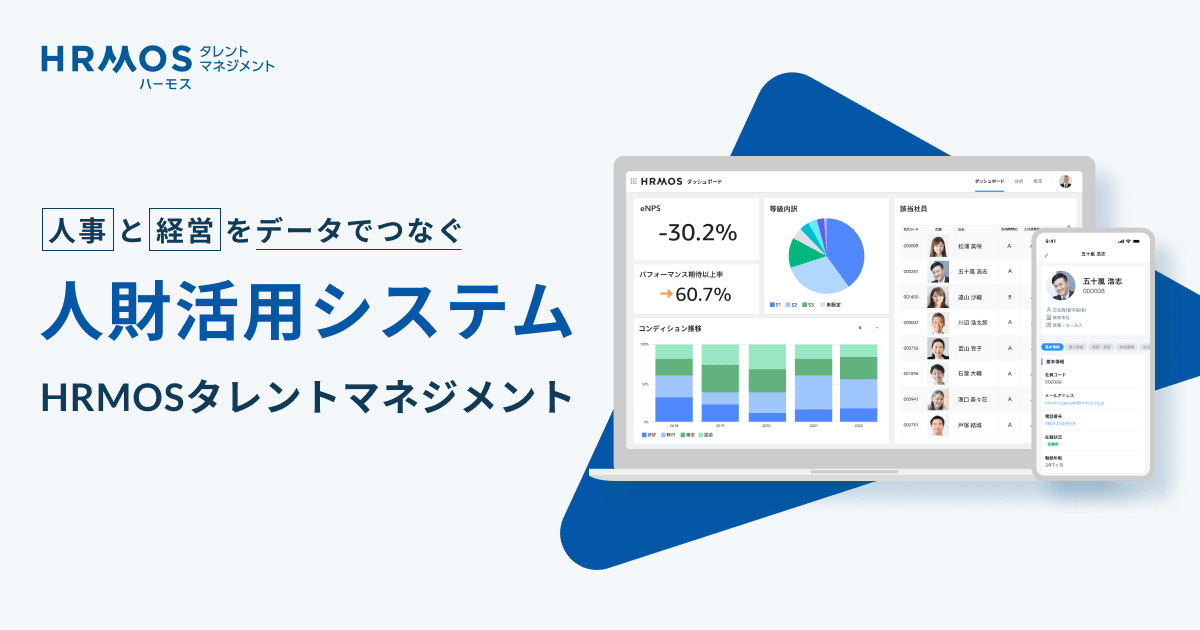目次
組織が変革を進める際には、混乱や反発がつきものです。こうした変化をスムーズに推進するために欠かせないのが「チェンジマネジメント」です。
チェンジマネジメントを計画的に実行しながら変革を進めれば、混乱や抵抗感を減らすことができ、関係者の理解と協力を得やすくなります。
本記事では、チェンジマネジメントとは何か、定義や重要性、代表的なフレームワークや事例、成功するためのポイントを解説します。
チェンジマネジメントの定義と重要性
時代の変化にあわせて企業にも変化や成長が求められる中、変革を進める際のマネジメントの重要性が高まっています。まずは、チェンジマネジメントの定義や現代ビジネス環境における必要性について解説します。
チェンジマネジメントの概念と目的
チェンジマネジメントとは、組織が変化する際、期待される成長や進化を実現するため、関係者が変化に適応できるよう支援するマネジメント手法です。
チェンジマネジメントにより混乱や抵抗を抑えることで、移行を円滑に進められます。さらに、組織全体を見渡して計画的なマネジメントを実施し、変化後に必要なスキルや価値観の導入をサポートします。
急激な変化は、関係者からの抵抗や組織内での混乱・軋轢を引き起こす要因となります。
しかし、チェンジマネジメントによって変革を計画的に進めれば、混乱や抵抗感が減って関係者は変化を受け入れやすくなります。
チェンジマネジメントは、組織として変化への対応力を高めるためのマネジメント手法といえるでしょう。
現代ビジネス環境におけるチェンジマネジメントの必要性
現代は変化が激しい時代です。企業が市場競争を勝ち抜いて生き残るには、環境変化に応じて企業も変革し、成長し続けることが求められます。
新技術の導入や市場トレンドの変化に対応し、柔軟に経営方針を見直すことが、現代ビジネスにおける重要な要件となっています。
変革が必要なタイミングにおいて、組織内部の変更をスムーズに行えるだけの対応力が求められます。
しかし、計画性なく組織の変革を進めようとすると、組織内で混乱が起きることがあります。変革に余計な時間や労力がかかり、時代の変化に取り残されることになりかねません。
混乱や抵抗を減らし、変革を滞りなく行ううえで重要なのがチェンジマネジメントです。チェンジマネジメントによって円滑な組織の変革が可能になります。
チェンジモンスターによる変革への抵抗
組織が変革を進めて新しい技術や価値観、働き方を導入する際、重要なポイントの一つが、変化に抵抗する勢力や要因への対応です。
チェンジモンスターとは、変革を妨害する人間の感情的・心理的な要因の総称のことです。変化や変革を推し進めるときには、一般的にチェンジモンスターが少なからず発生します。
現在の業務のやり方や自身の業務範囲を変えたくないなど、変化を拒んで抵抗したりかき乱したりする人が出るようなケースです。
チェンジモンスターの存在によって、変革の進行が遅れたり、期待通りの成果が得られなかったりする可能性があるため、注意が必要です。
変革に反対する従業員がいれば意見を聞いて変化に伴う懸念や不安を払拭するなど、組織変革を行う際はチェンジモンスターに適切に対処しましょう。
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
チェンジマネジメントの3つのレベル
チェンジマネジメントは、アプローチの対象に応じて「個人」「プロジェクト」「組織」の3つのレベルに分類されます。
個人レベルでのアプローチ
個人レベルで行うアプローチは、従業員一人一人に対して行うマネジメントやサポートのことです。
組織の変革に応じて、各従業員に求められる対応や変化を把握し、変化に対応できるようにサポートします。
個人レベルでサポートを実施すれば、従業員の適応力が高まることで、組織全体としての変革も円滑に進みます。また、変革に伴う従業員の負担や抵抗感を減らすことにもつながります。
変革を行う意義や必要な対応事項などを個別に説明すれば変革の必要性への理解が進み、従業員から協力を得やすくなるでしょう。
プロジェクトレベルでの取り組み
組織の変化に伴ってチェンジマネジメントを行う場合、複数の従業員が集まるプロジェクト単位でマネジメントを行うこともできます。
組織の変革にあわせて変革が必要なプロジェクトは何か、どのような変更が必要か、プロジェクト単位で行うアプローチです。
過去の類似プロジェクトを参考に人選や進行方法を決めることもありますが、過去の成功事例がそのまま適用できるとは限りません。
プロジェクトレベルで必要な変化を把握してチェンジマネジメントを行うことで、企業全体にも好影響をもたらします。
組織全体での変革
組織全体に対して行うチェンジマネジメントは、全社的な視点で変革を支援する取り組みです。
変革を進める際、個人レベルやプロジェクトレベルのような個別単位でのマネジメントも重要です。同時に、組織全体で変革が円滑に進むよう、全社的なマネジメントも欠かせません。
組織図の変更など、変革に際して組織全体として必要な対応があれば実行し、個々の従業員や部署ごとの変革の進捗度合いを組織全体で共有します。
変革の目的や必要な対応を全社で共有することで、取り組みの一体感が生まれ、スムーズな実行につながります。
<関連記事>
組織変革とは?企業の成功に欠かせないフレームワークとプロセスの重要性
チェンジマネジメントの代表的なフレームワーク
チェンジマネジメントを行う際のフレームワークにはさまざまなものがあります。以下では、代表的なフレームワークを6つ紹介します。
レヴィンの3段階変革モデル
3段階変革モデルは、ドイツの社会心理学者クルト・レヴィンが提唱したモデルです。
組織変革では以下の3つのプロセスが必要であり、各フェーズに応じた対応を取ることで、変革を効果的に進められます。
- 第1段階:解凍(Unfreezing)
- 第2段階:変革(Changing)
- 第3段階:再凍結(Refreezing)
最初の第1段階(解凍)では現状分析を行い、業務プロセスの見直しや変革の必要性を関係者に認識させます。第2段階(変革)は、新しいツールや方法、考え方を導入して実際に変革を進める段階です。社内で説明会や研修を実施して新たな作業工程に慣れてもらい、実行とフィードバック、改善を繰り返します。
最後の第3段階(再凍結)では、新たな価値観や行動、プロセスが日常的で当たり前のものとなるように、組織内で定着させます。
キューブラー・ロスのチェンジカーブ
チェンジカーブは、精神科医のキューブラー・ロスが「悲しみを受け入れるプロセス」として提唱したモデルです。
終末期患者の心理プロセスの分析がもとになっていますが、現在では組織変化に伴う関係者の心理変化を理解してチェンジマネジメントを実行する際にも活用されています。
チェンジカーブは、人々の心理変化を以下の段階に分けて考える点が特徴です。
前述したとおり、「チェンジモンスター」への対応は変革成功の鍵となります。
人々の心理変化に応じて対応することで、変革の必要性を関係者に理解してもらい抵抗感を和らげ、協力を得て組織の変革を円滑に進めることができます。
- 否定:変わらなければいけないという事実を否定する
- 怒り:変わらなければいけないことに対して怒りを感じる
- 抵抗:変化を何とか回避できないか抵抗する
- 落ち込み:変化が避けられないと知り、喪失感や無力感を覚えて落ち込む
- 受け入れ:変化や新しい現実を受け入れ始める
- 試み:新しい状態で何ができるのか、試みて探索する
- 発見:新しい状態での喜びや楽しみを見つける
- 統合:新しい状態への変化を受け入れ、変化を日常に取り込む
ブリッジズのトランジション理論
トランジション理論は、アメリカの心理学者ウィリアム・ブリッジスが提唱した理論です。トランジション(transition)は英語で転機や転換点を意味します。
トランジション理論では変化のプロセスを以下の3つに分けて考えます。各フェーズにおける人の心理状態に応じて対応することで変化を乗り越えられます。
- 第1段階:終焉(何かが終わるとき)
- 第2段階:中立圏(ニュートラル・ゾーン)
- 第3段階:開始(何かが始まるとき)
変化が起きる場合、まずは第1段階として現在の状況が終わることになるため、混乱や虚無感が生じます。
その次の第2段階は虚無感や喪失感と向き合う時期です。これまでの自分の状況が終わったことは理解したものの、新しい自分にもなりきれておらず、自分のアイデンティティを再構築する過渡期にあたります。
自身が置かれている現状に向き合うことで、変化が求められていることの意義を理解し、新たな気付きを得られます。
最後の第3段階は、状況を整理して新たな状況に適応できるように動き出す時期です。
ADKARモデル
ADKARモデルは、米国Prosci社の創業者ジェフリー・ハイアットが提唱した組織変革モデルです。
組織変革のステップとして「認知(Awareness)」「願望(Desire)」「知識(Knowledge)」「能力(Ability)」「強化(Reinforcement)」の5つを挙げ、頭文字を取って「ADKARモデル」と呼ばれています。
- 認知(Awareness):従業員に変革の必要性や内容を認識させる
- 願望(Desire):変革に主体的に取り組みたい意欲を醸成する
- 知識(Knowledge):変革を実践するうえで必要な知識を習得させる
- 能力(Ability):得た知識を実際に活用して変革を実行する
- 強化(Reinforcement):新しい方法を強化して変革を定着させる
変革の意義や内容を従業員に説明することで従業員は変革の必要性を理解し、自発的な関与や協力姿勢が育まれます。
その後、変革を進めるうえで必要な知識やスキルを身につけ、実際に行動に移して変革を実行します。
そして、組織の変革は一度実行すれば終わるわけではありません。元の状態に戻らないように変化後の状態を定着させるため、継続的に取り組むことが重要です。
コッターの変革を導く8ステップ
「変革を導く8つのステップ(The 8-Step Process for Leading Change)」は、ハーバード・ビジネス・スクールの名誉教授ジョン・コッターが提唱した組織変革モデルです。
「変革を導く8つのステップ」では、組織変革に必要なプロセスとして以下の8つの段階を挙げています。
- 危機意識を高める
- 変革を推進するためのチームを結成する
- 変革のためのビジョンを策定する
- ビジョンを伝達して共有する
- 従業員がビジョンを実現できるようにサポートする
- 短期的な成果を出すために計画を策定して実行する
- 改善成果を定着させて変革をさらに推し進める
- 変化後の状態を組織の文化として根付かせる
各ステップを段階的に実行することで、変革への理解が深まり、実行に移しやすくなります。
マッキンゼーの7S
マッキンゼーの7Sは、7つの経営資源に着目して現状分析や組織の戦略立案を行うフレームワークです。ハードな経営資源とソフトな経営資源の両面から分析することで、課題点を洗い出して改善策を導き出せます。
- Strategy:戦略
- Structure:組織構造
- Systems:システム
- Staff:人材
- Style:経営スタイル/組織風土
- Skills:スキル
- Shared Values:共通の価値観
ハード面の3つのS(戦略・組織構造・システム)に着目することで、組織の仕組みの特徴を把握・分析でき、改善の方向性を見出せます。
集権的か分権的か、部署・部門はどのように分かれているかなど、組織構造の特徴を分析し、意思決定のプロセスや人事・会計システムなど社内システムの特徴を分析します。
ソフト面の4つのS(人材・経営スタイル/組織風土・スキル・共通の価値観)からは、社風や共有されている価値観、企業の強みといえるスキル、従業員の特徴などを分析できます。
チェンジマネジメントを成功に導くためのポイント
チェンジマネジメントを行う際はポイントをおさえて実践することが重要です。以下では、チェンジマネジメントを成功に導くための3つのポイントを紹介します。
リーダーシップとコミュニケーションの重要性
チェンジマネジメントを実践して組織の変革を進めるためには、変革を推進できるリーダーの存在が欠かせません。
変革を成功させるためには、経営層やマネジメント層がリーダーシップを発揮して、全社を巻き込んで進める必要があります。
リーダーが変革への姿勢を示し、現場に足を運んで関係者に必要性を説明し、意見を聞きながら進めることが重要です。
意思疎通を図ることで組織の一体感が生まれ、変革に向けて一致団結した体制を築けます。
<関連記事>
リーダーシップスキルとは?リーダーに必要なスキルの種類とスキルを向上させる方法を紹介
データに基づいた意思決定と進捗管理
組織変革を進める際には、データに基づいて客観的に意思決定や進捗管理を行うことが重要です。
リーダーが主観的な判断で根拠なく変革を進めると、方針がぶれて混乱を招くことがあります。周囲の理解を得られず、反発を招くおそれもあります。
組織目標の設定や変化の状況を把握・評価できるツールを導入すれば、データに基づくチェンジマネジメントが可能になります。
組織変革では、変革ビジョンマップや企業診断キットなどを活用することで、効果的に進められます。
<関連記事>
従業員エンゲージメントの向上と維持
組織変革を成功させるためには、従業員が変革の必要性を理解し、積極的に変革に協力したいと思える環境を整えることが重要です。
従業員エンゲージメントとは、従業員が企業に対して抱く愛着や帰属意識のことです。
従業員エンゲージメントが高まるほど、従業員は組織に貢献したいと考え、変革にも積極的に関与します。
たとえば、適切な人事評価制度を整備することで、従業員の納得感や公平感を高め、エンゲージメント向上につなげることができます。
また、社内のコミュニケーションを活性化させ、組織への帰属意識を高めることも効果的です。
<関連記事>
チェンジマネジメントの資格
チェンジマネジメントの知識やスキルを身につけたい場合は、関連資格の学習を通じて体系的に習得する方法もあります。
代表的な資格としては、Prosci®が提供する「チェンジマネジメント資格認定プログラム」があります。
資格認定プログラムでは、変革の取り組みを成功させるための知識やスキル、ツールが提供されます。
新規プロジェクトの推進時や、変革に対する抵抗への対応、組織・個人の変革力を高めたい場合などに有効なプログラムです。
納得感のある評価を効率的に行うための仕組みを整備し、従業員の育成や定着率の向上に効果的な機能を多数搭載
・360°フィードバック
・1on1レポート/支援
・目標・評価管理
・従業員データベース など
チェンジマネジメントの実践事例
富士フイルム株式会社
イメージング、ヘルスケア、エレクトロニクス事業を展開する富士フイルムは、長期計画「SVP2030」で「社会へ変革を促す企業」を掲げ、チェンジマネジメントを全社的に推進すると発表しました。
マネージャー層の育成を軸に、現場で変革課題を設定・実行・学習を繰り返す仕組みを強化しています。
さらに「Work Style Innovation」により、多様な働き方と成果創出を両立する制度・風土を整備しました。
自社の働き方変革と、顧客のDX支援に一体となって取り組み、変革を仕組み化・定着させている点が特長です。
株式会社良品計画
「無印良品」を国内外で展開する良品計画は、統合報告(MUJI REPORT)で、事業の再成長に向けた「変革の道筋」を明確化しました。
生産機能の再構築や一元管理、サプライチェーン全体の効率化を目的としたオペレーション変革、人材採用・育成の強化を同時並行で進めています。
商品開発や人材育成などの業務プロセスを全社で横断的に改善し、短期的な施策で終わらせず、中期視点での定着を重視するチェンジマネジメントが特徴です。
日本マクドナルド株式会社
国内最大級のハンバーガーチェーンを運営する日本マクドナルドは、DE&I(Diversity, Equity & Inclusion)を中核に「オープンな組織づくり」を推進している企業です。
トップマネジメントがスポンサーを務める「オープンドア!チーム」を設置し、現場からの声を政策・制度に反映する仕組みを整備しています。加えて、健康経営の面ではテレワークやスーパーフレックス制度など、働き方変革を拡充させました。
制度の見直しと時代の変革にそった人材育成を両軸で進め、行動変容を継続的に促すチェンジマネジメントを展開しています。
チェンジマネジメントに関するおすすめの本
チェンジマネジメントの理解を深めるうえで役立つ書籍が多数出版されています。以下では、チェンジマネジメントに関するおすすめの本を3つ紹介します。
企業変革力
「企業変革力(Leading Change)」は、チェンジマネジメントの代表的なフレームワーク「変革を導く8つのステップ」を提唱したジョン・P・コッターの著作です。
企業の変革で必要なリーダーシップやリーダーに求められる役割を論じています。
企業が変革するときに踏むべきステップ、陥りやすい失敗例など、組織変革に携わるリーダー向けの実践的内容がまとめられています。
実践 チェンジマネジメント
「実践 チェンジマネジメント」はチェンジマネジメントの実践方法を解説した書籍です。
現代における変革の意味やチェンジマネジメントを実践するときのポイントなどを扱っています。
チェンジマネジメントのポイントを変革フェーズごとに整理し、組織づくりにおける重要事項を具体的に示しています。企業の変革プロジェクトにおけるチェンジマネジメントの実際の事例を用いながら、変革の成功要因などを紹介しています。
チェンジ・リーダーの条件
「チェンジ・リーダーの条件」はマネジメントを体系化したピーター・ドラッカーの著作です。マネジメントとは何か、定義や役割から始まり、マネジメントを行う際の具体的なポイントまで解説しています。
現代社会におけるマネジメントの重要性を説き、基礎知識として、対象範囲の捉え方や目標・方向性の設定方法などを論じています。
まとめ
変革をスムーズに進めるためには、個人レベルやプロジェクトレベル、組織全体でチェンジマネジメントを行うことが重要です。適切なマネジメントによって、組織の変革に伴う混乱や反発を減らすことができます。
チェンジマネジメントを実践する際は、レヴィンの3段階変革モデルなどの代表的なフレームワークを活用するのが効果的です。
組織の変革を成功させるためには、経営層やマネジメント層がリーダーシップを発揮し、データに基づいて意思決定や進捗管理を行うことが大切です。現場の不安や反発を減らせるように、従業員とのコミュニケーションを大切にしながら組織の変革を進めましょう。
HRMOSタレントマネジメントで適切な人材管理を推進
企業が変革を通じて組織をより良くするには、従業員の能力や成果などの現状を正確に把握・分析し、課題を特定して改善策を立案する必要があります。
正確な現状把握と分析を行うためには、人材の最新情報の管理をしていることが重要です。
適切な人材データ管理をするうえで、タレントマネジメントシステムの活用が有効です。変革に伴う新しい業務や役割に必要なスキルを可視化できます。
HRMOSタレントマネジメントでは従業員のスキルを可視化し、客観的かつ適切に数値化できます。それにより、適切な人材配置や従業員の現状にあわせた人材育成が可能です。
HRMOSのスキル管理機能について、詳しくはこちらをご覧ください。