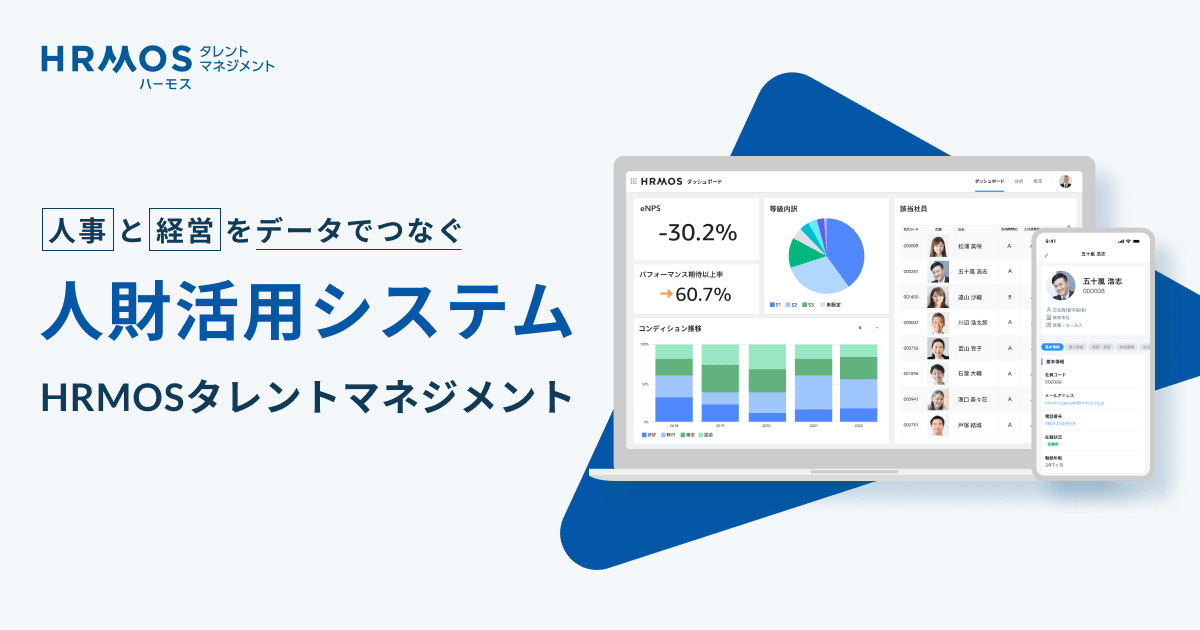目次
フィードバックにはさまざまな意味がありますが、ビジネスにおいても従業員や組織の成長を目指し、フィードバックは活用されています。
しかし、適切なフィードバックを実施できなければ、効果を十分に得ることはできません。そのためには、業種や職務、従業員との関係性などに合わせ、最も効果を発揮しやすいフィードバックの手法を選択することが大切です。また、フィードバックを成功させるためには注意しなければならない点もあります。
今回は、フィードバックの意味やビジネスに生かせるフィードバックの手法、実施時の注意点などについてご説明します。
フィードバックの意味とは
フィードバックとはどのような意味を持つのでしょうか。ビジネス上で使用される際の意味を中心にご説明します。
ビジネスにおけるフィードバック
ビジネスにおけるフィードバックとは、仕事上のある行動の結果について、その評価や改善すべき点を伝える行為を指します。一般的には上司から部下、マネージャーからメンバーに対し、1対1で向き合い、フィードバックするケースが多くなります。
フィードバックは、よくできた点を伝えてモチベーションを高めるとともに、課題が残る点を指摘して軌道修正を図り、部下の成長を促すものです。
また、フィードバックには双方向のコミュニケーションを促す効果もあり、互いの意見や考えを知るよい機会ともなります。
フィードバックを実施する機会が多いのは、プロジェクトの進行段階でこれまでを振り返るタイミングやプロジェクトの完了後、人事評価を伝える際、定期的な面談の際などです。
フィードバックの言い換え
フィードバックは英語にすると「Feedback」であり、「反応」「意見」「帰還」などを意味する言葉です。
したがって、フィードバックを言い換える際にも、これらの言葉を用いることができるでしょう。また、ビジネス上では「振り返り」や「評価」などへの言い換えも可能です。
フィードバックに似た言葉には、「フィードアップ」や「フィードフォワード」があります。フィードアップは、目的や目標のすりあわせをすること、フィードフォワードは未来の行動に対するアドバイスを指す言葉です。
フィードバックの本来の意味
一般的にフィードバックとは、物事への反応や結果を見て改良・調整することをいいます。また、利用者などからの意見や評価を指す場合もあれば、そのような意見や評価を関係者に伝える行為をフィードバックと呼ぶ場合もあります。
フィードバックは、本来は制御工学や通信工学で用いられていた用語です。
電気回路などのシステムで、出力した結果を入力に加えることで影響を与えることを指し、帰還とも呼ばれます。
システムを活用した企業の改善事例多数
株式会社サンリオ、トヨタカローラ山形株式会社、株式会社GA technologiesなど、どのような効果が得られたのか分かる事例を公開中
フィードバックの種類と特徴
フィードバックには「ポジティブフィードバック」と「ネガティブフィードバック」の2つの種類があります。
ポジティブフィードバックの特徴と影響
ポジティブフィードバックとは、前向きな言葉で、相手を肯定するようなフィードバックのことです。よくできていたこと、よかった点などを褒めることで部下の承認欲求を満たし、仕事に対するモチベーションをアップさせることができます。
ポジティブフィードバックの具体例は次のようなものです。
例1:「グラフや表もあり、時系列のデータも加えられていたから、資料がわかりやすかったよ。これからも見る人の視点に立ったわかりやすい資料作りを継続してほしい」
例2:「君ならきっと目標数値を達成できると信じていたが、私の想像以上によい成績を収めたね。これからも今回のように、ニーズに沿った提案をして、お客様に喜んでもらえるような営業活動を進めてください」
前向きな言葉をもらうことで相手は自分を認めてもらえたと感じ、自己効力感も高まるため、業務にも意欲的に取り組めるようになるでしょう。その結果、生産性の向上と従業員の自発的な成長が見込めます。
<関連記事>自己効力感とは?意味や高める方法、自己肯定感との違いを簡単に解説
ネガティブフィードバックの特徴と注意点
ネガティブフィードバックとは、問題点や課題を指摘し、改善を促すフィードバックです。
相手に客観的な視点で問題点を伝えることで、従業員が自発的に改善策を考えられるように促す目的があります。
ただし、ネガティブフィードバックは否定的な意見を伝えるため、従業員にストレスを与え、モチベーションを低下させてしまうリスクがあります。
ネガティブフィードバックをする際には、相手の存在や価値を否定するのではなく、改善すべき点だけにフォーカスして言葉を選びながら慎重に伝えることが大切です。また、フィードバック後のフォローも忘れないようにしましょう。
ネガティブフィードバックの例としては、次のような伝え方が考えられます。
「作ってもらった資料を確認したけど、一般的なサービス説明という印象だったね。これでは、クライアントには導入のメリットが伝わらないかもしれない。もっとクライアントをリサーチしたうえで、クライアント目線での資料に作り直してください。君ならできると思うよ」
フィードバックがもたらす効果
ビジネスシーンにおいてフィードバックを実践すると、次のような効果が期待できます。
パフォーマンス向上への貢献
フィードバックによって従業員の課題や問題点を客観的に指摘すると、従業員は自らの行動を振り返り、正しい方向に向けて努力できるようになります。
特に、目標達成に向けて努力してはいるものの成果が出ていない場合などは、フィードバック時の上司の意見が大きな影響を与える可能性があります。
従業員が自ら課題改善のために取り組み、業務効率などを改善すればパフォーマンスが向上するでしょう。
また、フィードバック時にはできていることを認めると、自分に自信が持てるようになるため、モチベーションが向上し、意欲的に業務に取り組めるようになります。
モチベーションとエンゲージメントの向上
ポジティブフィードバックによって、自分の成果や能力が認められると、モチベーションが高まり、自信を持って業務に取り組めるようになります。
また、ネガティブフィードバックであっても、上司からの指摘によって課題が明確になれば、自分で改善策を講じられるようになるでしょう。自分の力で課題を克服し、パフォーマンスを向上させれば業務に対する自信となり、モチベーションが高まります。
モチベーションが高くなれば、会社に対するエンゲージメントも高まり、組織全体の生産性も向上することにつながります。
スキルアップと成長の促進
定期的にフィードバックを行い、よい点を褒め、課題を指摘することは、従業員のスキルアップや成長を促します。日々の業務に真剣に向き合い、目標達成のために突き進んでいる場合、自分を客観的に省みる余裕がなくなってしまう従業員も少なくありません。
そのような場合でも、フィードバックをすると上司からの客観的な意見を知ることができ、部下も自分に不足している点や自分の強みを把握しやすくなり、自己成長につなげることができます。
また、上司も部下の成長度合いを確認しながら、必要な研修を提案したり、任せる業務の範囲を広げたりするなどして、成長を促進する取り組みを実施できるようになるでしょう。
信頼関係の構築
フィードバックを重ねると上司と部下のコミュニケーションが活発化するため、互いをよく理解できるようになります。
フィードバックを行うためには、上司は部下の残した結果のみではなく、日頃の業務の進め方も見る必要があります。部下は上司からフィードバックを受けることで、上司が自分をしっかり見守っていることに気付き、自分に対する期待を感じることもできるでしょう。
また、コミュニケーションの機会が増えることで、悩んだときや行き詰まったときにも上司に相談しやすくなり、関係性が強化され、信頼関係を築くことができます。上司と部下の間で良好な関係を築ければ、組織の雰囲気もよくなり、高いモチベーションを維持して業務に臨めるようになります。
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
効果的なフィードバックの手法
フィードバックには、いくつかの手法があります。ここでは代表的なフィードバックの手法を5つご紹介します。
FEED型
FEED型のフィードバックとは、「Fact(事実)」「Example(具体例)」「Effect(影響)」「Different(変更点・改善点)」の4つのステップに基づき、順に進めるフィードバックのことです。
事実とは部下の行動であり、事実をもとに、部下の行動に対して指摘をする理由を説明します。この説明が具体例に該当します。
次に、影響は部下がその行動をしたことでどのような影響が生じたかについて示し、最後に、変更点・改善点として、ほかにどのような行動ができるのかの提案をします。
FEED型は、行動から改善策までを流れに沿って説明するものであり、相手も理解しやすいというメリットがあります。
FEED型では具体的に次のような流れでフィードバックを行います。
・Fact
「昨日のプレゼンテーションでは、よく説明できていましたよ。」
・Example
「ただ、説明の時間が長すぎたので、質疑応答の時間が短くなってしまいましたね。」
・Effect
「参加者のアンケートではプレゼンテーションには満足したものの、疑問や質問をその場で解消したかったという意見が見られました。」
・Different
「次回のプレゼンテーションの際には、時間配分を工夫して、参加者の意見や質問に答えられる時間を作るように意識してください。」
KPT型
KPT型のKPTとは「Keep」「Problem」「Try」の頭文字をとったものです。
Keepとは継続して行うことであり、Problemとは課題や問題点、Tryは改善のために新たに取り組むことを指します。
KPT型は、プロジェクトや業務の進捗を確認し、今後の方向性を見直すうえで活用しやすいフィードバック手法です。
また、KPT型はコミュニケーションの中で今後の活動を明確にするという特徴があります。
KPT型のフィードバックの具体的な流れをご紹介します。
・Keep
上司「1回目のイベントは成功しましたが、企画するうえでどこに成功のポイントがあったと思いますか?」
部下「ターゲットを明確化したことで、関心の強いユーザーを集客でき、成果を得られたのではないかと考えています」
・Problem
上司「確かに参加者からの評判はよかったですね。では、次のイベントまでに改善が必要だと感じる部分はありますか?」
部下「受付の際に長い列ができ、お客様をお待たせしてしまったことが気になります」
・Try
上司「スタッフの配置に問題はなかったですか?イベントの開催前には、前回よりも受付に配置するスタッフの数を増やしてはどうですか?」
部下「そうですね。次回は、他の部署にも協力を依頼して人員を増やしたいと思います」
SBI型
SBI型とは、相手が置かれていた状況を示したうえで、相手がどのような行為をとったかを伝え、その結果で生じたことや行為による影響を伝えるフィードバック手法です。
SBIは「Situation(状況)」「Behavior(行為)」「Impact(影響)」の頭文字をとったものです。
具体的な状況や行動を示すことで、情報を整理しながら順に課題を伝えられるため、フィードバックを受ける側も納得しやすくなり、信頼関係も構築しやすくなります。特に、特定の具体的な行動についてフィードバックをしたい場合などに効果的なフィードバック手法です。また、フィードバックを受ける側の不安を軽減できるため、建設的な話し合いをしやすくなるといったメリットもあります。
SBI型のフィードバックの例をご紹介します。
・Situation
昨日のA社との打ち合わせの件だけど
・Behavior
よくA社の状況を調べて、A社に合わせた提案ができていたね。
・Impact
そのおかげで今朝、A社からぜひ導入したいと連絡が入ったよ。
サンドイッチ型
サンドイッチ型とは、ネガティブな内容のフィードバックを、ポジティブな内容のフィードバックの間に、サンドイッチのように挟む形で伝える手法です。
初めにポジティブなフィードバックを行い、よかった点を伝え、相手にポジティブな印象を与えることで相手の緊張を解き、指摘や課題など、ネガティブなフィードバックを話すきっかけをつかみやすくなります。
また、最後にポジティブな内容で相手によい印象を残して終えるため、相手はネガティブな指摘事項もポジティブに捉えやすくなります。
加えて、ポジティブな話題でフィードバックを終えるため、モチベーションの低下も抑える効果があります。しかしながら伝え方によっては、課題や問題点の指摘事項が印象に残りにくくなるというリスクがある点に注意しなければなりません。
サンドイッチ型フィードバックの具体例をご紹介します。
・ポジティブな内容
先日提出してもらったプレゼンテーションの資料は非常によくできていたよ。
・ネガティブな内容
ただ、もう少し細かくデータを分析できていたら、もっと説得力が増したんじゃないかな。
・ポジティブな内容
とはいえ、全体的にはよい資料になっていたし、初めて作ったにしては完成度が高いものだったと思うよ。
ペンドルトン型
ペンドルトン型とは、心理学者であるペンドルトンが提唱したフィードバック法です。
ペンドルトン型のフィードバックでは、「話す内容」「よかった点」「改善点」「今後の行動計画」「まとめ」の順に部下との会話を進めていきます。
じっくりコミュニケーションを図りながらフィードバックができるため、互いの信頼関係が構築できるとともに、部下にも考える時間を与えることができ、主体性を高められるといったメリットがあります。ペンドルトン型のフィードバックの具体例をご紹介します。
・話す内容
上司「今日のプレゼンテーションの反省をしてみよう」
・よかった点
上司「グラフや表も多く使われていて、わかりやすい資料を作成したなと感心したよ」
・改善点
上司「自分では何か気が付いたことはあるかな?」
部下「発表時に少し早口だったので、聞き取りにくかったのではないかと思います」
・今後の行動計画
上司「では、改善するためにはどうすればよいと思う?」
部下「プレゼンテーションの前にストップウォッチを使って、話すスピードを確認したいと思います」
・まとめ
上司「よいアイディアだね。では、次回はプレゼンテーションの前に時間配分のチェックを実践してください」
フィードバックを成功させるためのポイント
適切なフィードバックはさまざまなメリットをもたらします。フィードバックを成功させるためのポイントをご紹介します。
具体的で行動可能な内容を伝える
まず、フィードバックはできる限り具体的に伝えることが重要です。
ポジティブな内容を伝える際にも、具体性がなければどこがよかったのかがわからず、部下は自分の強みを十分に把握できません。
また、ネガティブな内容の際にも、曖昧な表現をしてしまうと指摘事項が明確に理解できないため、具体的な改善行動につなげられません。
フィードバックを行う際には、その後の行動につなげやすいようにシチュエーションや具体例を出し、どのような点が評価でき、どのような点に課題が残っているのかをしっかり伝えることが重要です。
タイミングと頻度を意識する
良かった行動や改善が必要な行動をとったときから時間が経ってしまうと、記憶も薄れてしまいます。また、時間が経ってから過去のことを指摘されても、部下は「なぜ今さら過去のことを蒸し返すのか」とネガティブな感情を抱く恐れもあります。
そのため、フィードバックは後からまとめて伝えるのではなく、気が付いたときにできるだけタイムリーに、こまめに行うことが大切です。
何らかの行動の後にすぐフィードバックができれば、ネガティブな内容であってもポジティブな内容であっても、部下は振り返りがしやすくなるため、主体的な成長につなげやすくなります。
相手の行動に焦点を当てる
フィードバックの際に最も行ってはいけないことが、部下の行動ではなく、性格や人間性に対するネガティブなフィードバックをすることです。
上司に人格を否定されたと感じれば、仕事に対するモチベーションが低下するだけでなく、信頼関係を構築することも難しいでしょう。
さらに、精神的なダメージにつながり、パワハラとして訴えられる恐れもあります。フィードバックをする際には、人柄ではなく、事実に基づいた行動に焦点を当て、よい点や改善が必要な点について客観的に伝えることが重要です。
双方向のコミュニケーションを心がける
上司が一方的にフィードバックをするだけでは、上司と部下の間に信頼関係は構築できず、フィードバックの内容も受け入れにくくなります。また、改善すべき課題がある場合でも、部下には上手く対処できなかった理由があるのかもしれません。
フィードバックの目的は、部下の自律的な成長を促すことです。
部下が自分で改善策を考え、行動できるように導くためには、部下の意見にもしっかり耳を傾けながら上司としてのアドバイスを行うことが重要になるでしょう。
フィードバックの際には、部下の中から答えを引き出すような問いかけをすることも必要です。
次の記事でもフィードバックの効果的な方法について具体的にご紹介しています。ぜひ、ご一読ください。
<関連記事>メンバーのモチベーションを上げる!正しいフィードバックの仕方とは
・「なんとなく」や特定の人の勘 に頼った配置 から脱却したい
↓
従業員のスキルを可視化し、組織の課題を可視化。評価・育成記録まで 一元管理 し、データに基づいた配置を実現
⇒デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
フィードバックする際の注意点
フィードバックは、伝え方によっては部下のモチベーションを低下させる恐れもあり、フィードバックをする際には次の点に注意する必要があります。
感情的にならず客観的な態度を保つ
フィードバックは、客観的な事実を踏まえ、よい点や改善すべき点を伝える行為です。
感情的になると部下は萎縮してしまう恐れがあり、部下は「上司に怒られないためにはどのようにすべきか」という点に主軸を置いてしまいます。そのような状況下では、部下の成長も組織の成長も期待できません。
また、上司の主観を交えた意見を伝えても、その意見には説得力がなく、部下のモチベーションを低下させる可能性があります。
フィードバックをする際には、決して感情を入れず、部下の行動に焦点を当て、客観的な評価や指摘を伝えることが重要です。
適切な環境と場所の選択
フィードバックは原則として、1対1で行うべきものです。
組織のメンバーが集まる中でフィードバックを行うと、ネガティブな内容の場合、指摘を受けた従業員は侮辱されたと感じ、上司との信頼関係が崩れてしまうリスクがあります。
また、フィードバックの際に、相手の考えを引き出そうとしても大勢の前では本音を言いにくいケースもあるでしょう。
たとえポジティブな内容を伝える場合であっても、フィードバックを行う際には、部下の気持ちに配慮し、周りの目を気にせず、リラックスした状態で話ができる場所を選ぶことが重要です。
フォローアップの徹底
フィードバックをしただけでは、フィードバックの効果は十分に得られません。
フィードバック後に、部下がしっかり課題に向き合いながら改善策を立て、行動に移しているかどうかを確認するフォローアップを徹底することも必要です。
課題はしっかり理解しているものの、なかなか効果的な改善策が見つけられずにいる場合や、行動に移せていないような場合は、フィードバックの繰り返しや、別の形でのサポートを行わなければなりません。
フィードバックは、その後のフォローアップを継続することで、効果を増大させることができるという点を忘れないようにしましょう。
ビジネスにおけるフィードバックの事例
ビジネスにおいてフィードバックが活用されている事例を2つご紹介します。
360度評価
360度評価とは、上司だけでなく、同僚や部下、他部署など、複数の人の視点から多角的に評価をする評価手法です。あらゆる方向から評価するため、360度評価と呼ばれます。
360度評価は、人事評価のためだけでなく、人材育成の目的でも実施されるものです。上司という限定された人物からだけではなく、複数人からフィードバックをもらえるため、自分の状況をより客観的に把握しやすくなります。また、今後の改善点もより具体的に考えることができるでしょう。
さらに、360度評価を継続することで複数の人からポジティブなフィードバックを受けられるようになると、モチベーションも高まり、成長スピードも速まる可能性があります。
<関連記事>360度評価とは?導入のメリットや項目例、成功のポイントを解説
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で向き合う定期的な話し合いです。
上司と部下がコミュニケーションを重ねることで信頼関係を構築し、部下の成長をサポートする目的で実施されるものですが、定期的に上司と部下が1対1で対話する機会は、フィードバックにも最適な機会だといえます。
また、1on1ミーティングを実施していれば、フィードバックを実施した後にも再び対話の機会を持てるため、フォローアップもしやすくなるというメリットがあります。
ただし、1on1ミーティングが毎回フィードバックの場になってしまうと、部下がその他の相談をしにくくなる恐れもあるため、注意が必要です。
<関連記事>1on1とは?実施の目的や効果、トーク例などを解説
フィードバックを組織の成長につなげる
フィードバックは、従業員の成長だけでなく、組織の成長にもつながるものです。フィードバックを組織の成長に活用する方法についてご説明します。
タレントマネジメントの活用
タレントマネジメントは、従業員のスキルや能力を数値化し、客観的なデータで一元管理できるシステムです。また、目標設定や目標変更の履歴、進捗を残すことができるため、目標の達成度合いや従業員の成長度合いも確認できます。
タレントマネジメントによる公平で客観的な評価と、目標に対する進捗度合いのデータは、フィードバックにも活用できるものです。
また、HRMOSタレントマネジメントにはフィードバック機能も付加されているほか、1on1ミーティングの記録も蓄積できます。また、客観的かつ多面的な評価を実施する360°フィードバックも可能です。

<関連記事>【事例付き】タレントマネジメントとは?目的、システム導入や比較・活用方法
フィードバック文化の醸成
ビジネスにおけるフィードバックは、上司から部下、リーダーからメンバーに向けて実施されるケースが多くなります。しかし、組織全体が成長するためには、若い世代だけでなく、上司やリーダーといったマネジメントをする立場にある人材の成長も欠かせません。上司や部下といった関係性にこだわらず、立場を超えて相互にフィードバックができる企業文化の醸成は、個人の成長とともに組織の成長を促すものです。
双方向のフィードバック文化の形成は、簡単なことではありません。しかしながら、フィードバックの文化が組織に徐々に根付いていけば、相互にフィードバックができる関係性を構築できるようになると期待できます。
フィードバックスキル向上のための取り組み
継続的なフィードバックを実践し、組織力を高めるためには、フィードバックが適切なものでなければなりません。
フィードバックによって部下が自分の弱みや強みを認識し、自分の行動を変容することが部下の成長につながります。しかし、上司が適切なフィードバックをすることができなければ、部下にも適切なアドバイスや気付きを与えることはできません。
そのため、フィードバックの成功においては、上司のフィードバックスキルがカギとなるのです。上司のフィードバックスキルを高めるための研修やセミナーなども実施し、組織として効果的なフィードバックを行えるよう、ノウハウの蓄積を進めることが重要です。
まとめ
ビジネスにおけるフィードバックとは、上司が部下に行動の成果や改善点などを伝え、部下の成長を促進する取り組みです。効果的なフィードバックを実施すると、部下の成長はもちろん、パフォーマンスやモチベーションの向上、成長する組織の形成に役立ちます。
フィードバックは、フォローアップも合わせて、継続して実施することが重要です。1on1ミーティングや360度評価なども活用しながら、人と組織の両方の成長を目指す取り組みを目指しましょう。
『目標達成』に直結する仕組み、ありますか?
過去の会話を履歴として残すことで、メンバーの成長と課題を「見える化」し、次の一手を明確にします。
フィードバックの質を向上させ、目標達成を加速させる仕組みを今すぐ手に入れませんか?