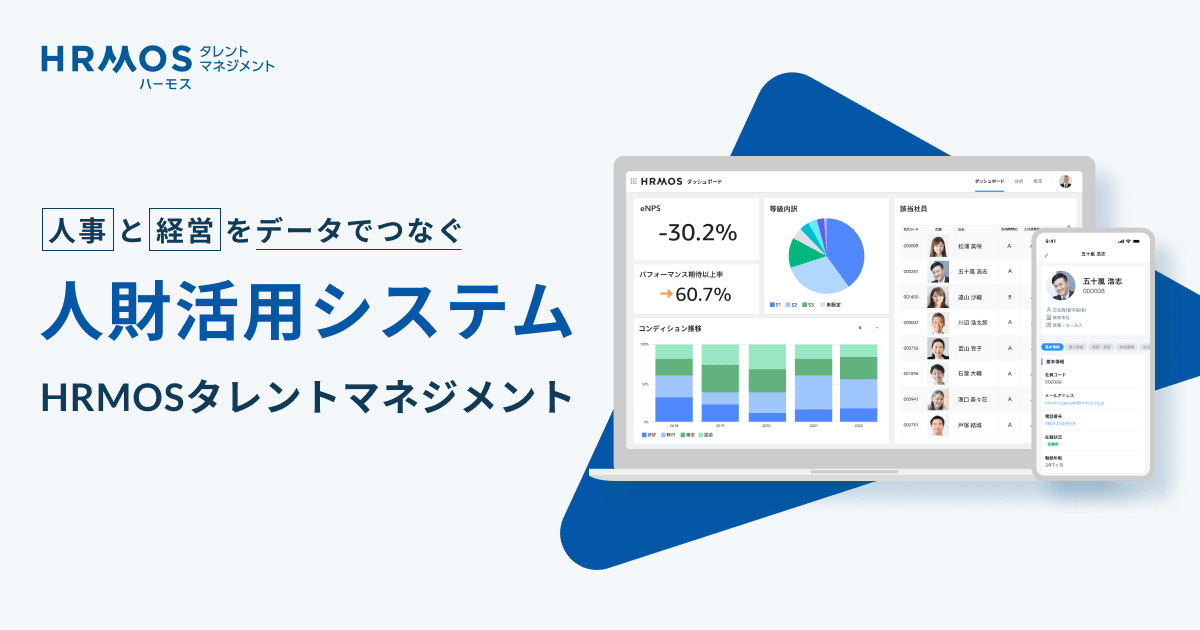目次
こんにちは。「HRMOS(ハーモス)タレントマネジメント」のHRMOS TREND編集部です。
こちらからお役立ち資料「タレントマネジメント成功への条件」を無料でダウンロードできます!
近年、企業の人事管理において「タレントマネジメント」という言葉が注目されています。とはいえ、具体的に何を指すのか、どのような背景や目的があるのかを理解していない人も多いようです。この記事ではタレントマネジメントの基本的な概念から、実際の企業での取り組み方法までをわかりやすく解説していきます。人事の専門家や経営者だけでなく、一般の社員にとっても有益な情報となりますので、ぜひ参考にしてください。
人事における「タレント」とは
タレントとは、英語で「才能・能力・資質」を意味します。人事の視点から見ると、これは「才能・能力・資質を持つ人材」を指します。芸能界のタレントとは異なる概念です。企業においては、優秀な人材を「Aクラス人材」や「ハイパフォーマー」と呼ぶこともありますが、「タレントか否か」は、その人の持つ「才能・能力・資質」に注目します。
例えば、化粧品メーカーでは、戦略的思考が得意でなくても、人とのコミュニケーションが得意な人は、接客販売部門でのタレントとして扱われる可能性があります。また、IT企業の事例を取り上げると、プログラミングスキルが高くなくても、チームでの協力や新しい技術への適応能力が高い人は、プロジェクトリーダーや研究開発部門のタレントとして重用されることが期待されるでしょう。
さらに、金融業界の事例を考えると、数値分析やリスク管理のスキルが高い人は重要なポジションでのタレントとして評価されることが一般的ですが、顧客との関係構築や営業戦略の立案能力が高い人は、営業部門や顧客サービス部門でのタレントとして高く評価されます。
このように、タレントとは一般的なスキルや経験だけでなく、その企業や業界特有のニーズに応じて、特定の能力や資質を持つ人材を指します。企業は、これらのタレントを適切に発見し、彼らの能力を最大限に活かすことで、組織全体の競争力を高めることができるのです。そのため、タレントの定義や評価基準は、企業のビジョンや戦略、業界の特性に応じて柔軟に設定されることが求められます。
タレントマネジメントの定義
タレントマネジメントは、企業の社員のスキルや能力などのデータを把握し、企業の利益に貢献するタレントを見つけ出し、そのタレントのパフォーマンスを最大化するための配置や教育を戦略的に行う取り組みを指します。これまでの人材育成は全社員が対象でしたが、タレントマネジメントでは、選ばれたタレントに対して必要な育成プログラムを実施するのです。タレントマネジメントについての定義を明確にしておくために、入門的知識として、最初にいくつかの著名な企業による定義や考え方を紹介します。
<関連記事>
・【事例付き】タレントマネジメントとは?目的、システム導入や比較・活用方法
IBMの考え方
IBMは、多岐にわたるビジネスソリューションを提供する世界的なIT企業です。人事部門は、タレントマネジメントの定義において、組織の文化や価値観を反映した考え方を重視しています。IBMによるタレントマネジメントの定義は「組織のビジョンや戦略をサポートし、従業員の成長と発展を促進する取り組み」というものです。この実現には、高度なスキルセットを持つ候補者の募集、継続的な学習と開発の機会の提供、および組織内での昇進を奨励して価値のあるチームメンバーに対する十分な報酬が重視されます。
Microsoftのアプローチ
Microsoftは、世界中で使用されるソフトウェアやサービスを提供する巨大企業です。人事部門は、タレントマネジメントの定義において、データ駆動型のアプローチを取っています。Microsoftによれば、タレントマネジメントは「従業員の能力やスキルを最大限に活用し、組織の目標やビジョンに合わせて彼らを育成・発展させる戦略的な取り組み」として定義されています。
ADPの定義
ADP(Automatic Data Processing)は、世界的に知られる給与計算および人事管理ソリューションの提供企業です。多くの企業や組織が、給与計算、人事、およびその他の関連サービスのためにADPを利用しています。このADPによれば、タレントマネジメントは「雇用主が生産的であり、長期間組織に留まる可能性のある労働力を募集・育成する方法」として定義されています。タレントマネジメントが戦略的に実施されれば、ビジネスの全体的なパフォーマンスの向上や競争力の強化を実現する可能性が高まります。簡単に言えば、タレントマネジメントは、組織の最も重要なリソースである人々への投資を意味するのです。これには、高度なスキルセットを持つ候補者の募集、継続的な学習と開発の機会の提供、および組織内での昇進を奨励して価値のあるチームメンバーに報酬をフィードバックすることが含まれます。
TechTargetの定義
TechTargetは、IT専門家や技術的な意思決定者向けのコンテンツを提供する企業です。彼らは特定の技術市場に焦点を当て、関連する製品やサービスに関する情報を提供しています。TechTargetによれば、タレントマネジメントは「企業が従業員を募集、訓練、および保持する方法を最適化するために使用するプロセス」として定義されています。これは、主に人事プロセスを通じて行われるものです。
Forbes Advisorの考え方
Forbes Advisorは、世界的な経済雑誌Forbesの一部として、消費者に金融製品やサービスに関するアドバイスや情報を提供するプラットフォームです。専門家による評価やガイドを通じて、消費者に賢明な金融決定を下すための情報を提供しています。そのForbes Advisorによれば、タレントマネジメントは「チームが最高のパフォーマンスを発揮するための動機づけとなる開発の機会や戦略を包括するもの」として考えられています。
これらの定義や考え方から、タレントマネジメントは単に人材の募集や保持だけでなく、従業員の能力やスキルを最大限に活用し、組織の目標やビジョンに合わせて彼らを育成・発展させる戦略的な取り組みであることがわかります。
さまざまな業界におけるタレントマネジメント
タレントマネジメントは、企業の競争力を高めるための戦略的な取り組みとして、多くの企業で実践されています。以下に、業種ごとの典型的な事例をいくつか紹介します。
ある大手製造業の企業では、新製品の開発を担当するエンジニアチームにおいて、特定の技術スキルを持つエンジニアをタレントとして特定しました。このエンジニアたちは、通常の研修プログラムに加え、海外の研究機関や大学での研修を受ける機会が与えられました。結果として、新しい技術の導入や製品開発のスピードが向上し、企業の競争力が大きく向上したのです。
また、ある流通業の大手企業では、店舗スタッフの中から優れた接客スキルを持つ者をタレントとして選出しました。彼らには、専門的な接客研修やマネジメント研修を受ける機会が提供され、店舗のリーダーとして活躍するようになったのです。その後の店舗の売上や顧客満足度が大幅に向上したのは、彼らのタレントがうまくマネジメントされた効果といえるでしょう。
さらに、金融業界の大手銀行では、高い顧客対応能力を持つ社員をタレントとして特定し、彼らにはプレミアム顧客対応の研修や、海外の支店での短期研修が提供されました。これにより、プレミアム顧客の満足度が向上し、資産運用の額も増加したのです。
ある広告代理店では、推奨するタレントとして、クリエイティブなアイディア提案力という点にフォーカスしてデザイナーやコピーライターを選出しました。彼らには、海外の有名な広告フェスティバルへの参加や、他のクリエイターとの交流の場が提供されたのです。結果として、新しいアイディアや手法を取り入れ、受賞歴のある広告を多数制作することにつながったのです。
これらの事例からもわかるように、タレントマネジメントは、単に優秀な社員を特定するだけでなく、彼らの能力を最大限に引き出すための環境や教育を提供することが重要です。そして、これにより企業全体のパフォーマンスや競争力の向上につながるのです。
<関連記事>
・タレントマネジメントを組織開発に活かす方法を解説
タレントマネジメントの起源と展開
タレントマネジメントの起源は、1990年代のアメリカにあります。この時期、労働市場の変動や技術の進化、経済のグローバル化など、多くの要因が組み合わさり、企業は最も優れた人材を獲得・保持するための新しいアプローチを模索するようになりました。なかでも、コンサルタント会社マッキンゼー・アンド・カンパニーの書籍『The War for Talent』は、この概念の普及に大きく寄与したといわれています。これは、企業が最も優れたタレントを獲得、育成、保持するための戦略と方法についての研究を基にまとめられた本です。特に、企業の成功は優れた人材の獲得とその人材の能力を最大限に活用することにかかっているという考えが強調されたのです。
この本の影響によって、シリコンバレーのスタートアップ企業は積極的にタレントマネジメントの戦略を採用し始めました。例えば、FacebookやNetflixは、独自のタレントマネジメントのフレームワークを開発し、優れた技術者やマネージャーの獲得と育成に成功しました。これらの企業は、従業員のキャリアパスの設計、メンタリングプログラム、継続的な教育の提供など、タレントの育成と保持に多大な投資を行ったのです。
一方、日本では、最初はグローバル企業での導入が始まりました。トヨタやソニーなどの大手企業は、国際的なビジネス展開を進める中で、多様なバックグラウンドを持つタレントの獲得と育成が必要となり、タレントマネジメントの取り組みを強化する必要に迫られたのです。そして、2015年頃からは、国内の中小企業やベンチャー企業も、タレントマネジメントの重要性を認識し、積極的に取り組むようになりました。
これらの動きを通じて、タレントマネジメントは、企業の競争力を高めるための戦略的な取り組みとして、世界中で注目されるようになり現在に至ります。そして、現代のビジネス環境では、タレントの獲得、育成、保持は、企業の持続的な成長と成功のための不可欠な要素となっているのです。
<関連記事>
・【タレントマネジメントの背景と進化】人材マネジメントの歴史とシステムの目的
なぜタレントマネジメントが注目されるのか?
タレントマネジメントが注目される背景には、経営環境の変化、従業員の価値観の多様化、労働力人口の減少などがあります。これらの要因は、企業が持続的な成長を達成するためには、優れた人材を獲得・育成・保持することなしでは立ち行かなくなる可能性を示唆しているのです。以下でそれぞれの要因について説明していきます。これらの背景から、タレントマネジメントは、企業の競争力を維持・向上させるための重要な戦略として、多くの企業で注目され、実行されているのです。
変化する経営環境
グローバル化の進行により、企業は世界中での競争に直面しています。例えば、AppleやAmazonなどの国際的な大手企業は、グローバルな視点でのタレントマネジメントを実施し、多様な文化や価値観を持つ人材を獲得しています。また、ITの活用によるビジネスモデルの変化は、企業が新しい技術や手法を迅速に取り入れる必要性を高めています。デジタルトランスフォーメーションやAI技術の導入により、企業は従来のビジネスモデルを見直し、新しい市場や顧客層をターゲットにする必要が出てきたのです。
従業員の価値観の多様化
ダイバーシティの推進や働き方改革により、従業員の価値観や働き方が多様化しています。例えば、多くの企業では、ジェンダーや年齢、国籍などの多様性を尊重し、それぞれの強みを活かすための取り組みを進めているところです。また、リモートワークやフレックスタイム制度の導入により、従業員のワーク・ライフ・バランスの向上が求められています。ミレニアル世代やZ世代の台頭により、キャリアの考え方や働き方に対する価値観が大きく変わりつつあり、企業はこれに対応するための新しい人材戦略を考える必要があるのです。タレントマネジメントは、その戦略の一翼を担います。
<関連記事>
・企業のダイバーシティ&インクルージョン 事例とともに意味から取り組みの具体例や推進のポイントまで解説
減少する労働力人口
多くの先進国、特に日本では、高齢化社会が進行し、労働人口が減少しています。これにより、企業間において限られた人材の中から最も優れたタレントを獲得するための競争が激化しているのです。例えば、日本の大手企業は、新卒採用だけでなく、中途採用や外国人採用を積極的に行い、多様な人材を獲得する努力をしています。また、多様なバックグラウンドを持つ人材の活用により、新しい市場や顧客層へのアプローチが可能となり、企業の競争力を高める要因となっています。このような環境では、きめ細かなタレントマネジメントこそが勝敗を分けるのです。
人事管理テクノロジーの発達
きめ細やかな情報管理が求められるタレントマネジメントの現場では、デジタルテクノロジーを活用したシステムが必須です。テクノロジーの発達により生まれたこのシステムは、わかりやすいインターフェースを持ち、Excelなどの表計算ソフトでは困難な処理を素早く確実に実施することができます。
<関連記事>
・タレントマネジメントと人事管理の違いは?目的やシステムの違いを徹底解説
タレントマネジメントの目的とは?
タレントマネジメントの最終的な目的は「企業利益の向上」です。その最終目標を達成するためには、多くの中間目的を設定する必要があります。それらを達成することで企業全体のパフォーマンスを高めることを目指します。ここで、目標について明確に言語化しておきます。以下の目的を達成することで、タレントマネジメントは企業の利益の向上を実現します。その結果、企業全体としての持続的な成長につながるといえるのです。
<関連記事>
・タレントマネジメントの目的は?メリットや効果を解説
タレントを獲得すること
企業の成長や競争力を維持するためには、優れた人材を継続的に獲得することが不可欠です。例えば、Googleは、独自の採用プロセスを通じて、世界中からトップクラスのエンジニアやマーケターを獲得しています。このような獲得戦略により、企業は新しい市場や技術の開拓、イノベーションの推進など、多岐にわたるビジネスチャンスを掴むことができます。
継続的に育成すること
獲得したタレントを最大限に活用するためには、継続的な育成が必要です。例えば、トヨタは、従業員に対して独自の教育プログラムやOJTを提供し、彼らのスキルや知識を高めています。これにより、企業は変化する市場環境や顧客ニーズに迅速に対応する能力を持つ人材を保持し続けられるのです。
<関連記事>
・人材育成のポイントとは?考え方や指導のコツを紹介
適切なポジションへ配置すること
タレントを適切なポジションに配置することで、その能力やスキルを最大限に活用することができます。例えば、IBMは、データ分析やAI技術に精通したタレントを、新しいビジネスユニットやプロジェクトチームに配置し、新しいサービスや製品の開発を推進しているのです。このような配置戦略により、企業は迅速かつ効果的にビジネスの変革やイノベーションを進めることができるでしょう。
定着率を高めること
優れたタレントを長期間保持することで、企業はその知識や経験を継続的に活用することができます。例えば、Netflixは、高い給与やフレキシブルな働き方を提供することで、優れたタレントの定着を促進しています。企業がタレントのノウハウやネットワークを継続的に活用し、ビジネスの成長や競争力の維持を可能とするには、このような経済的かつ環境的整備が不可欠です。
タレントマネジメント戦略のための6ステージ
タレントマネジメントを成功させるには、大まかに次のような6つの段階を計画しておく必要があります。これらの各ステージを通じて、タレントマネジメントは企業の競争力を維持・向上させるための重要な戦略となるのです。この6ステージの実践により、持続的な成長と成功の可能性が高まるでしょう。
<関連記事>
・タレントマネジメントのフレームワークとは?組織作りに有効な手法を解説
ステージ1:必要なタレントイメージを決める
まず、自社にとって必要なタレント像を明確にしましょう。これは、企業のビジョンやミッション、中長期的な経営戦略に基づいて行われます。あるIT企業がAI技術の導入を戦略的に進める場合、AIに関する知識や経験を持つエンジニアや研究者をタレントとして位置づけることが考えられます。このステージでは、企業の将来像とそれを支える人材像を一致させることが重要です。
ステージ2:タレント関連情報の可視化
人材の情報をデータベース化し、可視化します。これにより、企業は各従業員のスキルや経験、業績などの情報を一元的に管理・分析することができます。大手製造業の企業では、全従業員の業績や研修履歴、異動履歴などの情報をデータベースに集約し、人材の流動や成長をリアルタイムで把握しています。
ステージ3:タレントを特定する
人材データベースからタレントを特定する段階です。このステージでは、企業が求めるタレント像と実際の従業員の情報を照らし合わせ、タレントとしてのポテンシャルを持つ人材を特定します。金融業界の企業であれば、高い営業成績を持つ社員や、特定の資格を持つ社員をタレントとして特定することになるでしょう。
ステージ4:人材獲得計画の立案
タレントの育成や採用の計画を立てます。このステージでは、特定したタレントの現状のスキルや経験を踏まえ、将来必要となるスキルや経験を獲得するための育成プログラムや研修を計画します。また、外部からの新たなタレントの獲得を目指す場合、採用戦略やターゲットとなる人材像を明確にしなければなりません。ある広告代理店では、クリエイティブな思考を持つ若手クリエイターをターゲットにした採用イベントを開催しています。
ステージ5:タレントの採用及び育成
計画に基づき、タレントの育成や採用を行います。育成の場合、研修やセミナー、OJTなどのプログラムを実施することになるでしょう。採用の場合、求人広告の掲載や採用イベントの開催、面接や選考を行います。あるIT企業では、特定の技術スキルを持つエンジニアの育成のため、外部の専門家を招いての研修を実施しています。
<関連記事>
・OJTとOFF-JTとは?違いやメリット・デメリットを人材育成の観点で解説
ステージ6:PDCAを回す
実施した育成や採用の成果を評価し、必要に応じて見直しする段階です。このステージでは、タレントのパフォーマンスや成果を定期的に評価し、育成や採用のプロセスを改善するためのフィードバックを得ることが重要です。ある製薬企業では、新たに採用した研究者の業績や貢献度を評価し、次回の採用戦略の見直しを行っています。
タレントマネジメントシステムの導入のヒント
タレントマネジメントを効果的に実践するためには、適切なシステムの導入が不可欠です。しかし、多くのシステムが提供されているため、どれを選ぶかは一筋縄ではいきません。以下は、システム選びの際のポイントと具体的な事例を交えた選び方のガイドラインです。これらのポイントを踏まえながら、自社のニーズや状況に合ったタレントマネジメントシステムを選ぶことで、効果的なタレントマネジメントの導入が可能となるでしょう。
<関連記事>
・タレントマネジメントを効果的に運用するためのシステム導入と活用のポイント
自社のニーズを明確にする
まず、自社がタレントマネジメントで何を達成したいのか、具体的なニーズを明確にします。例えば、ある製造業の企業では、技術者のスキルマップを作成し、それに基づいて研修を提供することを目的としていました。このようなニーズに合わせるのであれば、スキルマッピング機能を持つシステムを選ぶことが考えられます。
予算を考慮する
システムの導入にはコストがかかります。初期導入費用だけでなく、運用・保守費用も考慮しておかなければなりません。中小企業の場合、低コストで導入できるクラウド型のシステムがよいでしょう。
<関連記事>
・中小企業こそタレントマネジメントを導入するべき理由、メリットを解説
導入後のサポート体制を確認する
システムの導入後も、サポートやアップデートが必要です。あるIT企業では、システムのカスタマイズや新機能の追加を頻繁に行うため、ベンダーとの継続的なサポート契約を結んでいます。このように、自社の運用スタイルに合わせたサポート体制を持つシステムを選ぶことが重要です。
ユーザーフレンドリーなインターフェースを持つものを選ぶ
システムを効果的に活用するためには、従業員が使いやすいものであることが重要です。ある流通業の企業では、年齢層が幅広いため、直感的に操作できるシンプルなインターフェースのシステムを選んでいます。
導入実績や評判を確認する
システムの導入実績や他社の評判を参考にすることで、そのシステムの実際の性能や信頼性を確認することができます。ある金融業界の企業では、同業他社が導入しているシステムの評判や実績を基に、自社の導入を決定しています。
まとめ
タレントマネジメントを導入しフレキシブルな人事戦略を実践しよう
タレントマネジメントは、企業の競争力を高めるための重要な戦略の一つとして注目されています。そして、その場限りの取り組みで終わるものではなく、継続的な見直しと改善が必要な取り組みである点を理解することが重要です。タレントマネジメントの実践によって、経営環境の変化と自社への期待役割に応じて、フレキシブルな人事戦略が可能になることでしょう。