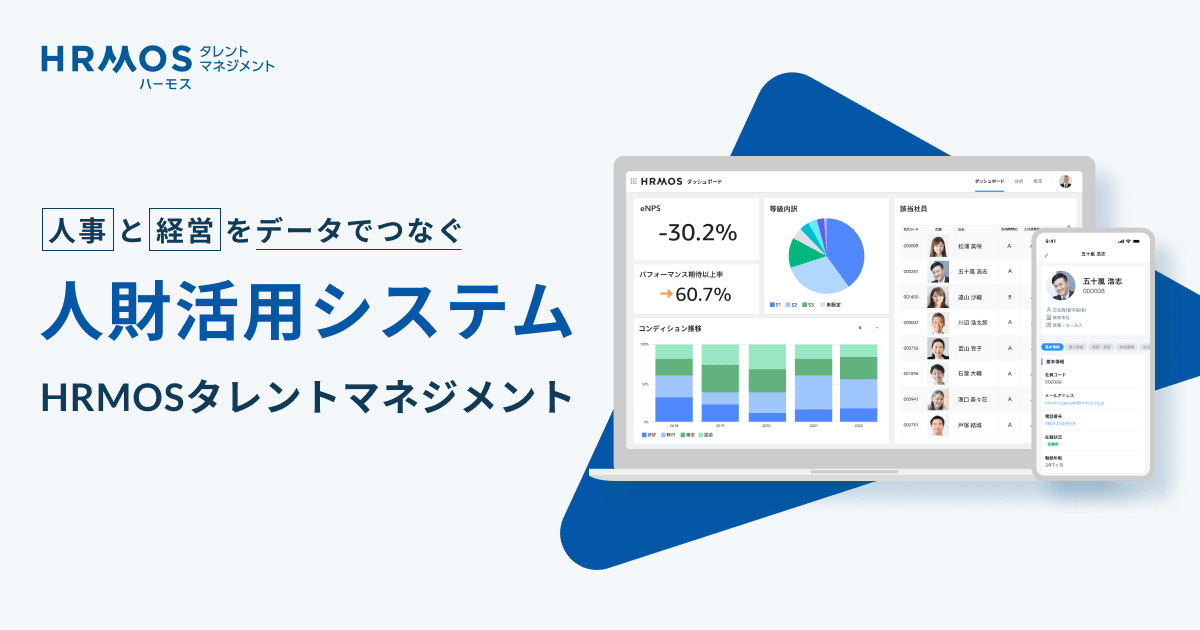目次
企業が成長して価値を高め、時代の変化に合わせながら事業を継続していくうえで、人材育成による人材価値の向上が欠かせません。
DX(デジタルトランスフォーメーション)人材をはじめとした専門性の高い人材の必要性が高まる中、従業員が新しい知識やスキルを学ぶ「リスキリング」が近年注目されています。
本記事では、リスキリングとは何か、意味や注目される背景、導入するメリット、導入方法を紹介します。
リスキリングの意味と定義
リスキリングは、人材の価値を高めて企業価値向上を図る際の手法のひとつです。
企業がリスキリングを導入する際は、その意味と定義を正しく理解しておく必要があります。
リスキリングとは何か
リスキリングとは「業務で必要になる新しい知識やスキルを身に付けること」を指し、英語の「Re-skilling」が語源です。
「Re(再び)」と「skilling(知識・スキルの習得)」を組み合わせたもので、日本語に直訳すると「知識・スキルの再習得」を意味します。
また経済産業省では、リスキリングの定義を以下のように表現しています。
| “「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」”出典:経済産業省「第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会」 |
技術革新やビジネスモデルの変化など、経営環境や時代の変化に対応するため、企業がリスキリングによって従業員の知識・スキル向上を図るケースが増えています。
経済産業省の取り組み
近年はデジタル化が進み、新たな知識やスキルが求められる場面が増えています。そのような中、経済産業省は「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」を実施しています。
支援事業では、キャリア相談や相談内容を踏まえたリスキリング講座の受講、転職相談・職業紹介が行われており、国を挙げてリスキリングに取り組んでいます。
納得感のある評価を効率的に行うための仕組みを整備し、従業員の育成や定着率の向上に効果的な機能を多数搭載
・360°フィードバック
・1on1レポート/支援
・目標・評価管理
・従業員データベース など
リスキリングが注目される背景
企業がリスキリングを導入する場合、そもそもなぜリスキリングを導入する必要性が高まっているのか、リスキリングが注目される背景を理解しておくことが重要です。
リスキリングの実施にはコストや時間がかかり、従業員への負担も発生するため、背景や必要性を理解したうえで、企業として必要な対応を実施することが求められます。
DX推進による人材ニーズの変化
日本ではDX推進により、新しい職業が生まれたり既存の職業で仕事の進め方が変わったりするなど、企業が必要とする人材が従来とは変化しています。
デジタル化に対応できる専門的な知識やスキルを持った人材が必要とされる一方、専門性の高い人材の確保は簡単ではなく、専門人材が不足している企業も少なくありません。
必要な人員を確保するためには、新規採用に加えて社内で専門人材を育成する必要があり、育成手法のひとつとしてリスキリングが注目されています。
<関連記事>
デジタルトランスフォーメーションとは?DX推進で企業・組織を改革する際の課題や企業事例などを解説
AI・IoT技術の進展と業務の自動化
AIやIoT技術の進展に伴い、単純作業や定型業務は今後ますます自動化されることが予想されます。
単純作業や定型業務に人の手が不要になれば、労働者に求められる役割や能力は変化し、創造性や高度な判断力が必要とされる仕事で役割を果たすことが求められます。
創造性や高度な判断力を従業員が身に付けるためには、学びの機会の提供や、人材育成の仕組みの構築が必要です。
リスキリングは、企業が必要な人材を育て、技術進歩に追い付くための重要な手段となり得ます。
リスキリングと類似概念の違い
企業が人材育成を行う場合は、さまざまな人材育成の手法の特徴や違いを理解したうえで、自社に適した仕組みを導入・構築する必要があります。以下では、リスキリングとよく似た概念について、概要やリスキリングとの違いを紹介します。
リカレント教育との違い
リカレント(recurrent)は「循環する」「再発する」などを意味する単語です。
「平成30年版 情報通信白書」では、「リカレント教育は、就職してからも、生涯にわたって教育と他の諸活動(労働、余暇など)を交互に行なうといった概念である」と紹介されています。
リスキリングもリカレント教育も、学習して知識・スキルを身に付ける点は同じです。
しかし、両者では主体が異なります。リスキリングは企業が主体となって行う人材育成を指すのに対して、リカレント教育は働く人自身が主体となって学ぶことを指す概念です。
また、リスキリングは従業員が働きながら社内で知識・スキルの習得を目指しますが、リカレント教育の場合は教育と他の諸活動を交互に行うため、一般的に休職・離職などで仕事から離れて大学などの教育機関で学び直すことを指します。
<関連記事>
【企業が取り組む人的資本投資】人材経営の核心とその戦略的価値
リカレント教育とは?意味や補助金、リスキリング・生涯学習との違いを解説
生涯学習との違い
生涯学習とは、人が一生を通じて学び続けることです。
「平成30年度文部科学白書では「生涯学習」とは、一般には人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます」と紹介されています。
リスキリングも生涯学習も、学習して知識・スキルを身に付ける点は同じです。
しかし、両者では学習の範囲が異なります。
リスキリングでは業務上必要な知識・スキルを学ぶのに対して、生涯学習には業務と関係のない知識・スキルの習得も含まれます。
アップスキリングとの違い
アップスキリングとは、文字通り「スキルをアップデートすること」です。既に持っているスキルを更新することを指します。
リスキリングもアップスキリングも、学習を通じた知識・スキルの習得である点は同じです。
しかし、リスキリングは新たな知識・スキルの習得を指すのに対して、アップスキリングは既に保有している知識・スキルの更新や強化を指す点で、両者は異なります。
たとえば、ある従業員がプログラミングについて学習する場合、プログラミングに関する知識がない初心者が学ぶ場合は、リスキリングです。
一方で、ITエンジニアが最新のプログラミング言語について学習し、既に保有しているプログラミングに関する知識・スキルをアップデートする場合は、アップスキリングに該当します。
・履歴書やExcel管理で情報がバラバラ(人事情報が属人化)
↓
人事情報・スキル・経歴を 自動更新・一元管理ができて、必要な人材に 数秒で辿り着ける 検索・抽出機能
⇒【人材DB機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
リスキリングが企業にもたらすメリット
従業員が知識やスキルを身に付けるリスキリングは、企業にさまざまなメリットをもたらします。以下では、リスキリングの主なメリットを紹介します。
業務効率化の実現
従業員が新しいスキルを習得すれば、業務プロセスが改善され、生産性の向上が期待できます。
データ分析や顧客対応の迅速化、AI・RPA(Robotic Process Automation)に関する知識習得による定型作業の自動化など、作業時間を短縮できれば業務の効率化につながる点が、リスキリングのメリットです。
特定の業務にかかる時間を短縮できれば、新たな業務に取り組むことができ、売上が向上します。また、残業時間が減って残業代の支出が減れば、人件費削減につながります。
残業が減れば、従業員のワークライフバランス改善や労働意欲向上など、健康経営の観点からもプラスの効果を得られる可能性があります。
イノベーションの創出
業務のやり方や、業務で用いる技術が今までと変わらず同じままだと、作業方法やスキルが陳腐化してしまい、時代の変化に取り残されることになりかねません。
しかし、リスキリングによって従業員が新しい知識やスキルを身に付ければ、異なる視点や発想を持つことができるようになり、既存の業務プロセスや製品・サービスに革新をもたらす可能性が高まります。
リスキリングによる知識・スキルの習得が視点の変化や視野・世界観を広げることにつながり、新たな気付きやイノベーション創出の可能性を生み出します。
採用コストの削減
リスキリングによって既存の従業員のスキルを向上させれば、必要な能力を持つ人材を社内で確保でき、新たな人材を外部から採用する必要がなくなります。
優秀な人材を外部から獲得できれば人材育成に時間をかけずに済む点はメリットですが、募集要項の作成や掲載、面接の実施など、採用活動に手間がかかる点がデメリットです。
求人を出してもすぐに応募があるとは限らず、人材確保までに時間がかかることもあります。
一方、社内で人材を育成するリスキリングであれば、採用活動に伴う手間や時間はかかりません。
新規採用のように、いつ人材を確保できるか分からない事態を回避でき、社内で人材育成を実施することで必要な人材を確保できます。
従業員エンゲージメントの向上
企業が従業員に新しい知識や技術を習得する機会を提供することで、従業員は自身の成長を実感でき、仕事への意欲が高まります。
従業員の会社に対する帰属意識や貢献意欲が向上し、企業の生産性向上につながります。
従業員のモチベーションが高く維持されれば、離職率が低下して、優秀な人材の流出を防げる点がメリットです。
従業員の定着率が高ければ、離職による人手不足のリスクが低くなります。
さらに、離職者が少なければ追加で人員を確保する必要が低くなり、採用活動にかかる時間や労力を削減できます。
従業員エンゲージメントについては、以下の記事で解説しているのでぜひご覧ください。
<関連記事>
従業員エンゲージメントとは? 高める方法や事例から学ぶ成功のポイントを解説
企業がリスキリングに取り組む際のステップ
企業が実際にリスキリングに取り組む際の流れは以下のとおりです。
- 経営戦略に基づいた必要スキルの設定
- 現状とのギャップ分析
- 教育プログラムの策定
- 実践機会の提供と評価
リスキリングの効果を最大限に生かすには、各ステップを順番に進め、適切な対応を行うことが重要です。
経営戦略に基づいた必要スキルの設定
リスキリングの実施にあたっては、どのようなスキルが必要なのかを明確にしなければいけません。
まず、企業の目標や将来のビジョンを明確にし、それに基づいて従業員に求められるスキルを特定します。
必要スキルの設定にあたっては、3〜5年後の事業展開を見据えた戦略を描き、その戦略を実現するために必要な人材像をイメージしてみましょう。
企業としての大きな視点から考え始めたうえで、個別の従業員に求められるスキルという細かな視点にまで落とし込む流れで考えると、整理しやすくなります。
たとえば、製造業であれば新たな分野への挑戦や、生産ラインへの新しい技術の導入を見据え、従業員にIoTやロボティクスなどに関する知識を習得させることが考えられます。
現状とのギャップ分析
従業員に知識・スキルを身に付けてもらうためには、現在保有している知識・スキルを確認し、逆に保有しておらず習得が必要な知識・スキルが何か、把握する必要があります。
従業員ごとに現在の業務遂行能力を評価し、将来必要になるスキルを特定するための分析が必要です。
求められるスキルと現状とのギャップを可視化するためには「スキルマップ」や「スキルマトリックス」などのツール活用が効果的です。スキルマップとは、従業員のスキル・知識・経験などを一覧表にまとめたもので、スキルマトリックスは取締役に特化したスキルマップといえます。スキルマトリックスとスキルマップについては、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
<関連記事>
スキルマップとは?社員スキルの見える化によるタレントマネジメント実践
スキルマトリックスとは?作成や開示の目的と必要な項目などを解説
教育プログラムの策定
eラーニング・集合研修・OJTなど、人材育成の手法にはさまざまなものがあります。スキルの種類や従業員の特性に合わせて、最適な学習方法を選択することが重要です。
eラーニングであれば、各従業員がパソコンから動画などを視聴して効率的に学習を進めることができ、OJTであれば知識・スキルを実際に持っている先輩社員から直接話を聞くことができるなど、人材育成の手法によって特徴が異なります。
また、教育プログラムの策定は一度行ったら終わりではありません。学習の進捗を管理し、定期的に教育プログラムの効果を測定して改善することで、よりよい教育プログラムを構築できます。
実践機会の提供と評価
リスキリングの実践機会を提供し、その効果を適切に評価することは、人材育成プログラムの成功に欠かせません。
座学だけでなく、実際の業務に即した形での学びの場を教育プログラムに設けることで、従業員は新しいスキルを実践的に身に付けられます。
リスキリングでは、単に知識を学ぶだけでなく、それを実務で活用できるレベルに達していることが重要です。
実践型研修を行うことで知識・スキルの習熟度合いを確認でき、評価や振り返り、改善によって実際に業務で生かせるレベルに達することができます。
・「なんとなく」や特定の人の勘 に頼った配置 から脱却したい
↓
従業員のスキルを可視化し、組織の課題を可視化。評価・育成記録まで 一元管理 し、データに基づいた配置を実現
⇒デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
タレントマネジメントシステムを活用したリスキリングの推進
リスキリングによる人材育成は、単に従業員に教育プログラムを課して終わるわけではありません。従業員のスキル習得・成長を企業の生産性向上・成長へとつなげることが重要です。
スキルの可視化と分析、学習進捗の追跡と評価、キャリアパスの設計と連動など、効果的にリスキリングを推進するうえでは「タレントマネジメントシステム」の活用が効果的です。
タレントマネジメントシステムとは、社員一人一人が持つスキルや経験、資格などの情報を蓄積・分析し、人材配置や採用などに活用することで、企業の成長につなげていくマネジメント手法です。社員に関する情報をデータ化し、一元管理する仕組みを構築することで、リスキリングを効率的に実施できます。
タレントマネジメントシステムについては、以下の記事で詳しく解説しています。
<関連記事>
HAMOS「スキル管理」従業員1人1人のスキルを数値で可視化・集計
リスキリング導入時の注意点
リスキリングを導入して失敗することがないように、導入時には注意すべき点があります。以下では、主な注意点を3つ紹介します。
従業員の負担への配慮
新しいスキルの習得には時間と労力を要します。
従業員が研修などに参加すると、通常の業務のために使える時間が減るため、同じ部署の人員を増やすなど、適切なサポート体制が整っている必要があります。
周りの社員が協力しようとする意識づくりや、職場の雰囲気づくりが重要です。リスキリングの対象となる従業員だけでなく、他の従業員も含めた社内全体で、人材育成制度の意義や重要性を共有することが求められます。
モチベーション管理の重要性
従業員が社内の教育プログラムに参加しても、モチベーションが続かず途中で意欲が低下してしまう場合があります。
リスキリングの導入にあたっては、知識・スキルの習得に取り組む従業員のモチベーション管理が重要です。
学習意欲を維持して新しいスキルの習得を促進するためには、リスキリングが本人にとって有益であることを十分に理解してもらい、積極的に取り組む姿勢を引き出すなど、適切な動機付けが重要になります。
また、1人で取り組むとやる気が続かないようであれば、集合研修を取り入れることがおすすめです。リスキリングによって自身が成長していることを実感できるように、研修期間中に適宜フィードバックを行う方法なども有効です。
<関連記事>
モチベーションとは? モチベーションマネジメントの方法や事例も紹介!
学習内容の実務への応用
リスキリングで学んだスキルを、日々の業務に取り入れる機会を積極的に設けましょう。
身に付けた知識・スキルが日々の業務やキャリアアップに役立っていると実感できれば、従業員は自身の成長を具体的に感じられ、モチベーションアップにつながります。
また、習得した知識・スキルは、実務で役立てた上で事業経営に貢献してこそ、意味があるものです。新たな知識・スキルを実際の業務で生かすことで業務効率化が進み、企業の生産性を向上させることができます。
リスキリングの具体的な事例
国内外の企業でリスキリングが導入され、ニュースなどで話題になった事例があります。以下では、リスキリングの具体的な事例を紹介します。
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友銀行ではDX推進の取り組みを促進するため、DXスキル学習プログラムを実施しています。
2016年から全従業員を対象として導入された「デジタルユニバーシティ」は、DXを担う人材の育成を目的としたDXスキル学習プログラムです。
マインド・リテラシー・スキルという段階ごとのプログラムが組まれ、デジタル環境の変化やデジタルを学ぶ必要性、最新のデジタル知識を学ぶことができ、システムを作る人だけではなく使う人も対象として研修が行われています。
スキル習熟度別にDX関連スキルの学習機会が提供されるプログラムは、従業員の自律的なリスキリングのために活用されています。
株式会社日立製作所
株式会社日立製作所は、2019年に複数の研修所を統合して「株式会社日立アカデミー」を設立し、デジタル技術を活用するための研修などを実施しています。
従業員へのリスキリング支援施策である「学習体験プラットフォーム(LXP)」は、日立製作所従業員の自律的な学びを支援する施策です。
また、DX推進に必要な人材育成のため、DXリテラシー研修などが実施されています。
富士通株式会社
富士通株式会社は、2022年に「ジョブ型人材マネジメント」の考え方に基づく新たな人事制度を導入しました。
社員の成長機会拡充に取り組み、リスキリング・アップスキリングなどを推進しています。
社員各個人のキャリアオーナーシップ醸成と、これに基づく挑戦・成長を支援するプログラムである「FUJITSU Career Ownership Program(FCOP)」を実施しています。
富士通グループの2023年度の実績として、従業員一人当たりの年間平均学習時間は37.4時間、年間教育金額は84,000円となっています。
リスキリングの将来展望
人材育成の手法として注目を集めているリスキリングは、今後さらに重要性が増すことが予想されます。以下では、リスキリングの位置付けや果たす役割など、将来の展望を紹介します。
グリーンリスキリングの台頭
グリーンリスキリングとは、環境に配慮したスキルの習得を意味する言葉です。
再生可能エネルギーに関する技術の習得や、環境への負荷が低い技術の習得などが該当します。
現代社会において、環境への配慮は企業が取り組むべき重要な事項のひとつです。
関連するスキルの習得は、社会的責任(CSR)活動の一環として評価されるものであり、グリーンリスキリングが今後トレンドとなる可能性があります。
グローバル競争力強化への貢献
グローバル化の進展に伴い、国内企業だけでなく海外企業との競争にもさらされる中、人材価値向上・企業競争力強化につながるリスキリングの重要性は、今後さらに高まるものと考えられます。
リスキリングによる人材育成は、業務効率化やイノベーション創出につながる可能性がある点がメリットです。
リスキリングによって新たな知識やスキルを持つ人材が増えることで、国際市場での競争優位性を維持・向上することにつながります。
<関連記事>
イノベーション人材とは? 育成方法や事例、求められる能力について解説
インクルーシブ・リーダーシップとは?リーダーの種類とインクルーシブな人材の育成
生涯キャリア支援としての役割
従来の一度きりの教育から脱却し、生涯を通じて学び続ける姿勢が求められる現代社会において、リスキリングは個人の市場価値を高め続けるための有効な手段です。
職業選択の幅が広がり、キャリアチェンジの機会が増えれば、個人の成長はもちろんのこと、日本社会全体で雇用の流動性の向上や経済の活性化が期待できます。
まとめ
リスキリングとは、業務で必要になる新しい知識やスキルを身に付けることを意味する言葉です。DX人材など、専門性の高い人材を育成する手法として活用できます。
業務を効率化でき、採用コストを削減できるなど、リスキリングにはさまざまなメリットがあります。ただし、導入にあたっては従業員に負担が生じるため配慮が必要です。
実際にリスキリングを導入する場合は、必要スキルの設定から教育プログラムの策定・実施、実践機会の提供と評価など、手順を踏みながら導入するのがよいでしょう。
タレントマネジメントシステム構築はHRMOSタレントマネジメント
リスキリングの導入から実施、振り返りまでを効率的・効果的に進めるためには、社員に関する情報をデータ化して、一元管理する仕組みを構築する必要があります。リスキリングを推進する場合、タレントマネジメントシステムの活用が効果的です。
HRMOSタレントマネジメントは、ビズリーチで培った即戦力人材データベースのノウハウを生かして、人材データや業務が連携する仕組みを目指しています。
従業員のスキル情報を一覧にして可視化し、最新のスキル情報を客観的に正しく数値化することで、適切な人材配置や従業員の現状に合った人材育成が可能になります。
従業員のスキル管理について、より詳しい機能は以下よりご確認ください。