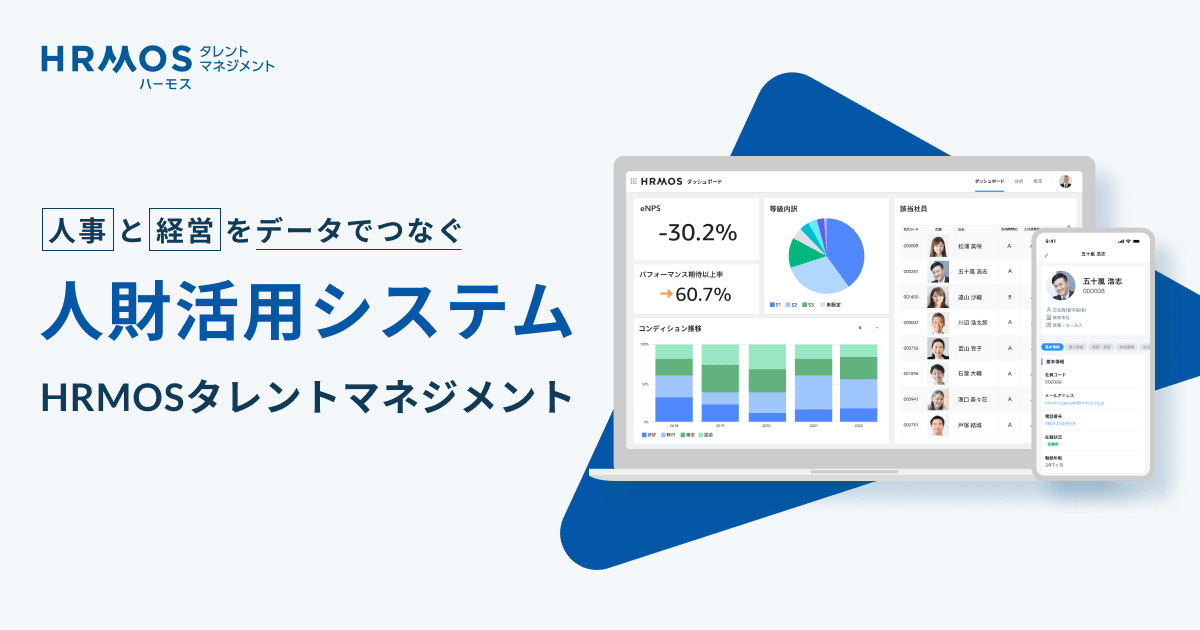目次
企業における人事異動は、組織の活性化や人材の成長を促進する重要な仕組みです。
しかし、異動を適切に管理できていない場合、従業員のモチベーション低下や離職リスクの増大につながる恐れもあります。
特に近年は人的資本経営が注目され、従業員一人一人のキャリア形成やスキル活用が、企業の持続的な成長に直結するようになりました。
そのため、「誰をいつどの部署へ異動させるか」という判断を戦略的に行い、透明性の高い異動管理を実現することが求められています。
本記事では「異動管理」の基本的な考え方から、目的や意義、実務におけるポイントまでを整理します。さらに、効率的に異動を進めるための仕組みや実際に発生しやすい課題とその解決策についても解説します。
異動管理とは
異動管理とは、従業員を適切な部署・役職に配置するための計画的・戦略的なプロセスを指します。単なる人員補充や欠員対応ではなく、組織戦略と人材育成を結びつけることを目的に実施されます。
従来の日本企業では、ジョブローテーションや定期的な異動が一般的でしたが、近年は以下のような背景により異動の形も変化しています。
- 専門性の高度化:特定のスキルを持つ人材を重点配置するケースが増加
- 働き方の多様化:リモートワークや副業解禁により柔軟な人材活用が進展
- 人的資本開示の流れ:キャリア形成支援や従業員エンゲージメントを重視
異動管理を適切に行うことで得られるメリットには、次のようなものがあります。
- 組織最適化:業務に必要なスキルを持つ人材をタイムリーに配置できる
- 人材育成:異動を通じて従業員が多様な経験を積み、キャリアを広げられる
- リスク回避:業務の属人化や不正防止につながり、ガバナンスを強化できる
- 従業員満足度の向上:キャリア希望を反映することでモチベーション維持に貢献
つまり異動管理とは、「企業の成長戦略」と「従業員のキャリア開発」を結びつける人材マネジメントの中核的役割を果たすものといえます。
<関連記事>
人的資本の情報開示とは|ガイドラインで開示が求められる7分野19項目や開示のポイントなどを解説
異動管理の目的と意義
異動管理を導入・強化する最大の目的は「人材の適材適所配置」と「組織の持続的な成長」を両立させることです。
企業は人材を有効活用しながら組織の競争力を高める必要があり、そのプロセスの中で異動は重要な手段となります。
以下では、異動管理の目的と意義を三つの観点から整理します。
人材の適切な配置と組織の活性化
異動管理の最大の目的の一つは、人材を適材適所に配置することによる組織力の強化です。
部署のミッションや直面する課題に対して最適なスキル・経験を持つ従業員を配置することで、業務効率や成果を最大化できます。
場合によっては新規事業への配置や、新しい視点をもたらす異動が、組織に刺激や変化をもたらすこともあります。
また、配置転換の機会を通じて従業員に多様な経験を積ませることで、組織全体の柔軟性や対応力が強まります。
<関連記事>
適材適所な人員配置を実現するには?-4つのポイントとフォローアップ-
人材育成とキャリア開発の促進
異動は、従業員のキャリアの幅を広げる貴重な経験となります。
異なる部署や職務を経験させることで、業務理解が深まり、異なる視点やスキルも身につきます。これにより、従業員の成長意欲を刺激し、長期的な人材育成につながります。
特に将来の幹部候補やリーダー層育成を考えるなら、複数部門や役割を経験させるローテーション型の異動設計が有効です。
従業員自身にもキャリアの選択肢を持たせることで、モチベーションやエンゲージメント向上にも寄与します。
<関連記事>
キャリア開発とは?企業の具体例やミドル・シニア世代の取り組み、よくある誤解と対策を解説
コンプライアンス強化と不正防止
異動管理には、ガバナンスやリスク管理の観点からの意義もあります。一つの部署に従業員をとどまらせ、長期間同じ業務を担わせ続けると、属人化や不正リスクが高まります。
そのため、定期的に人を入れ替えることは、業務の透明性を保つための手段ともなります。
また、異動のプロセスや基準を明確にすることは、企業が公平性や透明性を重視していることを示すメッセージにもなります。それにより、「誰にでもチャンスがある」という信頼感が従業員の間に生まれます。
異動の種類
企業における人事異動にはさまざまな形態があり、その目的や意図によって分類されます。異動管理を適切に行うには、まず「どのような異動の種類があるのか」を理解しておくことが重要です。
ここでは代表的な異動の種類を解説します。
配置転換
最も一般的な異動が、同一企業内で行われる配置転換(ローテーション異動)です。
従業員を異なる部署や職種に配置することで、スキルの多様化やキャリア形成を促進します。
定期的な配置転換を通じて業務の属人化を防ぎ、組織全体のバランスを維持する効果もあります。
<関連記事>
昇進・昇格、降格
昇進や降格にともなう異動は、役職や責任の範囲が変化することに対応した配置換えであり、本人の評価や育成方針に基づいて行われます。
これは、管理職登用や職務範囲の拡大に伴う配置変更を意味します。
例えば、課長職への昇進に合わせて本社への異動を行う場合、組織全体の方針理解や他部門との連携を重視した経験を積む目的があります。
こうした育成型の異動は、後継者育成や次世代リーダー形成の一環として重要です。
出向・転籍
出向とは、従業員が在籍企業に籍を置いたまま、別の企業や関連会社に派遣される形態です。
一方、転籍は、在籍企業との雇用契約を終了し、新たな会社と契約を結ぶ形態を指します。
出向はグループ内人材交流やスキルシェア、経営人材育成などを目的として行われるケースが多く、転籍は組織再編やキャリアチェンジの一環として実施されることがあります。
いずれも、本人のキャリア意向や適性を考慮しないとミスマッチを起こしやすいため、異動管理上は「目的・期間・評価の明確化」が不可欠です。
人事異動の進め方
人事異動を効果的に進めるためには、勘や経験に頼らず、データと計画に基づくプロセス設計が不可欠です。ここでは、異動管理を実務として行う際の代表的なステップを紹介します。
①現状の可視化と課題把握
まず重要なのは、現状の人員配置とスキル分布を可視化し、課題を明確にすることです。
各部署における人員構成、役職の年齢バランスやスキル偏在などを把握することで、異動の目的を明確にできます。
属人的な判断ではなく、データに基づく「異動の必要性」を特定することで、組織の最適化が進みます。
この段階で、過去の異動履歴や評価データも参照すると、配置の偏りや育成上の課題をより的確に把握できるでしょう。
②異動計画の立案と調整
現状を分析したら、次に異動計画の立案を行います。異動計画を立案する際は、企業戦略・事業計画と人材配置計画を連動させることがポイントです。
どの部署に、どのスキルを持つ人材が、いつまでに必要かを明確化し、短期・中期の異動スケジュールを設計します。
また、管理職層との意見調整や、本人のキャリア希望の反映も重要です。異動計画は、企業の成長と個人の成長の双方を意識して設計することが理想といえます。
③候補者選定と面談プロセス
異動候補者を選定する際は、スキル・評価・キャリア意向の3軸で検討することが有効です。
AIを用いたスキルマッチングやタレントマネジメントシステムを活用することで、客観的な判断が可能になります。
面談時には、本人のキャリア希望や家庭事情や今後の働き方に関する意向も丁寧に確認しましょう。異動の背景や目的を丁寧に伝え、本人が納得して異動を受け入れられるよう、対話を設計することが重要です。
<関連記事>
【事例付き】タレントマネジメントとは?目的、システム導入や比較・活用方法
④通知・引き継ぎ・移行
異動決定後は、スムーズな引き継ぎと移行を支援することが重要です。前任者と後任者の間で情報共有が不十分だと、業務の停滞やミスの原因になります。
人事部は異動通知のタイミングや周知方法を明確にし、受け入れ部署との連携を密にとる必要があります。
また、本人に対しては今後の評価方針や期待役割を具体的に伝えることで、異動後の適応を支援できます。
⑤異動後のフォローアップと評価
異動の最終段階で最も重要なのが、異動後のフォローアップです。
新しい部署や業務に慣れるまでの期間は心理的ストレスが高まりやすいため、異動先の部署と連携しながら、1〜3か月後にフォロー面談を行うことが推奨されます。
また、異動後の評価制度を見直し、短期的な成果だけでなく「適応力」「貢献意欲」「チームワーク」なども含めた多面的評価を取り入れると、従業員の成長を適切に支援できます。
適材適所を実現する異動管理のポイント
異動管理の最終的な目的は、従業員一人一人のスキル・志向と、組織のニーズを一致させることにあります。
単に人を動かすのではなく、「なぜその人を、なぜそのタイミングで動かすのか」を明確にし、企業の戦略と従業員のキャリアを両立させることが、真に適材適所を実現する異動管理といえるでしょう。
ここでは、異動を戦略的に成功させるための3つのポイントを紹介します。
人材データの把握と活用
異動を成功させる第一歩は、人材データの整備と一元管理です。
スキル・経験・評価・キャリア志向などを体系的に可視化することで、属人的な判断を排除し、客観的に「適した人材を適切な場所へ」配置できます。
タレントマネジメントシステムの活用により、複数部門の人材情報をリアルタイムで把握できるようになり、異動の意思決定も迅速化します。
ただし、人材データを異動管理に活用できている企業は依然として少数派です。人材登用や異動・配置・抜てきにおいて、主観に偏らない異動管理を行う姿勢が重要です。
<関連記事>
戦略的な異動計画の立案
異動は短期的な人員調整ではなく、中長期的な経営戦略の一環として位置づけることが重要です。
例えば、次世代リーダー育成や新規事業の拡大など、経営方針に合わせて異動を計画的に実施することで、組織の競争力を高めることができます。
この際、個人の成長段階やキャリアゴールを踏まえた配置を行うと、従業員のモチベーションを維持しつつ、企業の目標達成にもつながります。
従業員の希望を考慮した異動制度
従業員のキャリア意向やライフイベントを考慮した異動制度は、モチベーションの維持・離職防止の観点からも非常に効果的です。
例えば、自己申告制度や社内公募制度を導入することで、従業員自らがキャリアを選択できる環境を整えられます。
また、キャリア面談を定期的に実施し、希望する職種や業務内容を人事データベースに反映することで、企業と従業員の意向をマッチングさせやすくなります。
異動基準や選抜プロセスを明確にし、異動決定後の説明責任を果たすことも重要です。
企業が「公平なプロセスに基づいて判断している」と伝えることで、組織全体の心理的安全性も向上するでしょう。
<関連記事>
社内公募|人材の内部採用に欠かせない「社内公募」を採用管理システムの基盤を使って簡単に運用!
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
人事異動で陥りがちな失敗とその対策
人事異動は組織の成長を支える重要な施策ですが、運用を誤ると従業員のモチベーション低下や離職など、深刻な副作用をもたらすことがあります。
ここでは、企業が陥りやすい3つの失敗パターンと、それぞれの対策を解説します。
納得感の欠如によるモチベーション低下
最も多い失敗の一つが、異動理由や基準が不明確なまま実施されるケースです。
「なぜ自分が異動なのか」「どのような基準で決まったのか」が説明されないまま決定されると、従業員は不信感を抱き、モチベーションの低下につながります。
対策としては、異動決定の背景・目的・期待役割を丁寧に説明し、「成長の機会としての異動」であることを理解してもらうことが大切です。
また、従業員サーベイを定期的に実施することで、意欲低下の兆しを早期に把握できます。
<関連記事>
サーベイ|従業員と組織のコンディションを把握、従業員と組織の状況を可視化し分析、改善をサポート
人材と環境のミスマッチ
異動によって生じる最も深刻な課題が、スキル・適性と配属先業務のミスマッチです。
経験・専門性を十分に考慮せずに配置すると、本人の能力が発揮されず、パフォーマンスの低下や離職リスクにつながります。
このリスクを防ぐには、異動前にスキルマッピングや性格診断などの客観的データを活用し、業務特性と個人の適性を照らし合わせることが有効です。
また、異動直後のフォローアップ面談を定期的に行い、早期にミスマッチを修正できる仕組みを整えましょう。
制度の形骸化と機能不全
異動制度を整備しても、運用が形だけになると効果が失われます。定期異動が目的化していたり、キャリア申告制度が形骸化していたりすると、従業員が「どうせ希望しても反映されない」と感じ、制度への信頼が低下してしまうでしょう。
こうした状態を防ぐには、制度を定期的に見直し、「実際にどれだけキャリア希望が反映されているか」「異動後の成果が上がっているか」を定量的に検証することが重要です。
また、制度運用を管理職任せにせず、人事部門が主導してPDCAを回す体制をつくるとよいでしょう。
効果的な異動管理を実現するためのツール
異動管理を効率的かつ正確に行うためには、ツールの活用が欠かせません。従来は表計算ソフトや紙で管理されることが多かった異動情報ですが、近年はデジタル化が進み、人材データベースやタレントマネジメントシステムを活用する企業が増えています。
ここでは、代表的な異動管理ツールの特徴と、それぞれの活用ポイントを紹介します。
表計算ソフトの利用
多くの企業で導入されているのが、表計算ソフトを用いた異動管理です。
人員一覧・スキル情報・異動履歴を手軽に管理でき、初期コストがかからない点が魅力です。
一方で、データ更新や情報共有に手間がかかり、ファイルが複数存在すると整合性が取れなくなるという課題もあります。
また、担当者変更時の引き継ぎが難しく、属人化しやすい点も課題です。
中小企業や異動頻度の少ない組織では、テンプレート化されたエクセル管理でも十分機能しますが、人材数が多い場合や複数拠点を持つ企業では、システム化を検討することが望ましいでしょう。
タレントマネジメントシステムの活用
近年では、異動管理を含めたタレントマネジメントシステムの導入が急速に進んでいます。
人材のスキル・評価・キャリア志向などを一元的に可視化し、異動候補者の選定をデータドリブンに行えるのが特徴です。
また、過去の評価履歴や職務経歴をもとに「誰をどこに配置すべきか」をシミュレーションできるため、属人的判断を減らし、組織全体の最適配置を実現します。
さらに、異動後のフォローやエンゲージメント状況も追跡でき、単なる人事データ管理にとどまらず「戦略的人材マネジメント」の基盤となります。
<関連記事>
人財活用システム「HRMOS(ハーモス)タレントマネジメント」
コミュニケーションツールの導入
異動管理の際は、コミュニケーションツールを導入して、異動後のフォローアップを体系化する方法があります。
面談の予定調整、議事メモの記録、決定事項と期限の管理、関係者間での共有までをコミュニケーションツールで管理することで、目標進捗や課題が可視化され、対応の漏れを防げます。
異動後1か月・3か月・6か月といった節目ごとに、1on1ミーティングのテンプレートを活用して振り返りを標準化することで、定着支援や課題の早期発見につながります。
異動管理機能と1on1ミーティングの機能をあわせ持つHRMOSタレントマネジメントのようなツールを活用することで、運用の効率化が図れます。
<関連記事>
人事異動の先進企業事例
異動管理は企業文化や経営方針によって大きく異なります。
ここでは、異動を単なる人員調整ではなく「人材戦略の中心」として位置づけている3つの企業の先進事例を紹介します。
SOMPOホールディングス株式会社
SOMPOホールディングスは、「安心・安全・健康のテーマパーク」というグループのパーパスと、従業員のMYパーパスを重ね合わせる人材戦略を基盤に、異動・昇進を公募中心で運用しています。
会社都合の異動・昇進は原則実施せず、部長・課長ポストの多くは職務定義書をグループ内に公開し、応募条件は次のとおりです。
- MYパーパスとポストのミッションが一致していること
- 必要スキルを保有または習得見込みがあること
さらに、異動前後の合意形成と定着支援に向けて、MYパーパスに関する1on1を定期実施し、役員〜課長層にはコーチング研修を提供しています。
このような独自の取り組みによって、「命令による異動」から「パーパス起点の自律的異動」への転換を進めているのが特徴です。
オタフクソース株式会社
オタフクソースは「ものづくりを支えるのは社員一人ひとり」という方針に基づき、正社員を総合職として採用し、部門や職種をまたぐ異動を計画的に運用しています。
新卒は営業や生産に加え、調理講習の実施、イベント運営、取引先へのメニュー提案など、お好み焼文化の普及にかかわる実務へ配属されることが多く、顧客理解や素材・製法への理解を深めてから、職種横断の経験を重ねて視野を広げています。
育成面では、全員必須研修と選択・公募型研修、部門別研修、自己研鑽支援を組み合わせ、集合研修は事前準備と研修後の課題まで一体で設計しています。
資格や語学、異業種研修など就業時間外の学習も費用補助の対象とし、異動後の立ち上がりの早期化と定着の促進につなげています。
オリックス銀行株式会社
オリックス銀行株式会社は、事業拡大とキャリア採用の強化に合わせ、キャリア自律を前提にした異動・育成の仕組みを整備しています。
2022年には、管理職を目指す「マネジメント職」と、専門性を深める「エキスパート職」の複線型キャリアパスを導入しました。若手期からの1on1と年1回のキャリア面談で本人の志向と組織ニーズをすり合わせ、昇格面談時に進路を選択できる運用としています。
また、オリックスグループ全体の「キャリアチャレンジ制度」により、本人の応募に基づくグループ内出向(原則3年)の機会を提供しています。
加えて、階層別研修に加えた選抜型・テーマ別研修や自己研鑽の補助を行い、異動後の活躍を支えるスキル獲得を後押ししている点が特徴です。
<関連記事>
キャリアパスとは? キャリアプランとの違いやITエンジニアなど職種別具体例
これからの時代に求められる異動管理の在り方
人事異動はこれまで「会社主導の配置転換」が中心でしたが、今後は従業員の自律性を尊重し、データと対話を軸にした「共創型異動」へと進化しています。
社会・働き方・価値観の変化により、異動管理も新しい時代の要請に合わせて変革が求められています。
働き方の多様化への対応
リモートワーク、副業、時短勤務、副業解禁など、働き方は多様化の一途をたどっています。従来の「勤務地や勤務形態を固定する異動管理」では、従業員の多様なニーズに応えられません。
これからの異動管理では、柔軟な働き方を前提とした制度設計が重要になります。
例えば、「リモート異動(勤務地は変えずに職務のみ変更)」「短期プロジェクト型異動」など、時間や場所に縛られない配置を可能にすることで、スキル循環とキャリア形成の両立が可能になります。
デジタル化時代の人材戦略
AI・データ分析技術の進展により、異動管理にもデータドリブンな意思決定が求められるようになっています。
人材データベースやスキルマップ、AIマッチングなどの活用により、適性・評価・キャリア志向を総合的に分析し、科学的根拠に基づいた人材配置が可能になります。
また、異動後の定着や活躍度を可視化する「人材分析(ピープルアナリティクス)」の導入も進んでおり、人事担当者は感覚や経験則に頼った判断から、データに基づいて説明できる異動へと変わりつつあります。
<関連記事>
持続可能な組織づくりのための異動
人的資本経営が注目される中、異動は単なる人員再配置ではなく、組織の持続性を支える仕組みとして再定義されています。
従業員一人一人のキャリア自律を支援し、スキルを社内で循環させることで、外部採用に頼らずに競争力を維持できる「リスキリング型組織」への転換が進んでいます。
また、ダイバーシティ推進の観点からも、年齢・性別・勤務地などにとらわれない異動機会の提供が不可欠です。
多様な人材が活躍する土壌をつくることが、異動戦略を通じた組織の強靭化につながります。
これからの異動管理は、単なる配置転換ではなく、「人が活きる環境づくり」そのものを設計する経営施策です。
データと対話を生かした戦略的人事を通じて、企業と個人が共に成長できる仕組みを築くことが、次代の異動管理に求められる姿といえるでしょう。
<関連記事>
従業員エンゲージメントとは? 高める方法や事例から学ぶ成功のポイントを解説
まとめ
異動管理は、人員の入れ替えではなく、組織戦略と人材育成を結ぶ重要なプロセスです。
データに基づく配置判断と、従業員のキャリア意向の反映、そして異動後のフォローまでを丁寧に行うことで、定着と業務品質の向上につながります。
異動を仕組みとして運用し、その結果を次の配置に生かすことで、個人の成長と組織の目標達成の双方に貢献できるでしょう。
HRMOSタレントマネジメントで実現する「社内版ビズリーチ」
HRMOSタレントマネジメントは、異動管理を含む戦略的人材活用の中核ツールとして多くの企業で導入が進んでいます。中でも「社内公募機能」は、従業員のスキルと社内のポジション要件を可視化し、社内で挑戦したいポジションを選択したり、欲しい人材にスカウトを送ったりすることができます。
さらに、採用管理システム基盤を生かした「求人作成・選考フローの自動化」や、従業員限定の安全な閲覧環境など、セキュリティ面でも安心。「異動を命令から選択へ」変える仕組みとして注目を集めています。
サービスの詳細はこちらからご確認ください。