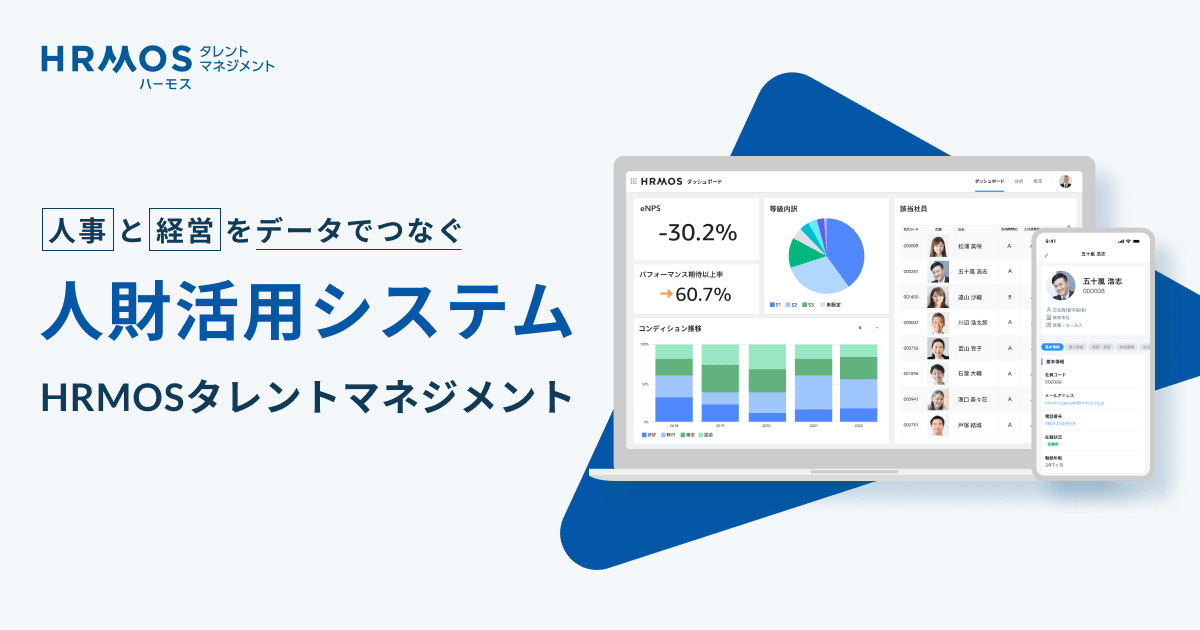目次
多くの企業が採用したいと口を揃える「ハイパフォーマー」。
人材不足により大量採用によって労働力が補えない現代では、一人一人の能力を引き出して生産性を高めることが重要です。
本記事ではハイパフォーマーの定義、主な特徴や行動特性、採用・育成のポイントや退職を防ぐ方法を解説します。
ハイパフォーマーの定義
はじめに、ハイパフォーマーの定義を解説します。
ハイパフォーマーとは
ハイパフォーマーとは、継続的に高い成果を上げ、企業の業績に大きく貢献する人材を指します。必要なスキルや経験を備えているだけでなく、周囲へよい影響を与える存在でもあり、組織には次のような効果をもたらします。
- 生産性の向上
- チームワークの活性化
- 従業員のモチベーション向上
また、組織における成果配分を示す「2:6:2の法則」では、成果の約8割を上位2割のハイパフォーマーが生み出すとされています。残りは6割がミドルパフォーマー、2割がローパフォーマーに位置づけられます。
つまり、ハイパフォーマーは単に成果を上げるだけでなく、組織全体を牽引する存在であり、その活躍は企業の競争力を大きく左右するといえるでしょう。
ローパフォーマーとは
ローパフォーマーとは、ハイパフォーマーとは逆に十分な成果を発揮できていない人材を指します。
単に成果が低いだけでなく、場合によっては仕事への意欲が下がったり、ネガティブな姿勢が目立ったりすることもあります。その状態が続くと、周囲のモチベーションや組織全体の雰囲気に悪影響を与える恐れがあります。
そのため、従業員がローパフォーマー化しないよう、適切なフォローや育成の仕組みを整えることが重要です。
ELTVとの関係性

「ELTV(Employee LifeTime Value)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。日本語でいうと「従業員生涯価値」のことで、一人の従業員が、入社してから退職するまでに生み出したアウトプットの総量を測る指標です。
ELTVの最大化を目指すための要素は2つあります。
1つは、従業員のアウトプット(成果)を増やして縦軸の数値を伸ばす方法で、もう1つは従業員に長く働いてもらうことで横軸の数値を伸ばす方法です。
ELTVの観点から、高い成果を出すハイパフォーマーには長く活躍してもらうことでアウトプットの総量は高まっていくと考えられます。
つまり、組織はハイパフォーマーに長く働いてもらうための施策や対策を行う必要があります。
<関連記事>
・部署やチームを横断した最適な人材配置が難しい…
↓
従業員の保有スキルを1クリックで可視化・分析できて、スキルマップの自動作成で人材の過不足が一目瞭然に
⇒【スキル管理機能】デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
ハイパフォーマーの主な特徴と行動特性
ハイパフォーマーの主な特徴と行動特性を8つご紹介します。自社の人材と照らし合わせて確認してみてください。
1.成果にこだわる
ハイパフォーマーは成果を出すことに強いこだわりを持っています。企業や組織が掲げる目標を正確に理解し、その達成に向けて何をすべきかを自ら考え、試行錯誤を重ねながら成果へと結びつけます。
その過程では、優れた問題解決能力や戦略的思考を発揮するだけでなく、環境の変化に柔軟に対応できる適応力も欠かせません。
さらに、単に求められた水準を満たすだけでなく、「期待を超える成果を出す」という意識が高い点も、ハイパフォーマーならではの特徴といえるでしょう。
2.行動力がある
ハイパフォーマーは掲げた目標や成果から逆算し、今何が必要か・何に取り組むべきかを自ら明確にしながら戦略的に考え、自ら実行に移す力があります。
もちろん失敗する場合もありますが、何が問題だったのか、成功するためには何が必要かを考える優れた問題解決能力や適応力を持ち、挑戦を継続できることもハイパフォーマーの特徴です。
ただし、単に行動することが正しいわけではありません。チャレンジ精神に加えて、目標やゴールに向かって道筋を立て、正しいマイルストーンを設定する力が求められます。
3.コミュニケーション能力が高い
コミュニケーション能力が高いこともハイパフォーマーの特徴の一つです。
どれだけスキルや知識を持っていても、一人で生み出す成果には限界があります。より高い成果を出すために、社内外の関係者とのコミュニケーションは必須といえます。
ハイパフォーマーは周囲との信頼関係を築き、円滑なコミュニケーションによって成果を最大化する存在です。
4.ポジティブ思考
成果を出す過程では、誰しも壁にぶつかったり失敗を経験したりします。ハイパフォーマーはそうした状況でも前向きに業務へ取り組み、最善を尽くす姿勢を崩しません。
失敗しても諦めるのではなく、現状を打開する方法を考え実行し、最終的に成果へとつなげます。その前向きな姿勢が、成果だけでなく周囲からの信頼や評価にもつながっていきます。
5.周囲のメンバーからの信頼が厚い
周囲のメンバーから厚い信頼を得ているのもハイパフォーマーの特徴です。高い成果を出すためには周囲の協力が必要不可欠ですが、ハイパフォーマーは自身のスキルや経験、ノウハウを積極的に周囲へ伝えたり、周囲のメンバーが困ったりしていれば積極的にサポートします。
また年次や役職に関係なくすべての人に敬意を持って接することができ、ときには建設的な批判を受け止めるなど、チームメンバーに心理的安全性をもたらすことができます。
ハイパフォーマーのこのような姿勢により、自然と周囲のメンバーから信頼を獲得し、社内外から頼られる存在になるでしょう。
<関連記事>
職場の心理的安全性とは?作り方や4つの因子、高める方法を解説
6.積極的に自己研鑽をしている
ハイパフォーマーは積極的に自己研鑽を続けています。
ビジネスの環境は常に変化しており、今持っている知識やスキルだけでは成果を出すことが難しくなっていく恐れがあります。
ハイパフォーマーは目まぐるしく変化する世の中で、どのようなスキルや知識が求められるか高いアンテナを張り、絶えず学び続ける姿勢を持ち、自身の成長に積極的です。
7.優れたセルフマネジメント
セルフマネジメントに優れているのもハイパフォーマーの特徴です。
高い成果を出し続けるためには、体調管理や業務量のコントロールが欠かせません。さらに、環境の変化や失敗に直面しても立ち直るレジリエンス、感情を整えるアンガーマネジメント、集中力や内省力を高めるマインドフルネスといった力も重要です。
こうしたセルフマネジメントによって、ハイパフォーマーは誘惑に負けず、目標に向けてやるべきことに集中できるのです。
<関連記事>
マインドフルネスとは? 企業に導入する方法や瞑想のやり方、効果を解説
8.健康的なワーク・ライフ・バランス
ハイパフォーマーは仕事とプライベートのメリハリをつけるのも上手です。仕事で成果を出すために、十分な休憩や睡眠を取り、食事や運動にも気を配ってコンディションを整えています。
常に高い生産性を維持するために、オンとオフの切り替えを意識的に行っているのも特徴です。
一方で、ワーカホリックやバーンアウトには注意が必要です。仕事へ過度に依存したり、ストレスや疲労を抱え込んだまま放置したりすると、心身の不調を招く恐れがあるからです。
<関連記事>
ワーク・ライフ・バランスとは? 使い方や例文、企業の取り組み事例を簡単に解説
ただし、たとえ一般的にハイパフォーマーに必要とされる要素、例えば高いスキルや経験、問題解決力や適応力を備えていても、必ずしもどの企業や組織でも成果を発揮できるとは限りません。
求められる役割や成果の基準は組織ごとに異なり、個人の能力と環境がかみ合わなければ、その力を十分に生かせない場合もある点に注意しましょう。
ハイパフォーマーの分析方法
自社のハイパフォーマーを明確にするには、まず各部署・組織単位で現在活躍している人材を分析することが重要です。
現在、自社でハイパフォーマーとして活躍している人材には、どのような特徴や共通点があるのか要素分解し、明らかにする必要があります。
ここでは代表的なハイパフォーマーの分析方法の一例をご紹介します。
必要なデータを集める
ハイパフォーマーを分析するにあたり、まずは次のデータを集めましょう。
- 属性データ:年齢、性別、最終学歴、高校の偏差値、転職回数
- 行動データ:勤怠、スケジュール(営業時間、会議時間、事務時間)
- 評価データ:人事評価(行動評価、実績評価)
- 入社時のデータ:選考時の履歴書・職務経歴書・エントリーシート、適性検査(能力検査・性格検査)の結果
平均値を比較する
次に集めたデータを用いて、ハイパフォーマーとその他の従業員グループにおける各種データの平均値を比較します。
次のような属性をハイパフォーマーと比較すると、有効な結果を得られるでしょう。
- ローパフォーマー群
- 全従業員
- 特定の部署、入社年次など
相関関係を分析する
集めたデータの間に相関関係があるかを調べることも有効な分析方法です。
例えば、評価データと入社時のデータに相関関係があるかなど、各項目との相関関係を求めることでパフォーマンスとの関係性を分析することができます。
そのほか、重回帰分析(複数の変数と成果の関係を同時に分析する手法)など複数の分析手法やデータ集計方法を用いることで、適切な分析ができるようになります。
・「なんとなく」や特定の人の勘 に頼った配置 から脱却したい
↓
従業員のスキルを可視化し、組織の課題を可視化。評価・育成記録まで 一元管理 し、データに基づいた配置を実現
⇒デモ画面付き解説資料のダウンロード(無料)はこちら
ハイパフォーマーを増やすには
自社にハイパフォーマーを増やすには、適性を見極めた人材の採用と、既存従業員の育成が欠かせません。
ハイパフォーマーを増やすための取り組みとして、採用と育成、2つのステップをご紹介します。
採用
ハイパフォーマーを増やすためには、まず採用の段階で自社に合った人材を見極める必要があります。スキルや経験だけでなく、組織文化やチームとの相性も重視することで、採用後に力を発揮できる人材を迎え入れることができます。ここでは、採用における具体的なポイントを見ていきましょう。
ハイパフォーマーの定義を人材要件へ反映
自社におけるハイパフォーマーを正しく定義できたら、次はその定義を人材要件へ反映します。職種や組織ごとにハイパフォーマーの定義も異なるため、それぞれについて人材要件を設定することが必要です。
<関連記事>
人材要件とは何か?フレームワークの定義から設定までの具体例を解説
採用活動
採用活動では、通常の採用活動や社員紹介制度(リファラル採用)など採用経路にかかわらず、ハイパフォーマーの定義に基づいた人材要件を設定することで、採用したい人材像が明確になります。
その人材像に基づいて選考時の見極めを行うことで、面接担当者による判断のブレも軽減できるでしょう。
面接担当者による判断のばらつきを軽減するためには、採用担当者のトレーニング、評定シートを準備するなどの方法が挙げられます。また適性検査を用いることでミスマッチ防止につながります。
<関連記事>
リファラル採用とは?メリット・デメリットと成果を出すためのポイントを紹介
育成
ハイパフォーマーの前提となる「成果」は、適切に計測してこそ比較できます。そのためにはまず個人やチームに課される「目標」を適切に設定して管理し、また適切に評価を行うことが必要です。
適切な目標管理と評価
目標管理では、OKR(Objectives and Key Results)やMBO(目標管理制度)などのマネジメント手法を用いることも効果的です。
評価の際は、成果が正しく評価される仕組みや昇進・昇格、昇給、キャリアパスを明示することで、モチベーション高く業務に取り組めるでしょう。
<関連記事>
OKRとは? OKRの要素や導入メリット・OKR運用サイクルの流れを解説
パフォーマンスを上げるための研修実施
ハイパフォーマーの定義によって明らかになった要素を、研修などによって既存の従業員に習得してもらうことで、パフォーマンスを上げることができます。
また研修後のフォローも重要です。フォローを実施しないと研修で学んだ内容が十分に定着せず、期待していた効果を得にくくなります。
研修以外にもコーチングの実施やOJT、メンターの活用をはじめ、業務中に機会を提供しながら従業員の成長を促すことも効果的です。
<関連記事>
コーチングとは?スキルやロールプレイの事例、ティーチングとの違いを解説
異動・配置
目標管理や研修を行ってもなかなかパフォーマンスが向上せず、パフォーマンスが低下している可能性も考えられます。
ローパフォーマーの業務適性が現在の業務とマッチしていない場合は、異動や配置転換を検討しましょう。本人の適性を見極めたうえで、最適な業務を任せることでパフォーマンスの向上が期待できます。
<関連記事>
適材適所な人員配置を実現するには?-4つのポイントとフォローアップ-
ハイパフォーマーの退職を防ぐ方法
ハイパフォーマーの採用や育成は重要ですが、企業や組織が高い成果を上げ続けるためには、現在活躍している人材の退職を防ぐことも不可欠です。
高い成果を残すハイパフォーマーは、競合他社などからヘッドハンティングされやすく、わずかな不満で退職する可能性があります。ハイパフォーマー自身もやりがいを求めたり、環境や処遇の改善を目指して退職したりする恐れもあるでしょう。
ハイパフォーマーの退職を防ぐために何をすべきか、その方法を紹介します。
適切な評価制度の構築
ハイパフォーマーの退職を防ぐために、成果に対して適切な評価を行う評価制度の構築が必要です。
ハイパフォーマーの退職理由の一つに、「成果に対して評価が適切でないと感じる」ことが挙げられます。高い成果を上げても評価が変わらなかったり、自身が思っていたほど評価を得られなかったりすると、業務へのモチベーションが下がる恐れがあります。
昇進・昇格や昇給、キャリアパスなどの評価基準を明確にして、従業員にとって納得度の高い評価を行いましょう。
<関連記事>
キャリアパスとは? キャリアプランとの違いやITエンジニアなど職種別具体例
適切な裁量権
適切な裁量を持たせることで、意欲や定着率の向上が期待できます。
単に与えられた仕事をするのではなく、新しいことや難しいことに挑戦する姿勢を持ったハイパフォーマーも少なくありません。
そのため、業務の進め方や業務上の判断など一定の裁量権を与えることでモチベーションを維持して業務に取り組むことができるでしょう。
ただし、裁量権を与えすぎると組織全体のマネジメントに影響を及ぼす可能性もあるため、裁量権の範囲は慎重に検討する必要があります。
ワーク・ライフ・バランスへの配慮
ハイパフォーマーのワーク・ライフ・バランスへの配慮も欠かせません。
高い成果を期待されるあまり、ハイパフォーマーに業務が偏る傾向もあります。
結果として他の従業員よりも抱える業務が増え、プライベートの時間が確保できず、ワーク・ライフ・バランスの改善を求めて退職を考えることも少なくありません。
ハイパフォーマーに業務が集中しすぎないよう、組織全体で業務量を調整し、ハイパフォーマーに限らず従業員のワーク・ライフ・バランスへ配慮することが必要です。
<関連記事>
ワーク・ライフ・バランスとは? 使い方や例文、企業の取り組み事例を簡単に解説
ローパフォーマーの底上げ
ローパフォーマーの底上げをすることで、ハイパフォーマーの退職防止につながります。
成果を出せないローパフォーマーがいると、その分の業務や目標がハイパフォーマーの負担になり、業務量が増加します。また評価方法によってはハイパフォーマーが高い成果を出しても評価されず、不満を抱えてしまうかもしれません。
ローパフォーマーをゼロにすることは難しいものです。しかし、適切な目標設定や研修の実施、周囲のサポート体制を整えることでローパフォーマーの成長を促し、成果の向上が期待できます。
結果としてハイパフォーマーの負担が軽減され、不満も緩和されるでしょう。
定期的なフォロー
定期的にハイパフォーマーをフォローすることも重要な退職防止策です。
ハイパフォーマーは能動的に業務に取り組み、成果を出してくれるため、フォローの必要がないと考える管理職も少なくありません。しかし、ハイパフォーマーも不満や悩み、ストレスを抱えていることがあるでしょう。それらを誰にも相談できず、退職につながってしまうことがあります。
ハイパフォーマーだからと任せきりにせず、1on1など定期的な面談機会を設け、フォローを行いましょう。必ずしも本音を話してくれるとは限りませんので、エンゲージメントサーベイなどを用いて状況を把握することも有用です。
<関連記事>
従業員エンゲージメントとは? 高める方法や事例から学ぶ成功のポイントを解説
システムを活用した企業の改善事例多数
株式会社サンリオ、トヨタカローラ山形株式会社、株式会社GA technologiesなど、どのような効果が得られたのか分かる事例を公開中
ハイパフォーマーと類似する概念
企業が成長し、生産性を高めるためには、ハイパフォーマーに加えて、別の観点からも重要とされる人材の存在が欠かせません。
ここでは、そうした人材の代表例として「ハイポテンシャル人材」と「イノベーション人材」について解説します。
ハイポテンシャル人材との違い
ハイポテンシャル人材とは、将来の経営幹部候補を指します。企業の持続的な成長において欠かせない存在です。
具体的には、上昇志向を持ち、経営幹部としての資質や知識を備えていることに加え、企業や組織への高いエンゲージメントを持ち、現在の職務でも優れた成果を出している人材が該当します。
言い換えれば、ハイパフォーマーの中でも将来のリーダーに求められる素養を備えた人材が、ハイポテンシャル人材にあたります。
<関連記事>
イノベーション人材との違い
イノベーション人材とは「モノ」や「サービス」のほか、「仕組み」「組織」「ビジネスモデル」などに対し、今までにない価値を提案・提供できる人材を指します。
現代の市場は変化が激しく、新しいサービスやモノなどイノベーションの創出が企業の発展には不可欠な存在といえるでしょう。
イノベーション人材には「アイデアを出せる人材」と「事業を成長させる人材」の2つのタイプがあります。
ハイパフォーマーは「高い成果を上げる人材」ですが、必ずしも「アイデアを出せる人材」や「事業を成長させる人材」とは限りません。
<関連記事>
イノベーション人材とは? 育成方法や事例、求められる能力について解説
まとめ
高い成果を出せるハイパフォーマーはどの企業にとっても、採用したいと考える人材ですが、採用や育成、定着は課題が多い状況です。
ハイパフォーマーを増やすためにはまずハイパフォーマーの特徴や行動特性を把握し、自社で活躍するハイパフォーマーを定義しましょう。
定義した内容を人材要件に盛り込み、採用や育成のプロセスに反映させましょう。また、ハイパフォーマーが定着するよう、退職を防ぐ取り組みやローパフォーマーの底上げも同時に進めると効果的です。
ハイパフォーマーは業界や職種、企業の文化によって定義は異なります。
自社で活躍する人材の傾向を分析し、組織に最適なハイパフォーマー像を見極めることが重要です。
HRMOSタレントマネジメントでハイパフォーマーを増やそう
HRMOSタレントマネジメントでは、人材データの蓄積・分析を通じて、ハイパフォーマーの特徴や行動特性の可視化を支援します。
また評価やサーベイ、1on1支援などハイパフォーマーを増やすためのツールが整っています。
HRMOSタレントマネジメントを活用して、自社で活躍するハイパフォーマーを定義し、数多くのハイパフォーマーが活躍する環境や制度を整えましょう。